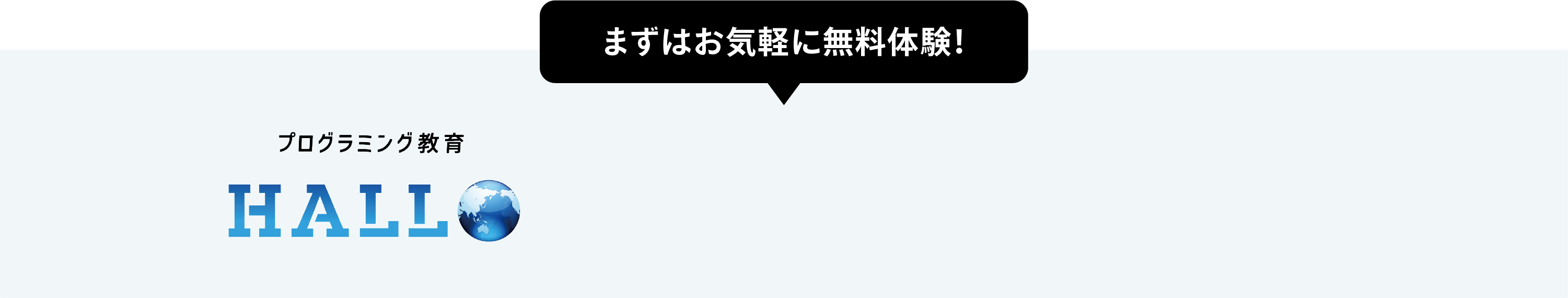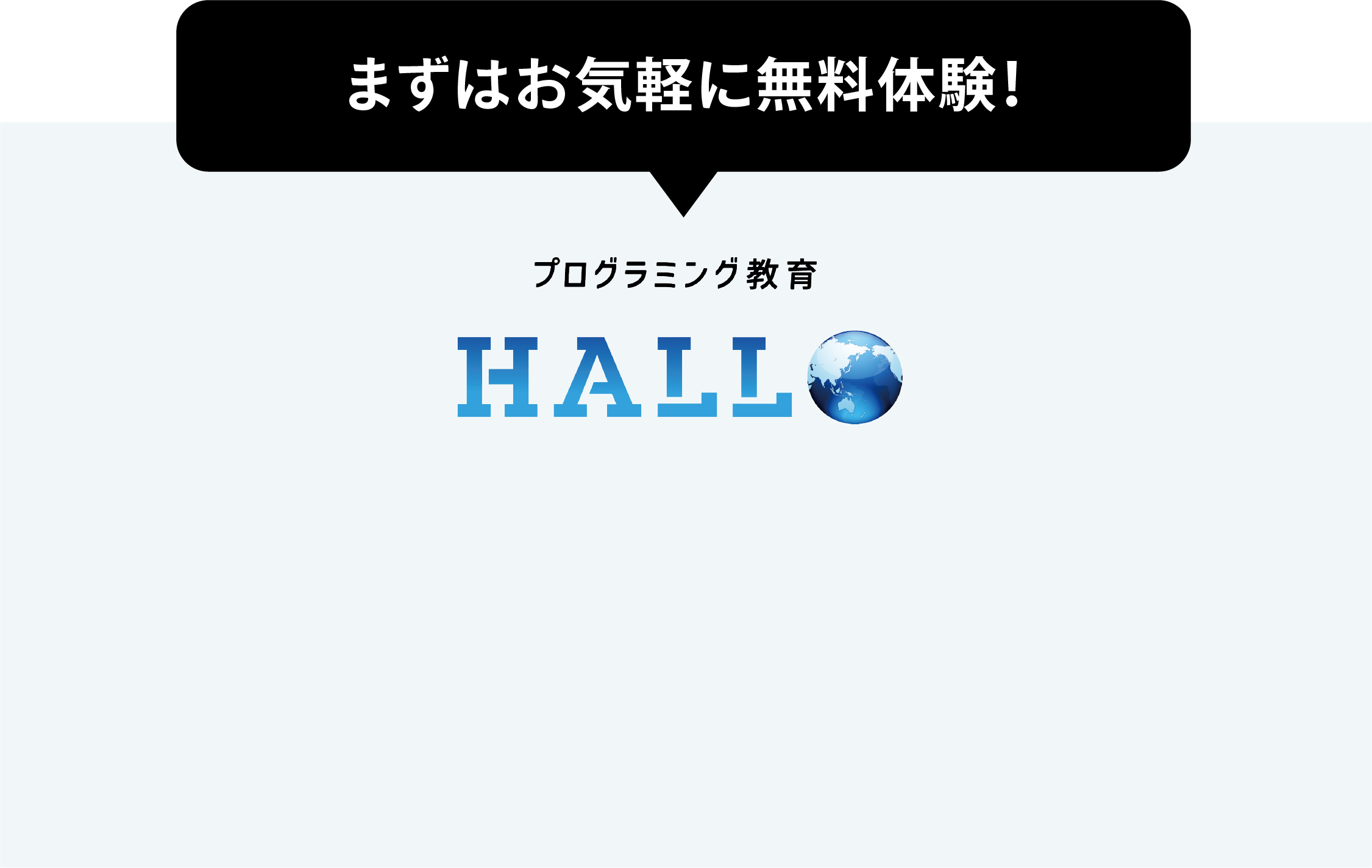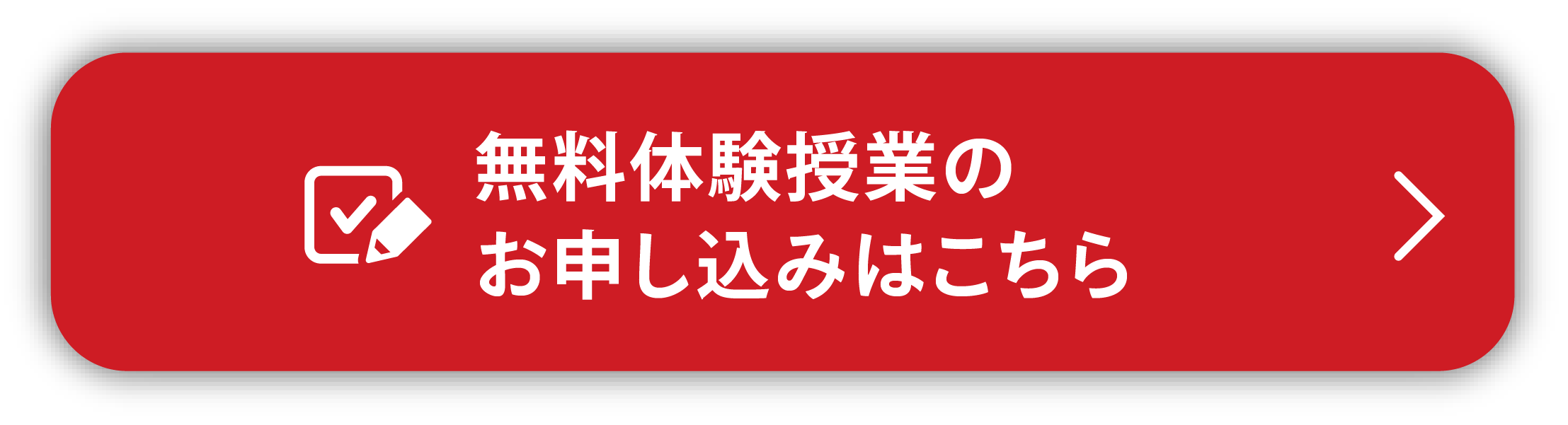マイクラを使ったプログラミング教室は意味ない?理由やメリットを詳しく解説
公開日:2025.4.21
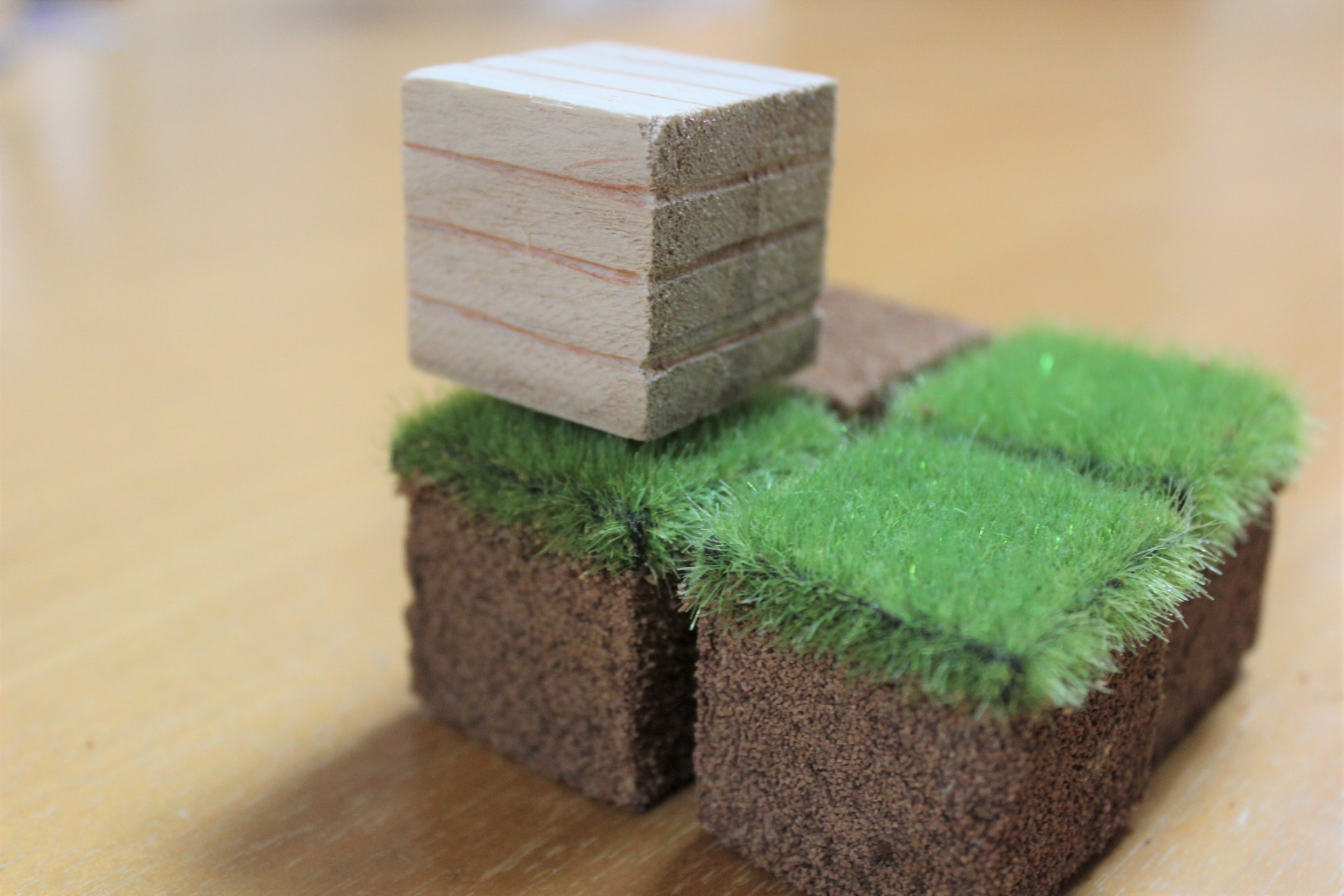
子どもたちの未曾有の創造力を伸ばし、かつ問題解決能力を育むことのできるプログラミング教育。その教室での授業のツールとして通称「マイクラ」が選ばれているのは、子どもたちのモチベーションをより高め、さらなる能力開発をもたらすことが期待できるからです。正式名称「マインクラフト」は世界的に大人気のゲームのこと。美しいCG(コンピュータ・グラフィックス)の世界に入り込み、自由自在に行動して冒険や街を構築していくモノづくりの楽しさがあり、多くの人たちが年齢や性別を問わず夢中になっています。
ゲームと教育というと無関係にも捉えられがちですが、実は学習とくにプログラミング学習との相性が抜群なのです。その理由、驚くべき効果のメカニズムをご紹介します。
この記事の目次
マイクラを使ったプログラミング教室は意味ない?
マイクラは普通にプレイして楽しいゲームですが、それを例えば自宅でやるのとプログラミング教室の授業としてすることの大きな違いは「目的」「目標」「ゴール」がきっちりと定められているかどうかということです。その目的つまりプログラミングスキルを磨き、問題解決能力を養っていくには最適な環境づくりと、ゴールへと導くメンター(導き手)として、講師によるガイドがとても重要になります。
また、歳の近い仲間がいると楽しみが増え、学習する意欲も高まります。共に学び成長していける仲間と適切な指導をしてくれる講師がいる教室に所属することの効果があるからこそ、プログラミング教室に多くの子どもたちが集まっているのです。
マイクラを使ったプログラミング教室が「意味ない」と言われる理由

それでも、マイクラを使ったプログラミング教室の効果について、疑問の声があがっているのも事実です。ここでは、そうした疑問点のうち代表的なものを3つ挙げて、なぜ「意味がない」と言われるのかその理由と共に実際はどうなのか解説していきます。
実践的な内容ではないから
まずマイクラのプログラミング教室で子どもを学ばせても、実践的なプログラミングスキル習得には直接結びつかないとの声があがります。実践的なスキルとして挙げられるのはコーディング・スキルであり、それを身につけるためのスクールなのだから、意味がないというのです。
この指摘の通り、マイクラのプログラミング教室ではシステム開発やアプリ開発で使われるプログラミング言語を学ぶわけではありません。ビジュアルによるプログラミングを学びのメインとしています。しかし実はこれこそがプログラミングの土台となる基礎を養うレッスンなのです。
マイクラでは物事を自らの頭で考え、ゴールを具体的に思い浮かべ、それを実現するためのルートを導き出していく構想・構成力が求められます。そしてそのために課題を具体的にひとつずつクリアしていかなければなりません。実践的なスキルももちろん必要ですが、そのスキルを使いこなすバックボーンをつくり、プログラミング頭脳を養成していくのです。
授業料が高い傾向にあるから
マイクラのプログラミング教室は、授業料が高いとの指摘もあります。習い事として見て、一般的なプログラミング教室の月会費は約10,000円ですが、マイクラを使う教室の場合、10,000~30,000円程度になります。10,000円前後の入会金が設定されていることもあります。オンラインか教室での対面形式か、教室でも運営形態やカリキュラムによって異なりますが、一般的なプログラミング教室よりも高めの料金設定であることは事実です。これには教材として使われるマイクラのライセンスなどにコストがかかる上、どの教室であれほとんどが専用カリキュラムを開発し最先端の授業を提供しようとしているからです。
マイクラを使うプログラミング教室は、プログラミングの技術というよりその土台、基礎の部分の能力を養っていくものです。技術ももちろん必要ですが、子どもたちの将来を見据え、有能なプログラマーを養成するためのカリキュラムに注力し充実させようとしています。そのため、授業料に見合ったリターンはあるはずです。短期コースや集中講座、無料または低価格の体験授業もあるので、そうした選択肢も使い精査してみてください。
独学で身につけることもできるから
オンライン講座や動画もありますし、初心者のスタートアップに必要なことを記した書籍も多数出ていて、それらを活用すれば自宅で独学をしてもプログラミングを習得していくことはできます。そのため、教室に通う必要はないという意見も少なくありません。ただし、何を学ぶにしてもそれが習い事であれ勉強であれ、指導するメンターや講師がいるのといないとでは雲泥の差があります。
スポーツや勉強など物事を習得するためには自分の頭で考えて、動かなければ本当の意味でそれを身につけることはできません。
プログラミングでは、必ず困難な課題に直面します。そうした場面で、同じ学びの場にいる仲間から励ましをもらい、講師陣に指導を求めることができることがどれだけの当人の背中を押すことになるかは、これまでいくつもの学びの場を経験してきた保護者の方なら身をもってご存知のはずです。成長や成果を喜び、ときに厳しく背中を押してくれる環境や教室こそ、物事を学ぶ最も恵まれた場所なのです。
マイクラを使ったプログラミング教室に通うメリット
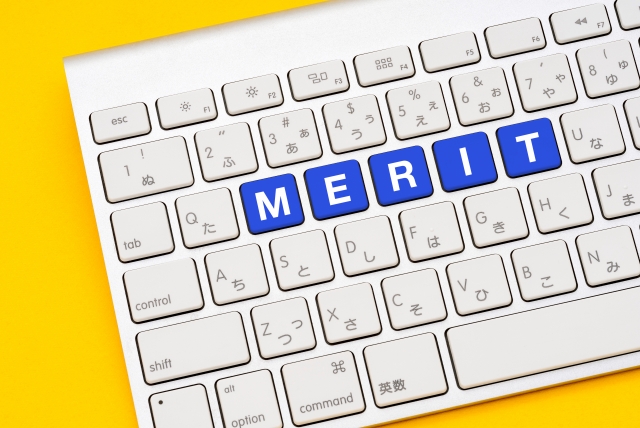
教室に通うことのメリットはいくつもあります。卒業生の口コミでも、楽しみながら学べたとの声がたくさんあがっており、もちろんプログラミングのスキル習得に役立ち、メンタルや思考から成長したと実感する声が寄せられています。それはどういうことなのか、詳しく紹介していきます。
楽しみながら学ぶことができる
学びには努力が必要ですが、同じ努力でも楽しみながらできるのであれば苦痛にはなりません。教室で学ぶ大きなメリットはそこにあり、子どもはより大きな成果をあげることに喜びを感じます。
楽しければ学ぶ時間を忘れてしまうほど集中でき、もっと先へ進みたいというモチベーションにも繋がります。
マイクラ自体はゲームですので、子どもたちにとって、入り口のハードルは高くありません。むしろ大好きなもののひとつですから、興味関心を持って進めていくことができます。ゲーム自体のゴールは街づくりです。大人でも目を見張るような立派な建造物を効率よく仕上げていく子どももいれば、独自の世界観を持っている子どももいます。
どちらが正しいというのではなく、どのタイプであれ、独自の世界をつくりだし伸ばしていくことから始めるのがマイクラを使ったプログラミング教室の根幹です。そしてその力は楽しむことによって引き出されていくのです。
関連リンク:https://www.hallo.jp/fs/column/20220920/
パソコンのスキルが身に付く
一般的なプログラミング教室での実践的なスキルの習得よりも、その土台や基礎となる知力やマインドセットを養成するのがマイクラを使ったプログラミング学習です。その学びの中で、結果的に様々なスキルを身に付けることができたとの声も少なくありません。
そのひとつがパソコンのスキルです。マイクラでは、主人公のキャラクターとして行動します。動かすにはパソコンのキーボードやマウスを操作しなければなりませんし、「コード」と呼ばれる命令文への理解が求められます。
自転車に乗る練習と同様に、何度も繰り返し練習することで、子どもはその方法を習得していきます。たとえば日本語入力の方法や先生への質問で、メールやチャットを使いこなせるようになるなど、ひとつひとつを習得していくうちにパソコンに慣れ、機能を知り、親しみ、自然と使いこなせるようになっていくのです。
先生のアドバイスを聞くうちに、自分で検索し、解決を見出していくことも覚えていきます。その精度やスピードが日増しに高まっていく子どもたちの姿が教室では当たり前のように見られています。
主体性、問題解決能力などが身に付く
マイクラを使ったプログラミング教室は、学校の授業で昔から見られるような先生の話を聞いて、ノートに授業内容を書き写すだけのものとは違います。基本を学んで、ゲームをどのようにして攻略していくのか、何を作っていけばよりよくなるのかを考えるのは子ども自身であり、先生はあくまで子どもたちのサポート役です。
そうした環境での学びが主体性を育み、問題解決能力を高めることにつながるのです。
かねてより日本社会では、指示を受けて、それを全うする社会人が有能と評価される傾向にありましたが、現在は「指示待ち人間」などと呼ばれ、組織よりも、個として企画を発案しそれを実行し成果を挙げていくようなフロンティアタイプが社会を引っ張っていく時代へと移り変わっています。
そんな新時代を生きていく子どもたちがマイクラを通じて司令塔や指揮官となり、またヒーローとしてキャラクターを動かすことで自ら世界を切り開いていく人材になれることでしょう。
創造性や想像力が養われる
マイクラを使ったプログラミング教室では、「自分の思い描いた世界をつくることができてうれしい」との声が聞かれます。プログラミングの世界もスキルが必要ですが、そもそも、そのもととなるグランドデザインを思い描くことのできる創造性や世界観がなければはじまりません。子どもたちは教室という学びの場にいながら、創造性を育んでいき自由に発想することを覚えていくのです。
また、マイクラは仮想現実ですが、その世界は3Dです。平面ではなく立体の現実世界と同様の空間が広がっています。そのゲームの世界では3方向に座標があり、それを使って移動し空間を自在に操ることができます。その全能感が子どもたちの想像力を刺激していくのです。サッカーやラグビーではこうした空間認識能力を「スキャナー」と呼び、一部のスター選手が備えているといわれています。ピッチ上にいながら、はるか上空から試合のポジショニングを俯瞰し把握することのできる能力と同等の能力が育まれるかもしれません。
将来の仕事の選択肢が広がる
マイクラによる英才教育は、子どもたちが将来やりたいと思える仕事の選択肢を広げることにつながります。
様々な素材を組み合わせてのモノづくりを経験することは、多くの学びとなります。
それは将来、独自の作品を作り出すデザイナーなどのクリエイティブな仕事も選択肢として広がります。マイクラで行っているように建物に興味を持ったなら、建築家等を目指して、街づくりなどで社会に貢献していく仕事も夢ではないでしょう。
ゲームのなかであれば、たとえば弓矢を手に入れるために森の木を切り倒し、原木を木材に加工して棒とし、さらに棒の両端を結ぶ糸を入手して固定しなければなりません。このような原始的な体験が創造力を養っていくのです。
マイクラのようなゲームを知育ゲームとも呼ぶのは、ゴール設定のみならずそこに到達するための道筋を効率よく論理的に思考して課題を克服し、状況に応じて臨機応変に計画を変更したり工夫しながら実行することで知性が伸びるからです。実際に職業選択を考える年齢になった際に、これらの体験が有効に働く可能性も大いにあります。
集中力を身に付けられる
マイクラの世界に没頭し、楽しみながらプログラミングを学ぶことで、子どもは自然と集中力を身につけることができます。近年、小学校などで注意力散漫な子どもたちが授業中に教室を走り回る光景が問題視されることもありますが、実際、授業中にじっと座っているのが難しい子どもたちも少なくありません。
しかし、無理に座らせておくことが解決策ではありません。大切なのは、子どもたちが自ら興味を持ち、没頭できるような環境を整え、そこに居場所を作ることです。モチベーションが集中力を高め、時間を忘れるほどの没頭をマイクラを通じて経験することが、子どもたちにとって大きな成長のきっかけになるかもしれません。
そのため、教育現場でも情操教育の観点からも、マイクラを使ったプログラミング教室への期待が高まっています。集中力を養いながら、感情や情緒を育み、創造的で表現力豊かな子どもに成長する手助けとなるでしょう。
マイクラを活用したプログラミング学習が向いている子どもの特徴

集中力をつけ創造力を育み、論理的思考力を伸ばしていくことなど、マイクラを使ったプログラミング学習のメリットをご説明してきましたが、子どもをみて本当にマイクラが必要なのかと考えてしまう方もいるでしょう。この学習が向いているという子どもの特徴を3つ、ご紹介します。
自主性や主体性を身につけたい
マイクラのなかで自ら設定したゴールを達成するために計画をつくり、課題に取り組み問題を解決していく過程で、子どもたちは自主性や自立性を育んでいきます。「かわいい子には旅をさせよ」という格言がありますが、それがバーチャルの世界でも同様に、子どもが自らの力で課題に向き合う経験を積んでいくことで、自主性・自立性が養われて行きます。
そこでの成功体験によって、自らの人生を自力で切り開いていくことの大変さを覚えます。困難を乗り越えていく地力は、身をもってそこに立ち向かうことで育むことができ、マイクラによって成し遂げることができるのです。
子どもが自主性に乏しく、自立できるのか不安にみえたり、学校や地域社会になじめず、自分の殻の中に閉じこもりがちなタイプであれば、マイクラによるプログラミング教室は向いていると言えるでしょう。
学校の授業やテストに備えたい
プログラミング学習は、テストや受験に役立つことでも知られています。実際のところ、教育現場では2020年から小学校で必修化され、2025年には大学入学共通テストでも出題されました。
ますます過熱ぶりが報道されている中学受験、その先の高校や大学受験、資格取得を目指すうえでも役に立つ能力が、プログラミングには内在しています。頭の柔らかい子どものうちほど効果があるとされていますので、勉強が苦手という子どもにも、この教室は向いているでしょう。
マイクラを通じてプログラミングへの理解を深め、子どものうちに楽しく学ぶことを習得することで、変わりゆく教育カリキュラムにも対応し役立つことでしょう
将来の選択肢を増やしたい。
プログラミングスキルはキャリア形成で強い武器となります。ITスキルは習得しているのが当然という世の中ですが、プログラミング言語の理解があるとないとでは、キャリア選択の幅も違ってきます。
そのスキルを使っていくつもの会社を渡り歩き経験と腕を磨きながら、自分で起業し経営者になるという道も選択肢のひとつになるでしょう。
現在は多様性が重要視されるようになり、様々な働き方が受け入れられる社会となりましたが、そこでサバイバルしていくことのできる能力を望むのであれば、プログラミング教室は良い出会いより良いスタートを切れるでしょう。
マイクラを使ったプログラミング教室の料金相場

マイクラを使ったプログラミング教室の料金相場は10,000~30,000円です。カリキュラムによって多少異なりますが、習い事の相場としてみるとやや高額です。ですが、そこに通うことで得られるリターンからその価値を認めて子どもを通わせたり、将来への投資と考える人が増えています。また、教室はどのように選べばいいか悩む保護者もいるでしょう。次は、教室の選び方や子どもの対象年齢など注意事項を説明します。
子ども向けのプログラミング教室の選び方

プログラミングスクール、特にマイクラをつかった教室選びにおいて、注意しておくとよい項目を4項目を挙げ、具体的に解説します。お子さんのベストとなる教室選びに役立ててください。
対象年齢に当てはまるか確認する
プログラミングスクールを選ぶ際には、対象年齢の確認を忘れないようにしてください。子どもは1学年違うだけで、理解力も違えば学習の進み具合も変わってきます。対象年齢よりも上のクラスに入ってしまい、結果として授業についていけず、せっかくのプログラミング学習をあきらめてしまうというケースにもなりかねません。
一方で、低い年齢を対象としたクラスならいいというわけでもなく、こちらは幼すぎ、簡単すぎて興味を持てず、通うことをやめてしまう可能性も高まります。
子どものレベルや成長に合ったクラスというのが、マイクラをつかったプログラミング教室では重要になります。子どもの成長に合わせてのカリキュラムが組まれている教室を選んであげるようにしましょう。
年齢はホームページやパンフレットに明記されていることが多いので、確認をしておきましょう。
予算に合った料金で選ぶ
料金の確認もおろそかにしないようにしてください。
マイクラを使ったプログラミング教室の料金相場は10,000~30,000円ですが、月額料金のほかに入会金が必要であったり、教室で授業を受けるための教材費やパソコンのレンタル料なども加算されたりすることを考慮しておく必要があります。
初期費用というだけでなく継続的に支払わなければならないとなると、家計への負担が増えます。あくまで無理のない範囲で決めていくことがポイントです。
一方で、4,000円程度と格安をアピールしているようなスクールもあります。なかには「無料」というスクールまでありますが、安いことが必ずしも良いという訳ではありません。少しでも不安要素がある場合は直接スクールに足を運ぶなどして確認することをおすすめします。
通学・オンラインで選ぶ
同じマイクラをつかったプログラミング教室でも、学習スタイルはオンラインと対面学習の2つがあります
オンライン学習は自宅にいながら授業を受けられるので、送り迎えの必要もなく子どもが危険な目に遭うリスクもありません。子どもにとっても、自分のペースで勉強を進めることができます。
しかし、スクールで受けられるようなきめ細かいサポート、たとえばパソコンの設定などは保護者がしなければなりませんし、インターネット環境も整備しなければなりません。当然ながら、そうしたコストも考慮しておく必要があります。
かたや対面学習は同じ志を持った友だちや仲間もでき、講師陣との密接な関係を築いてより多くの学びを得ることができるでしょう。どちらが良いというのではなく、どちらが家庭環境や教育方針により適しているかという観点が、選ぶ際のポイントになります。
無料体験を利用して決める
どこのスクールにするか、ある程度絞り込んだら、実際に見学に訪れてみるといいでしょう。受付の雰囲気や講師陣の人柄、そしてそこに通っている子どもたちの様子をみてみると、合うか合わないかが見えてくることが多いです。
また実際に通って勉強するのは子どもですから、子どもの気持ちを尊重して決定してあげるようにすると良い結果に恵まれます。学校選びもお見合いと同様、相性というものがあります。スクールには無料体験の機会が設けられていますから、利用するのが得策です。無料体験時には説明を受ける時間も設けられているので、スクールのシステムや追加で必要になる費用など、きちんと理解するまで質問し確認しておくことが必要です。
子どものプログラミング教室なら『プログラミング教育 HALLO』

最後に、プログラミング教育 HALLOについて説明させていただきます。
「年長・小学生・中学生のための本格プログラミング教育」と掲げ、「自分で学び、自分で理解していく力」を育みIT社会とグローバル社会に活躍できる人材の育成を目指しています。
採用している教材「Playgram」は、ゲームで遊んでいるような感覚で冒険を進め、気付いたら実用レベルのコーディングまで身につけることができるものです。他のプログラミング教室で扱う教材よりも、とにかく子どもが夢中になる仕掛けがたくさん組み込まれています。学習管理システムを用い、一人ひとりの学習時間や頻度、各ステージの理解度や進度などを把握し、やる気スイッチグループの個別指導メソッドをかけ合わせて、一人ひとりに個別最適化されたレッスンを行っています。期間も時間も幅広く設定し、子どもが楽しく続けられる学習サイクルを提案しています。対象者やコース、利用の流れなど、サービス内容はHPにありますが、ご質問があればお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが対応させていただきます。
プログラミング教室利用者の体験談

体験授業も随時、募集し、その模様も公開しています。実際にカリキュラムを体験していただき、活気ある教室をみていただくのが最初の出会いであると考え、講師陣ならびにスタッフ一同、心よりお越しをお待ちしています。
体験談①
Mちゃん 小学3年生のお母さまはこんな感想を語ってくださいました。
「アプリ内の課題をクリアすることで、ロボットなどを動かすような体験内容でした。
レベル1の簡単な問題から始まり、レベルがあがるごとに内容がだんだん難しくなるようです。難しくなるといってもスモールステップで少しずつ段階を踏んでいくみたいなので、取り組みやすくなっているように感じました。ゲーム感覚でクリアしていくことができて楽しそうな様子でしたよ。解いていく中で娘がつまずくときがあったのですが、先生は正解を教えるのではなく、答えを導くためのヒントをくれるんです。そのヒントをもとに、子ども自身が考えて正解を見つけていました。考えて解くことによって『自分でできた!』という達成感を得られそうだなと思いましたし、課題解決力が養われそうだという印象を受けました」
体験談②
続いて、Aちゃん 小学4年生のお母さまです。
「問題がだんだん難しくなっていき次々にステージが現れるので、娘は『もっとやりたい!』という気持ちになったようです。時間内に何問クリアできるか?とレベルをはかったことで、もっとできるようになりたいと思ったみたいです。体験後も『つづきをやりたい!』と話していました。
実は、プログラムが組めるようにならなくてもいいかなと思っているんです。ただ、子どもが将来「やりたい。必要だ」と思ったときにスッと取り組めるように、触れる機会だけは小学生のうちから持っていてほしいなって。『自分にもつくれるものなんだな』という実感をつかんでくれたらなと思っていたんです。仕組み・考え方にフォーカスして学べるHALLOのような教室は、まさに私が望んでいたかたちでした」
体験談③
続いてNちゃん 小学3年生のお母さまです。
「答えは何通りもあるという考え方は、正解の無い時代に『自分なりの答え』を見つけていくうえでとても大切だと思います。プログラミングのレッスンを進めていくことで、こういった思考が深まっていくことも期待できるのかな、と思いました。ちなみに、レッスン後には『もっとやりたい〜』って言われてしまって。逆にハマっちゃって大変かも?!なんて思ったりもしました(笑)」
プログラミング教室に関するよくある質問
子どもにプログラミング教育は必要?
はい、もちろんです。ロールプレイング式で段階的にプログラミングの基礎を学んでいくので、初心者でも安心して学べるカリキュラムになっています。また、iPadでレッスンを行うので、パソコンに苦手意識がある子どもでも取り組みやすいです。わからないところがあっても、スタッフが丁寧にサポートしますので、安心してご受講ください。
子どもがプログラミングを習得するには?
小さな成功体験の積み重ねと学習サイクルです。何より続けることが大切です。プログラミング教育 HALLOなら楽しく続けられる学習サイクルと子ども一人ひとりをしっかり指導することで、子どものスキルがどんどん上達し、可能性を引き出すメソッドがあります。
子どもがプログラミングを学習するメリットは?
「自分で学び、自分で理解していく力」を身につけることです。IT社会とグローバル社会で大いに活躍できる人材となることでしょう。とにかく夢中になる仕掛けをたくさん用意していますので、遊んでいるような感覚で冒険を進め、気づいたら実用レベルのコーディングまで身につけることができます。
まとめ
プログラミング教育 HALLOは、人工知能(AI)技術の研究開発で日本を代表する最強のエンジニア集団Preferred Networksと、40年にわたり80万人の子ども達のやる気スイッチを入れてきた、やる気スイッチグループが手掛ける”超本格派”プログラミング教育です。