小学校でのプログラミング必修化について具体的な内容も含めて徹底解説!
更新日:2025.10.7
公開日:2022.9.5

2020年から小学校におけるプログラミング教育が必修となりました。ただ、必修化されたといってもどのような教育なのかよくわからない人も多いようです。そこで、本記事ではプログラミング教育の必修化について概要や目的に触れながら、プログラミング教育でおこなわれている具体的な授業のポイントや課題などを事例も挙げながら紹介します。
この記事の目次
1.小学校でプログラミングが必修化になった背景と目的
そもそも小学校でプログラミング学習を必修化することになったのはなぜなのか、疑問を持っている人もいるかもしれません。そこで、こちらでは小学校におけるプログラミング学習必修化の背景や目的について解説します。
1-1.プログラミングが必修化になった時期
小学校でのプログラミング教育は、2020年度から必修となりました。これは、文部科学省が定める教育課程の基準である「学習指導要領」が約10年ごとに改訂される際に、プログラミングが新たに加えられたためです。
学習指導要領は、全国どの学校に転校しても、子どもたちが同じレベルの教育を受けられるようにするための大切な指針です。また、この改訂には、社会の変化に柔軟に対応できる力を育てるという目的もあります。
近年はAI技術が急速に進歩し、社会全体のIT化も進んでいます。こうした背景から、これからの時代を生きる子どもたちには「プログラミング的思考」が欠かせない力として重視されるようになりました。そのため、この力を育てることを目指して、全国の小学校でプログラミング教育が一斉に導入されたのです。
1-2.必修化の背景
私たちの生活は、今やITと切り離せないものとなっています。スマートフォンや家電製品、自動車など、身の回りの多くのものにITが使われています。普段はその仕組みを詳しく知らなくても使うことができますが、社会全体がますますデジタル化していくこれからの時代には、ただ使うだけでなく、仕組みを理解し、自分で活用する力が必要とされます。
企業でも、人がおこなってきた仕事の一部がAIやロボットに置き換わる未来が考えられています。このような社会では、与えられた技術を受け入れるだけでなく、自分で問題を見つけて解決方法を考え、技術を上手に使いこなす力がとても大切です。
こうした背景から、子どもたちに論理的な考え方を身につけてもらうためのプログラミング教育が注目されています。未来を生きる子どもたちが必要な力をしっかり身につけられるように、小学校でもプログラミング教育が学習指導要領に加えられ、必修化が進んでいます。
1-3.必修化の目的
プログラミング学習というと、将来プログラマーになるための教育だと考えられがちです。しかし、小学校でおこなわれているプログラミング学習の目的は、専門的な技術を身につけることではありません。主なねらいは、物事を論理的に整理し、問題を解決する「プログラミング的思考」を育てることにあります。この力は短期間で身につくものではないため、子どもが柔軟に新しいことを吸収できる小学生のうちから学ぶことが大切です。
授業では、パソコンを使った操作だけでなく、タイピングなどの基本的なスキルも身につけます。また、低学年ではコンピューターを使わずに、カードやブロックを使ってプログラミングの考え方を体験する授業もおこなわれています。こうした活動を通して、子どもたちは受け身で技術を使うのではなく、自分から積極的に学び、社会で活かそうとする姿勢を身につけていきます。
これまで、子どもがパソコンやタブレットに触れるのは主に遊びの場面が多く、学習の機会は限られていました。しかし、今後ますますIT社会が進んでいくことを考えると、小学生のうちからプログラミングを学ぶことはとても重要だといえるでしょう。
2.教科には含まない?小学校でおこなうプログラミング学習のポイント

こちらでは小学校でおこなわれるプログラミング学習の3つのポイントについてまとめました。
2-1.パソコンは必ずしも使わない
小学校のプログラミング学習は必ずしもパソコンを使用するとは限りません。たとえば、カードやブロックなどの道具を使用してコンピューターの基礎学習をおこなうケースです。パソコンやタブレットを使わないプログラミング学習は「アンプラグド・プログラミング」と呼ばれています。タイピングがまだ十分身に付いていない小学校低学年であってもプログラミングのイメージがつかみやすかったり、学習をスタートさせるきっかけにできたりという点がよいところです。小学校でのプログラミング学習はあくまでも基礎を学ぶものであって、難しいプログラミング言語を学ぶ期間ではありません。そのため、子どもが楽しみながら論理的思考を身に付けていくことが重要視されます。
小学校の頃には読書をする機会も少なくありませんが、視覚的に学ぶ方法として絵本が用いられるケースもあります。絵本はイラストがあるので飽きにくく、子どもが想像力を働かせながら学べる良い教材のひとつといえるでしょう。実際に授業に取り入れられているものとして、海外のプログラマーで作家・イラストレーターの作者が手掛けたものがあります。こちらは宝石集めをしながら、物語のなかから練習問題が出てくるといったものです。ほかにも、カードを使ってダンスの流れを考えるといった方法もあり、体を動かしながら論理的思考を育てることが可能です。
2-2.扱う言語やソフトは自由

小学校でおこなわれているプログラミング学習では、特定のプログラミング言語やソフトウェアを全国一律で使うと決められているわけではありません。各学校は、文部科学省のホームページに掲載されている研修用教材を参考にしつつ、子どもの年齢や学習環境に合わせて教材を選んでいます。教材には動画やテキストなどさまざまな形式があり、遊び感覚で学べる内容が多いことも特徴です。
例えば、プログラムを使って図形を描いたり、キャラクターを動かして簡単なゲームを作ったりする授業がおこなわれています。身近なテーマを取り上げることで、子どもたちは楽しみながら論理的に考える力を身につけていきます。学習に使う機材は主にタブレットですが、学校によってはプログラミング専用のキットを使うこともあります。パーツを組み立ててロボットを作り動かす教材や、センサーを使って仕組みを体験できる教材などがその一例です。
このように、子どもたちは自分の手を動かして試行錯誤しながら、考えたことを形にする過程を通してプログラミングを学んでいます。
2-3.各授業の一環としておこなわれる
| 各教科でおこなわれているプログラミング学習の例 | |
| 算数 | Scratchなどのビジュアル言語を使って、正多角形を描く。 |
| 社会 | 都道府県や地域の情報を、プログラミングを活用して学ぶ。 |
| 理科 | プログラミングを通じて、電気を使った身近な道具の性質を理解する。 |
| 音楽 | ソフトを利用し、特定のリズムやパターンで音楽を作成する。 |
プログラミング学習は単体の教科ができるわけではなく、各授業のなかでおこなわれます。特にプログラミングは算数や理科との相性が良く、授業に取り入れやすいです。また、教科においてプログラミングに関する成績は評価対象にはなっておらず、あくまでもその教科で学ぶ内容についての理解度や知識などが評価されます。
小学校で大切にされているのは、プログラミングに親しみを持ち、自分から学ぼうとする気持ちを育てることです。無理にやらされるのではなく、楽しみながら学ぶ経験を積むことが、将来の学びにつながります。あせらずに体験を重ね、自然と興味を広げていくことが、小学生にとってのプログラミング教育の大きな意味だといえます。
3. 小学校の実際のプログラミング学習事例【学年別】

小学校のプログラミング学習は学年が上がるごとにステップアップします。こちらでは、小学4~6年生の間で学ぶことの一例について紹介します。
3-1.小学4年生
「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」では、株式会社ポケモン協力のもと技術進化と自分たちの生活の関わり方を学んだ例があります。具体的には、ゲーム制作者へのインタビューを通じて技術を使った仕事や働く意義を考えること、意図した内容でプログラミングを作成する方法を学ぶために、ポケモンキャラクターを使用したプログラミング教材を用いて、実際にキャラクターを動かしてみるという体験がおこなわれました。
3-2.小学5年生
小学5年生では算数で正多角形の作成をおこなった事例があります。実際に、このプログラミング学習を受けた生徒からは「結果が視覚化されているので楽しい」「失敗を繰り返しても落ち込まずにトライできる」という声が寄せられました。また、プログラミング教材を使用して、英語による道案内のプログラミングの授業もおこなわれています。こちらの事例では「英会話能力の向上につながった」「プログラミングの簡略化をおこなうなかで、プログラムにはさまざまな形があることを学んだ」という意見などがありました。
3-3.小学6年生
6年生のプログラミング学習はプログラミングの実践編といっても良いでしょう。理科の授業では電気の性質や働きを理解したうえでプログラムを作成し、安全で効率的な信号機の仕組みを知るという授業がおこなわれました。さらに、家庭科では教材のセンサーや制御機能などを有効活用して、生活に役立つ道具を作成した事例もあります。こういったプログラムの作成を通して、センサーが節電に有効であることを知ったという感想が寄せられました。
4. 小学生がプログラミング学習をおこなうメリット
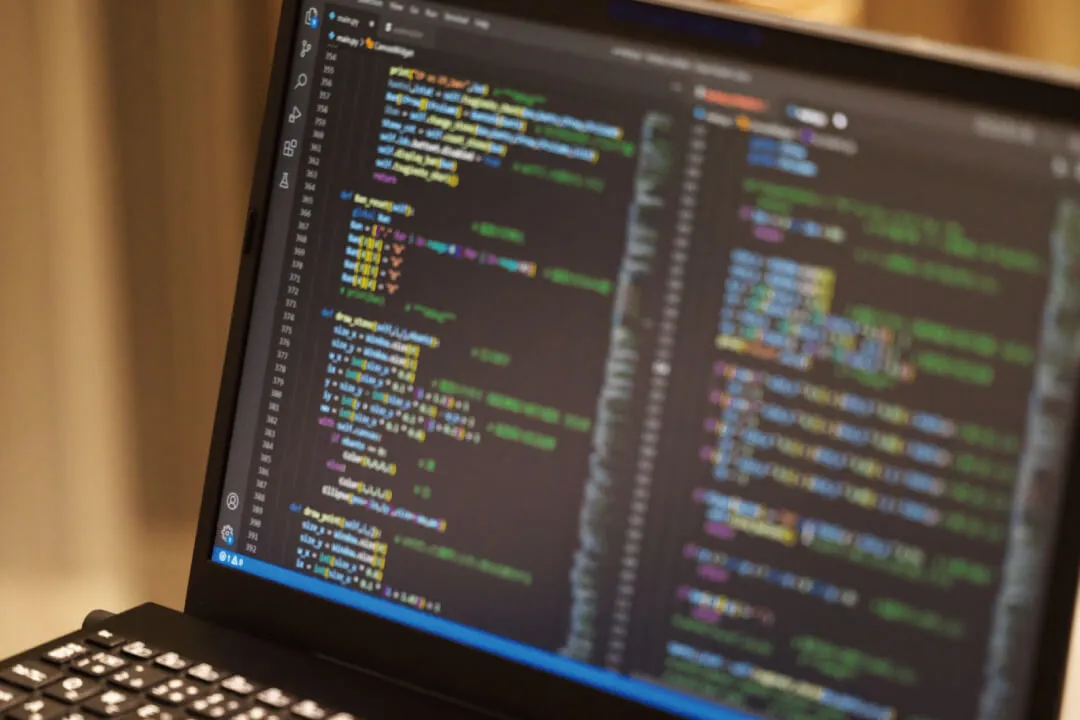
小学校でのプログラミング学習はさまざまな面で利点がありますが、課題を抱えているのも現状です。そこで、こちらでは小学校におけるプログラミング学習の利点、今後改善していくべき課題について見てみましょう。
4-1.プログラミング的思考が身に付く
プログラミング学習は、単なる技術習得にとどまらず、これからの社会で必要とされる多様な力を育てます。ゴールに向けて手順を組み立てるなかで論理的思考力が養われ、エラーに向き合い解決策を見つける経験は問題解決能力につながります。効率のよい方法を模索する過程では批判的思考力が磨かれ、情報を集めて活用する力や、自由な発想を形にする想像力も伸びていきます。そして何より、子どもが「やってみたい」という気持ちから自ら学びに向かうことで、自主性が自然に育まれていきます。
関連リンク:https://www.hallo.jp/column/post-329/
4-2.大学入試対策にも役立つ
2025年から大学入学共通テストに「情報」が加わり、プログラミングに関する問題も出題されることになりました。小学校で学ぶ内容は基礎的ですが、この時期からプログラミングに慣れ親しんでおけば、中学・高校での本格的な学習へスムーズに移行できるでしょう。さらに、学習を通じて養われる論理的思考力や情報整理能力は、他の教科の理解を深めるうえでも大いに役立ちます。つまり、小学生のうちに基礎を固めておくことは、将来の大学入試において「情報」だけでなく、さまざまな分野で大きな強みとなるのです。
4-3.将来の選択肢が広がる 60%
現在、社会全体でIT人材の不足が課題となっており、プログラミングの知識やスキルは将来に向けて大きな可能性を広げる要素とされています。プログラミングを通じて育まれる論理的思考や課題を解決する力は、理系分野に限らず幅広い職業で必要とされる力です。さらに、自分の発想を形にする体験は、子どもが将来の興味や目標を見つけるきっかけにもなります。小学生の段階からプログラミングに親しむことで、学びの世界が広がり、将来選べる道もより多様になっていきます。
5. 小学生のプログラミング学習の課題

小学校でのプログラミング学習は子どもの将来において大きな意味がありますが、教える立場である教師すべてがプログラミングに関する知識を持っているわけではない点が問題になっています。そのため、教師側の負担・混乱の軽減を考慮して情報を提供したり、研修をおこなったりすることが大切です。具体的には「プログラミング的思考の本質を考慮したうえでプログラミングの経験を増やす」「ICT機器やアプリの使い方の指導」といったことが挙げられます。文部科学省、総務省、経済産業省のほか、全国の教育委員会・学校、民間企業・団体によって立ち上げられた「未来の学びコンソーシアム」では、小学校のプログラミング学習向け教材や実際の授業事例などを掲載しているので参考にしましょう。
さらに、パソコンやタブレットなどの機器の不足、不十分なネットワークなど学習環境が整っていないケースもあります。学校側の問題以外にも、保護者側が感情面で不安を感じている問題もあります。中学校・高校に進学すればプログラミングの授業が本格的にはじまりますが、その基礎を学ぶべき小学校でプログラミング学習が十分おこなわれていないという不安です。学校、保護者、生徒など全員がプログラミング学習を受け入れられる体制を整えることは優先するべき課題といえます。
6.【小学生向け】家庭でのプログラミング学習方法

小学生が家庭でプログラミングを学ぶ方法には、いくつかの選択肢があります。例えば、教材や書籍を使って基礎を身につける方法や、アプリやおもちゃを使って楽しく学ぶ方法があります。また、オンライン講座や学習サイトを利用することも可能です。さらに、もっと本格的に学びたい場合は、プログラミング教室に通うという方法も選べます。
6-1.テキスト教材・書籍を使って学ぶ
プログラミング学習の入口として、テキスト教材や書籍はとても役立ちます。紙の教材は順を追って学べるため、初めての子どもでも落ち着いて理解しやすいのが特徴です。小学生向けのテキスト教材の多くは、イラストや図解が豊富で、遊び感覚で読み進められます。文字を追いながら考える習慣が自然に身につき、保護者が一緒に読み聞かせのように進めることも可能です。紙の本を使った学習は、デジタルに慣れていない家庭でも安心して取り組める第一歩になります。
関連リンク:https://www.hallo.jp/column/post-471/
6-2.プログラミングアプリを活用する
タブレットやパソコンで使えるアプリは、遊び感覚で学べる手軽な方法です。たとえば、「Scratch」や「Viscuit」といったビジュアルプログラミングのアプリがあります。これらは、カラフルなブロックを組み合わせるだけでキャラクターを動かせるので、文字入力が苦手な小学生でも直感的に操作できます。そのため、論理的な考え方を身につけるきっかけにもなります。また、「codeSpark Academy」や「Springin’」のように、ゲームのような課題をクリアしていくタイプのアプリもあります。こうしたアプリは、達成感を味わいながら続けられるのが大きな魅力です。遊びの延長として取り組めるため、保護者も子どもに学習を勧めやすく、自然と学ぶ習慣が身につきやすい方法といえるでしょう。
6-3.プログラミング玩具で遊びながら学ぶ
ロボットやブロックを使ったプログラミング玩具は、体を動かしながら学べるため、特に低学年の子どもたちに人気があります。たとえば、「レゴ® エデュケーション SPIKE」や「Ozobot(オゾボット)」では、ブロックを組み立てたり、色を組み合わせたりして動きをコントロールできます。このように、プログラムの結果が目に見える形でわかるので、子どもたちは試行錯誤を重ねながら自然と考える力を身につけていきます。さらに、「カードでピッ!とプログラミング」などのカード型玩具は、パソコンがなくても遊べるため、初めてプログラミングに触れる子どもにもぴったりです。保護者が一緒に遊ぶことで会話が生まれ、学びの時間が楽しい思い出にもなります。
6-4.オンライン講座や動画、学習サイトを使う
ご家庭のインターネット環境を使えば、プログラミングの学習はいつでも始めることができます。「Progate」や「ドットインストール」などの学習サイトは、初心者にもわかりやすい工夫がされているので安心です。さらに、「NHK for School」のような公共の教育サービスや、YouTubeの解説動画など、無料で利用できるサイトも積極的に活用しましょう。家庭で学ぶ最大の良さは、子どもが自分のペースで、何度でも繰り返し学習できることです。また、保護者も学習の様子をそばで見守りやすく、必要なときにアドバイスできる点も大きなメリットです。
6-5.プログラミング教室に通う
本格的にプログラミングを学ばせたいと考えているご家庭には、プログラミング教室に通わせる方法も効果的です。多くの教室では、プログラミングに詳しい講師が直接指導してくれるため、子どもが疑問を感じたときにすぐに質問でき、理解を深めやすい点が特長です。さらに、同じ年代の子どもたちと一緒に課題に取り組むことで、お互いに刺激を受けながら協力する力も身につきます。カリキュラムも体系的に作られているため、学習のステップアップが分かりやすく、成果が目に見えて実感しやすいのも安心できるポイントです。また、保護者にも定期的に学習の報告があるため、子どもの成長の様子を把握しやすい点も魅力です。
7.小学生のプログラミング学習なら、プログラミング教育 HALLO

提供先:プログラミング教育 HALLO
プログラミング教育 HALLOは、子どもたちが「実用的なプログラミングスキルを身につける」ことを大切にしているプログラミング教室です。対象は年長から中学生までで、学習教材「Playgram(プレイグラム)」を使い、ゲーム感覚で学びながら、ビジュアルプログラミングからテキストコーディング(Python)まで無理なくステップアップできます。教室の特長の一つが少人数制による個別最適レッスンです。1クラス少人数で授業をおこなうため、一人ひとりの理解度や進み具合に合わせたサポートが受けられます。また、自宅学習と組み合わせることで、小さな成功体験を積み重ねることができます。さらに、週1回の教室レッスンに加えて、学習管理システムを使い、子どもの理解度を「見える化」しています。月に1回の作品発表の機会もあり、達成感を味わいながら、プレゼンテーション能力も自然と身についていきます。
8.まとめ
2020年度から小学校で必修となったプログラミング教育は、専門的な技術を身につけることが目的ではありません。主なねらいは、将来に役立つ「論理的思考力」を育てることにあります。また、「プログラミング」という新しい教科ができたわけではなく、算数や理科など、普段の授業のなかで、パソコンを使わない活動も取り入れながら進められます。このような経験は、2025年から始まった大学入学共通テスト「情報Ⅰ」への対策になるだけでなく、子どもたちの将来の選択肢を広げることにもつながります。そのため、家庭学習やプログラミング教室など、子どもに合った学び方を見つけることが大切です。




