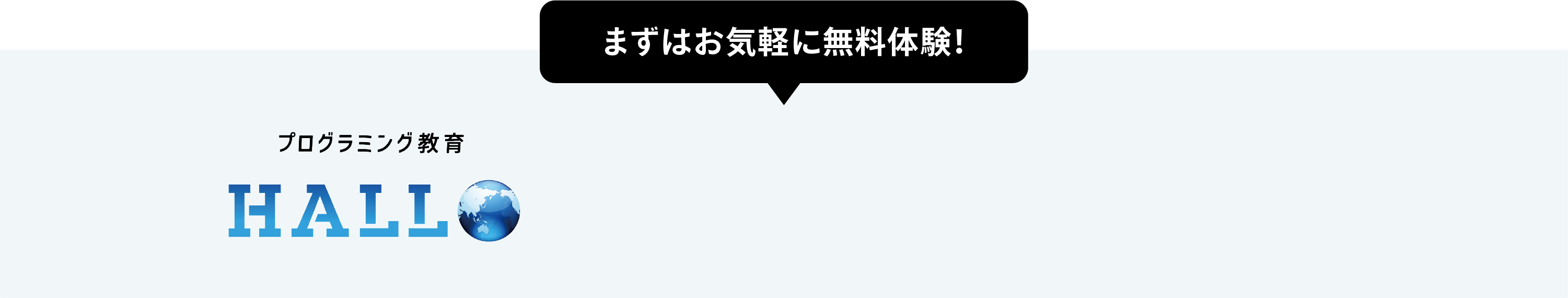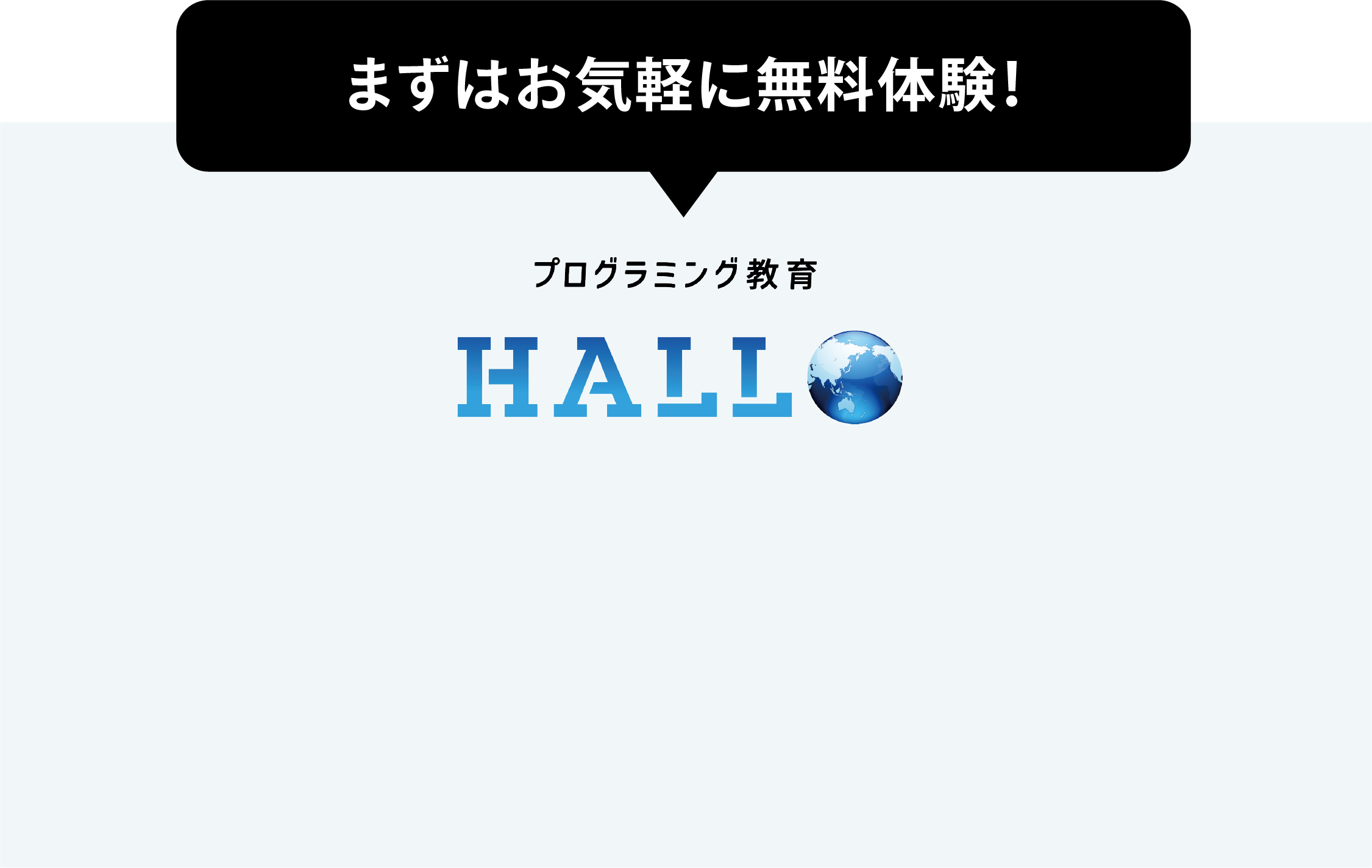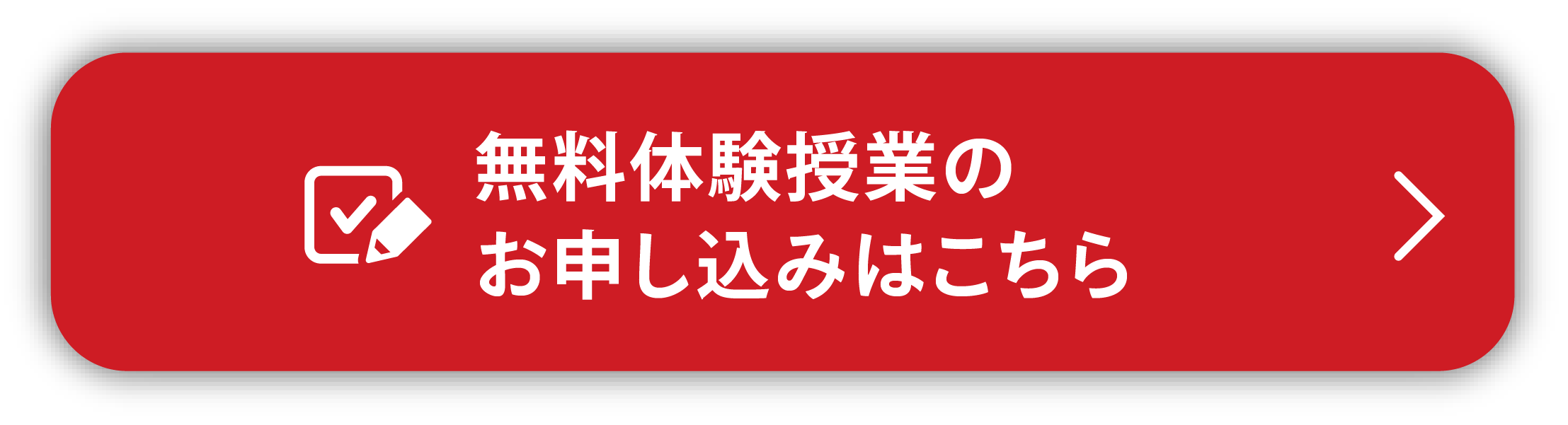ロボット教室のデメリットとは?メリットや通わせる際の注意点などを詳しく解説
更新日:2025.4.28
公開日:2022.11.11

私たちの生活には、今やロボットはなくてはならないものとなっています。マンガやアニメの影響もあり、ロボットに興味を示す子どもたちも多くいます。そんな現代社会で子どもの将来のためになると注目されているのが、ロボット教室です。この記事では、ロボット教室の基本情報やロボット教室に向いている子どもの特徴や、通わせる際の注意点も合わせて解説します。
この記事の目次
1.ロボット教室とは?

ロボット教室とは、ロボット作りやロボットを思い通りに動かすために、どのようにすればよいかを学べる教室です。「STEM(ステム)教育」あるいは「STEAM(スティーム)教育」に沿った学びができると注目を集めています。
「STEM」は科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・数学(Mathematics)の頭文字をとったもので、「STEAM」は、それに芸術(Art)分野を加えたものです。つまり、「STEM(STEAM)教育」とは、理科、算数・数学、図工、技術、美術など、それぞれの科目で学んだことを通して、生活や社会の課題発見や問題解決に生かす教育手法です。グローバル化が進み、文系・理系といった枠にとらわれず課題を解決する力が求められている現代、文部科学省はこのような科目横断的な学習を推進していて、その一環として2020年には小学校でプログラミング教育が必修化されました。
ロボット教室では、ロボット製作を通して創造力や集中力を鍛え、論理的思考力や空間認識力を養うことができます。まさに「STEM(STEAM)教育」に沿った学びができます。そして、ロボット教室で得られた学びは、子どもが将来社会で求められるスキルを身につけられると考えられています。
2.ロボット教室の基本情報

ロボット教室は、子どもたちがロボットを作ってプログラミングを学べる場所です。ロボット教室は人気で、教室によってどのようなロボットを作るか、どれくらいの時間勉強するかなどは、異なります。具体的な授業内容や料金などは、実際に子どもを通わせたいロボット教室へ問い合わせてみましょう。
2-1.学習内容
ロボット教室では、市販または教室オリジナルのロボット教材を使用し、センサーやモーターを搭載したロボットを製作していきます。基本的にテキスト通りに組み立てていきますが、パーツを追加して応用的なロボット製作を行う場合もあります。なかには、ロボットプログラミングを学習して、ロボットを思い通りに動作させるカリキュラムを用意している教室もあり、授業内容はロボット教室によってさまざまです。子どもたちはロボット製作を通して失敗体験や成功体験を繰り返しながら、ロボットの動きや仕組みといったものを学んでいきます。
2-2.対象年齢
ロボット教室の対象年齢は、基本的に小学生以上です。しかし、なかには幼稚園・保育園の年長(5歳児)あたりから入会を受け付けているロボット教室もあります。低年齢でロボット教室に通い始めたとしても、指導者がサポートをするため、製作で挫折する心配はあまりないでしょう。さらに、中学生向けの上級教室を開設しているところなら、長く通わせてロボット製作に関するスキルを磨いていくことも可能です。
2-3.授業時間
ロボット教室の授業時間は、基本的に1回90分です。製作に時間がかかるため、学校の授業時間よりも長くなっています。もともとロボットが好きで、集中力のある子どもなら、時間を忘れてロボット製作に夢中になれるので、90分は物足りなく感じるでしょう。しかし、集中力がない子どもにとっては退屈で疲れてしまうかもしれません。低学年の子どもや初級者を対象としたクラスでは、50分コースを開設している教室もあります。子どもの集中力やロボットに対する興味を考えて、教室選びをすることが大切です。
2-4.授業回数
ロボット教室は、カリキュラムを年単位で組み、月2回の授業回数にしているところが多いです。1カ月に2回の授業を1年間継続し、合計24回の講座を受けるといった形式になります。月謝は教室ごとに異なるため一概には言えませんが、ほかの習い事に比べて授業1回あたりの料金は高くなる傾向があります。
3.ロボット教室のデメリットや、やめてしまう理由は?
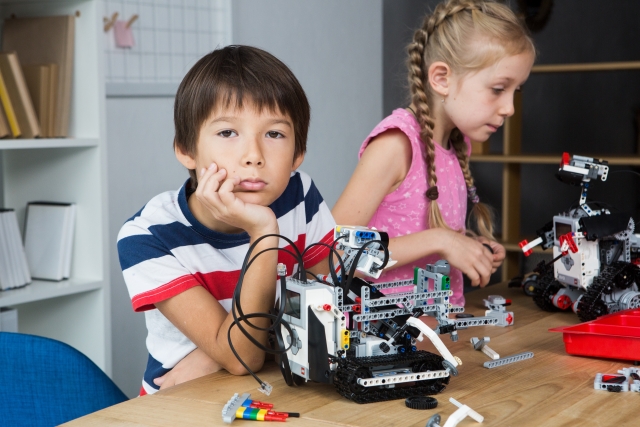
ロボット教室は子どもにとって興味を引くカリキュラムが組まれ、楽しい体験を通してプログラミングを学んでいくことができます。しかし中には、長続きせずにやめてしまったという子どももいます。では、どのようなことがやめるきっかけになってしまったのかを見てみましょう。子どもに合ったロボット教室選びの参考にしてください。
3-1.講師との相性がよくなかった
多くの子どもを担当する先生の中には、やはり子どもとの相性に差がある場合もあります。自分の子どもとはうまく合わないと感じることや、他の子どもへの対応と自分の子どもへの対応に違いを感じることがあるかもしれません。人と人との相性は、子どもだけでなく大人にも存在します。そのため、教室の評判だけで決めるのではなく、まずは体験レッスンを受けてみることが大切です。レッスン後に子ども自身の感想を聞き、実際に合っているかどうかをじっくり見極めてください。
3-2.教室の雰囲気が合わなかった
コミュニケーション力が付くと期待していたのに、授業中のほとんどは一人で黙々とロボットを組み立てるだけだったということもあるようです。ほかにも、周りが騒がしくて集中できなかったという意見やただ遊んでいるようにしか見えなかったなど、教室で授業を行う様子を見て、期待通りではなかったことで、やめてしまったというケースもあります。教室の雰囲気を知る為に、入会前に授業見学や体験レッスンを受けるようにしましょう。
3-3.成長が目に見えて分からない
ロボットプログラミングは、点数がつけられる教科と違い、子どもの成長の伸びが分かりにくいと感じている人も少なくないようです。中には、「ただ遊んでいるようにしか見えない」、「ほかの勉強も自主的にするようになると聞いていたが、そうはならなかった」など、子どもの成長が目に見えて分からないことも、やめる理由の一つになっているようです。プログラミングというのは、すぐに身につくものではなく、長い時間をかけて習得していくものなので、急激に成績を上げることを望んでいる場合は不向きかもしれません。
3-4.金銭的負担で続けられなくなった
ロボット教室は、ほかの習い事に比べて費用が高くなることがあります。毎月の授業料だけでなく、教材費も同様です。中には、コースがステップアップする時に、新しいロボットを購入しなければいけない、それに伴って授業料が高くなるので、続けられなくなったという口コミもあります。ロボット教室は、教材が特殊なため、教材費が高くなりやすいです。そのため、毎月の授業料だけでなく、ステップアップした時にかかる追加の教材費も、事前に確認して継続して通えるのか、しっかり考える必要があります。
3-5.自宅から遠く通うのが大変になった
ロボット教室の人気が出てきたとはいえ、まだまだ教室の数が多いとはいえません。そのため、教室に通いたくても、教室が近所にないため毎回送迎をしていると、それだけで保護者の負担が大きくなってしまいます。実際に送迎が難しくやめてしまったという保護者もいるので、送迎の必要性や時間を考慮して教室選びをする必要があります。また、親の送迎ができなくなったときのことを考えて、子ども一人でも教室に行ける方法を考えておくといいでしょう。
3-6.単純に飽きてしまった
ロボット教室に通い始めた頃は、ロボットを作ることが楽しくて意欲的に取り組んでいても、時間がたつにつれて、興味が薄れてしまい、実際に、ロボット作りに飽きてしまった子どももいます。また、ステップアップして難易度が上がったことで挫折してしまい、ロボット作りに興味が持てなくなったということもあります。その場合、教室が子どもに合っていない可能性もあるので、ほかのロボット教室を探してみましょう。講師や周りの友達など環境が変われば、新しい刺激になり、また興味を持って楽しく取り組むことができるようになるかもしれません。
3-7.ほかの習い事と両立ができなくなった
保護者としては、子どもが興味を持ったことは可能な限り体験させてあげたいと思うものですが、ほかの習い事をすると、時間だけでなく、金銭面での負担も大きくなってしまいます。中でも特に多いのが、受験のために学習塾に通い始めることです。小学校・中学校・高校など受験を控えた子どもは、学習塾に通う時間が増え、特別講習も受けるようになると、費用も高くなってきます。そのため、ほかの習い事に掛ける時間と費用の負担が大きくなりやめてしまうこともあります。休塾という制度を設けているロボット教室もあるので、ほかの習い事を始めた時は、規約を読み返したり、教室に聞くなど、休塾という選択肢も考えてみましょう。
4.通わせるべき?ロボット教室のメリットは?

ロボット教室に通わせるのは無駄、途中でやめてしまった。等のマイナスな意見を見ていると、子どもは興味があっても通わせないほうがいいのでは、と悩む保護者もいると思います。しかし、ロボット教室には、子どもにとってたくさんのメリットがあるのも事実です。保護者がどのようなメリットを感じているのか、実際の口コミを見てみましょう。
4-1.子どもが夢中になっている姿が見られる
教室では、子どもはロボット作りに夢中になっています。実際に、飽き性の子どもが意外に夢中になって取り組んでいる姿を見て、成長を感じた。という保護者の声もあります。ロボットは一つひとつのパーツを正しく組み立てなければ動かすことはできません。そのため、子どもたちは目の前のロボット作りに集中して取り組む事ができます。もし、集中力が途切れてしまっても、講師がサポートしてくれるので、安心して見守ることができます。
4-2.自分で考え、頑張る力が身に付いた
組み立て方が分からなくても、講師はすぐに答えを出さず、どのようにすればいいのか、子どもと一緒に考えて、解決へ導きます。そのため、子どもは自分で考える力がつき、努力して完成する成功体験を生むことで、子どもの自信に繋がっていきます。実際に、「子どもが自分でロボットを作ることができると知って自信が付いた」と子どもの成長を感じている保護者の方もいます。自分で考える事、完成に向かって頑張ることは、大人になっても必要な力になるので、子どものころから成功体験をたくさんさせることは、成長に大きなプラスとなるでしょう。\
4-3.論理的思考力や想像力が身に付いた
ロボット作りを通して、論理的思考力や想像力を身につけていきます。保護者の口コミでも、「前に進むには、4つのタイヤそれぞれを前回りに動かすコードが必要と理論立てて考える力がついた」というものもあります。ロボット作りやそれを動かすプログラミングは、一つひとつを順番に組み立てていくことで、初めて思うように動かすことができるようになります。それまでには失敗を繰り返し、その失敗の原因を考えて修正していく工程で、論理的思考力や想像力が育まれていきます。
4-4.協調性を学んで明るくなった
ロボット教室では、一人でロボットを組み立てることもありますが、周りの友達と協力して一つのロボットを作ることもあります。この時、どこをどのようにして組み立てるといいのかなど一緒に考えながら、コミュニケーションを取ります。そのため、内向的だった子どもが協調性が身につきよく喋るようになった、友達が増えた、と感じる保護者も多くいます。協調性が育まれることは、学校生活はもちろん、社会に出た時にも、役立つ力となります。
5.ロボット教室に向いている子どもの特徴

ロボット教室は子どもの興味を強く引くため、子どもから「やりたい!」と言われて悩んでいる親御さんもいるかもしれません。ただ、長く続けられるか、効果が出るかといったことについては、ほかの習い事以上に子どもの適性が大きく関わります。この段落では、ロボット教室に向いている子どもの特徴を解説します。
5-1.レゴや積み木のような組み立てる玩具が好き
ロボット教室に向いているのは、ブロックや積み木などの組み立てる玩具が好きな子どもです。小学校で図工や工作が得意な子どもも向いています。小さな頃からブロック遊びや工作が好きで、一人で黙々と何かを作ろうとする子どもは、ロボット教室で生き生きと学べるでしょう。たとえば、部品の細かい違いに気づくことができる、ブロックの色合いや長さ・大きさのバランスを考えることができる、手先が器用などの特徴がある子どもはロボット教室に向いています。
親から見てロボット作りに向いている性格や才能を何かひとつ持っていることは、向いているかどうかを判断する目安になります。なかには、組み立てや工作が苦手な子どものスキルを伸ばしたいという目的で、子どもではなく親がロボット教室に通わせたいという場合もあるかもしれません。しかし、ロボット教室は1回の授業時間が長いため、途中で嫌になって通わなくなるおそれもあります。組み立て遊びや工作が苦手な子どもの場合は、親子でよく話し合って決めましょう。
5-2.乗り物や機械に興味がある
普段から車などの乗り物や機械など、人間が作った「動くモノ」に強い興味を持つ子どもは、ロボット教室を楽しめるでしょう。実際にロボットを製作し、動かしてみることで、日常的に目にしている、機械の仕組みなどの基礎を理解できるので、子どもにとって満足度が高いのです。それに、実生活の中で乗り物や機械を子どもが好きなように動かせる機会はほとんどありません。ロボットを思い通りに動かすことで、子どもが日々感じている「自分も機械を動かしてみたい」という願望をかなえることができるのです。
5-3.自分で新しい遊び方を作り出せる
玩具やゲームで遊ぶときに、決まった遊び方にとらわれず、自由な発想で楽しめる子どもはロボット教室に向いていると言えます。「決まった遊び方にとらわれない」ということは、単にルールを破るという意味ではありません。たとえば「これをやったらどうなるのだろう」「こうしてみたらおもしろそうだ」といった好奇心や発想力のある子どもを指します。ロボット教室の多くは、テキスト通りの製作を行ったあとに、応用や発展を考えさせる指導方法を取り入れています。そのため、これまでになかったことを作りだそう、試してみようという気持ちの強い子どもは、好奇心や発想力をさらに磨いていけるのです。
6.ロボット教室に通わせる時の注意点

自分の子どもがロボット教室に向いていると思っても「本当に大丈夫かな」と不安を持つ親御さんもいるかもしれません。たしかに、親御さんが子どもだった頃にはロボット教室はほとんど存在していなかったでしょう。通った経験がないので、さまざまな疑問・不安を抱くのは当然のことです。この段落では、ロボット教室に子どもを通わせる際に、親御さんが気になりそうな注意点を解説します。
6-1.教材費が高い
ロボット教室のデメリットのひとつが、教材費が高いという点です。授業1回あたりの費用が高くなることはすでに述べましたが、ロボット教室では入会金や教材費といった費用が月謝のほかに発生します。入会金については、ほかの習い事と同じ水準かもしれませんが、ロボット製作を行うため教材費が高いのです。教材費は教室によって差がありますが、高額な場合は5万円以上かかる場合もあります。もちろん、教材費は毎月発生するものではなく、カリキュラムごとに発生するのが一般的ですが、学校の成績アップや資格取得など、目に見える成果の保証がないため割高感があります。
とはいえ、ロボットを製作し、動かしてみるという体験は学校や家庭ではできません。また、独自の大会を設けているところもありますし、ロボット教室で学んだことをきっかけに、大学でロボット工学を学んだ人や産業界に進んだ人もいます。学校や家庭でできない体験や将来に役立つ経験について、親御さんがどう評価するのかもポイントになるでしょう。
6-2.ケガをする可能性がある
ロボット教室では電子部品や機械を扱うため、ケガをするリスクがないとは言えません。また、取り扱いを間違えるとロボットの部品やパーツなどが壊れてしまう場合があります。もちろん、子ども向けのロボット教材は安全面に配慮して作られていますし、指導者も扱い方の注意をしてくれます。よほど乱暴なやり方をしない限り、子どもがケガをしたり、ロボットを破損させたりするリスクは低いと考えて大丈夫です。
ただし、なかには先端がとがっているパーツや、強力なモーターを搭載するロボットもあるため、子どもの不注意でケガをしてしまう可能性もあります。ロボットを動かす活動をしているときなど、子どもが興奮して走り回ったり、ふざけたりして教材を壊してしまうケースもあるかもしれません。授業中の体調不良やケガにつながる事故に関しては、教室側が責任を負わないことを規約に明記しているロボット教室もあります。また、教材の初期不良については交換の対象となりますが、故意に無理な力を加えてパーツを破損させた場合などは無償交換の対象外で、別途修理費用や教材費がかかる場合もあります。
ロボット教室に子どもを入会させるときには、指導者の話をよく聞くように約束をすることも大切です。興奮したときに感情をコントロールする力が身についていない場合には、もう少し年齢が大きくなってから通わせることを検討してもよいかもしれません。
6-3.女の子は通いにくいと感じることも
「リケジョ(理系女子)」という言葉が流行ったように、女性エンジニアの数も増えてきています。そのため、女の子でもロボットに興味を持って教室に通ってみたいという需要はゼロではありません。しかし、ロボット教室に通っている子どものほとんどは男の子です。世の中はジェンダーフリー・ジェンダーレスに向かっているため、男女関係なく話せる女の子や、女の子の友達がいなくても気にならない性格の子どもなら問題なく通えるでしょう。しかし、女の子のグループで行動したい性格の子どもや、女の子がいないと嫌だという子どもの場合、ロボット教室には通いにくいかもしれません。
ロボット教室のなかには、グループでロボットを製作するところと、個人のブースを設けてロボットを製作するところがあります。周囲に女の子がいないと気になってしまうタイプの子どもは、グループレッスンではなく個人のブースを設けている教室を探すのもひとつの方法です。数は少ないものの、女の子だけのコースを設置しているロボット教室もあります。また、プログラミング教室になるとロボット教室よりも女の子の比率が高めです。子どもに身につけてほしい能力にもよりますが、ロボット教室ではなくプログラミング教室を検討するのもよいでしょう。
6-4.教室によって合う・合わないの差が激しい
ほかの習い事にも言えることですが、指導者と子どもとの相性の問題があります。指導方法や教材が子どもに合っていなければ、長続きできません。生徒の自主性を育てるために指導者がほとんど指導を行わず、ヒントを与えるだけというところも見られます。初心者には指導者がていねいにヒントを出すなど、教室によって指導者の教え方は違いますが、わかりやすく教えてくれないとストレスを抱えてしまう子どもいるでしょう。
また、ロボット教材の見た目が子どもの趣味に合っていないときや、組み立て方が難しいときなども、子どもがストレスを抱える原因となります。指導者になる前は技術者だったなど、人と接する経験が少なかった指導者のなかには、子どもから見たときに説明がわかりにくい、難しいという人もいるでしょう。
教室や指導者との相性を見極めるためには、体験授業を受けて子どもとの相性は問題ないか、よく確かめましょう。なかには、複数回にわたって体験授業を受けられる場合もあります。また、2回か3回で完結する初心者向けの講座を受講するのもひとつの方法です。短い講座を受けて、通わせても大丈夫と判断できるのであれば1年のカリキュラムの講座を申し込むようにすれば、子どもが長く通えるでしょう。
6-5.プログラミング重視ではない
ロボット教室の多くが「プログラミングも学べる」と宣伝していますが、親御さんが「プログラミング教育」に期待している内容とは異なるため、注意が必要です。ロボット教室の小学生向けのカリキュラムは基本的にロボット製作が中心で、その過程でロボットを制御するための「ロボットプログラミング」に触れることはあります。しかし「Scratch」のようなプログラミング言語を使って、プログラミングについて学んでいくわけではありません。
また、パソコンを使ってアニメーションやゲームを作れるのは、プログラミング教室のほうです。ロボット製作ではなく、プログラミングを中心に学んでほしいという場合には、ロボット教室は最適な選択だとは言えません。教室のなかには、プログラミング教室とロボット教室の両方を設置しているところもあるので、体験授業を通して学ぶことをしっかり確認しておきましょう。
7.子どものプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOでは、残念ながらロボットを使ったカリキュラムは取り入れていません。その理由は、ロボットを組み立てる時間を省き、プログラミングそのものを学ぶ時間を十分に確保するためです。さらに、プログラミング教育 HALLOでは、3D空間を活用し、無限の表現が可能な環境を提供しています。パーツを追加購入する必要がなく、費用を抑えることができる点も大きな特徴です。
確かに、ロボットを組み立てて動かすことは子どもの好奇心を引き立てますが、プログラミング教育 HALLOではオリジナル教材「Playgram」を使い、子どもが楽しみながらプログラミングを学べるカリキュラムを提供しています。また、ゲーム作りを通じて子どもの創造力を育み、表現力を養うことで、完成した時の達成感を味わい、それが自信へと繋がります
カリキュラム:https://www.hallo.jp/fs/course/curriculum/
8.ロボット教室は向き不向きがある! 子どもに合うか確認しよう
ロボット教室は子どもの好奇心をかきたて、独創性や発想力を養うのに適した習い事です。ただし、子どもの性格や趣向によってはロボット教室に向かない場合があります。また、プログラミング教室とは学ぶ内容や教室の雰囲気が異なります。もしも、子どもにプログラミング教育を学んでほしいと考えているのであれば、ロボット教室ではなく、プログラミング教育の体験から始めてみてはどうでしょうか。
ロボット教室とプログラミング教室の違いについては下記の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。
ロボット教室とプログラミング教室の違い|おすすめの習い事はどっち?
執筆者:プログラミング教育HALLOコラム編集部