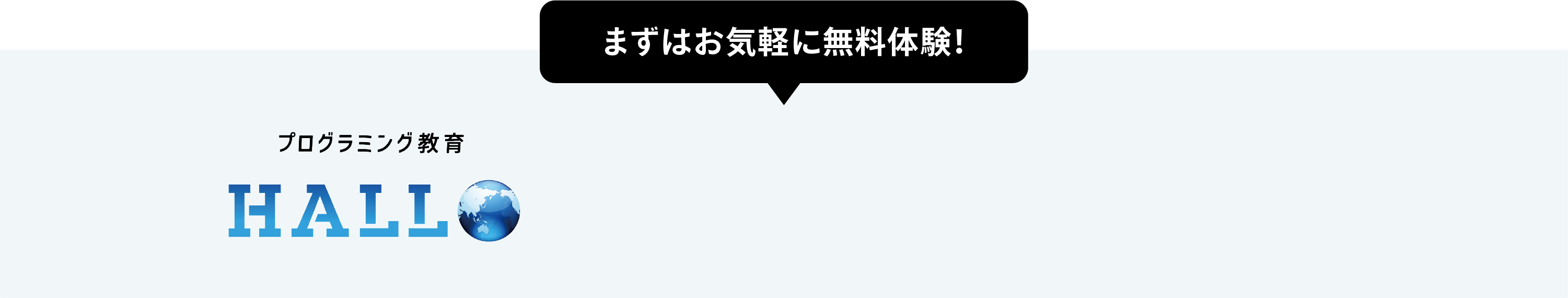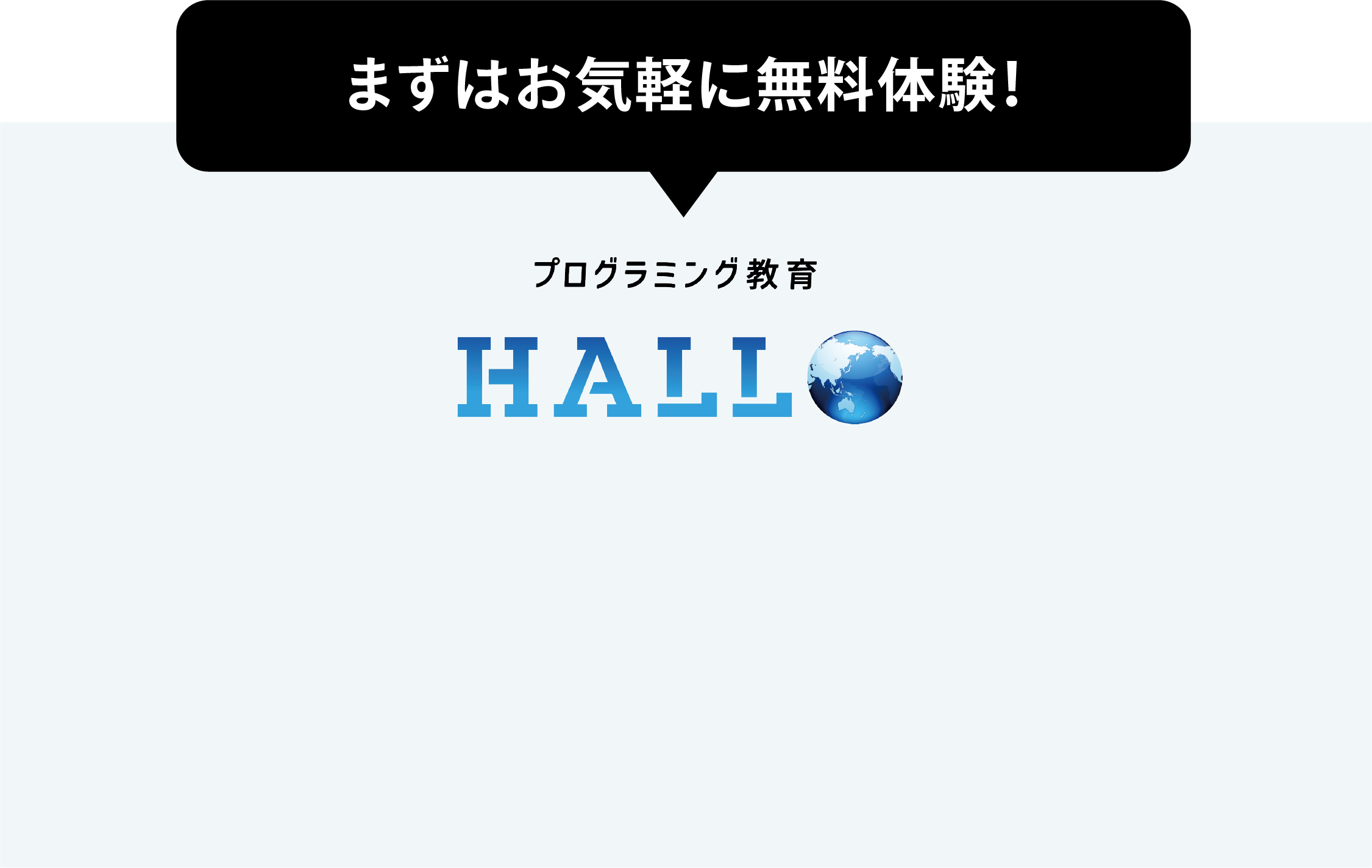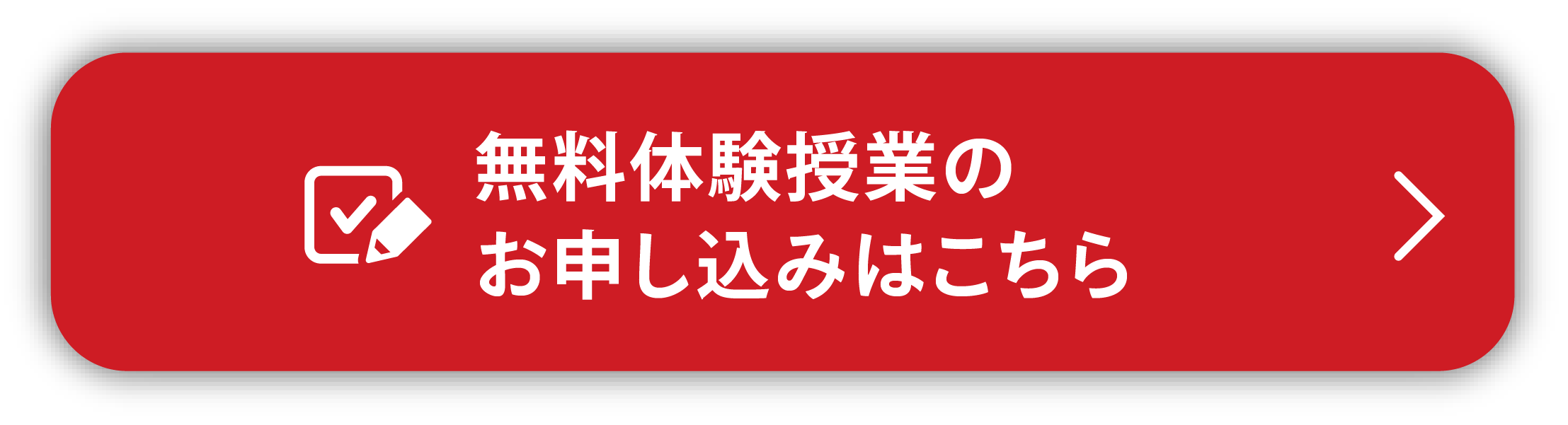プログラミングのオブジェクト指向とは?基礎知識を徹底解説
更新日:2025.4.18
公開日:2025.4.17
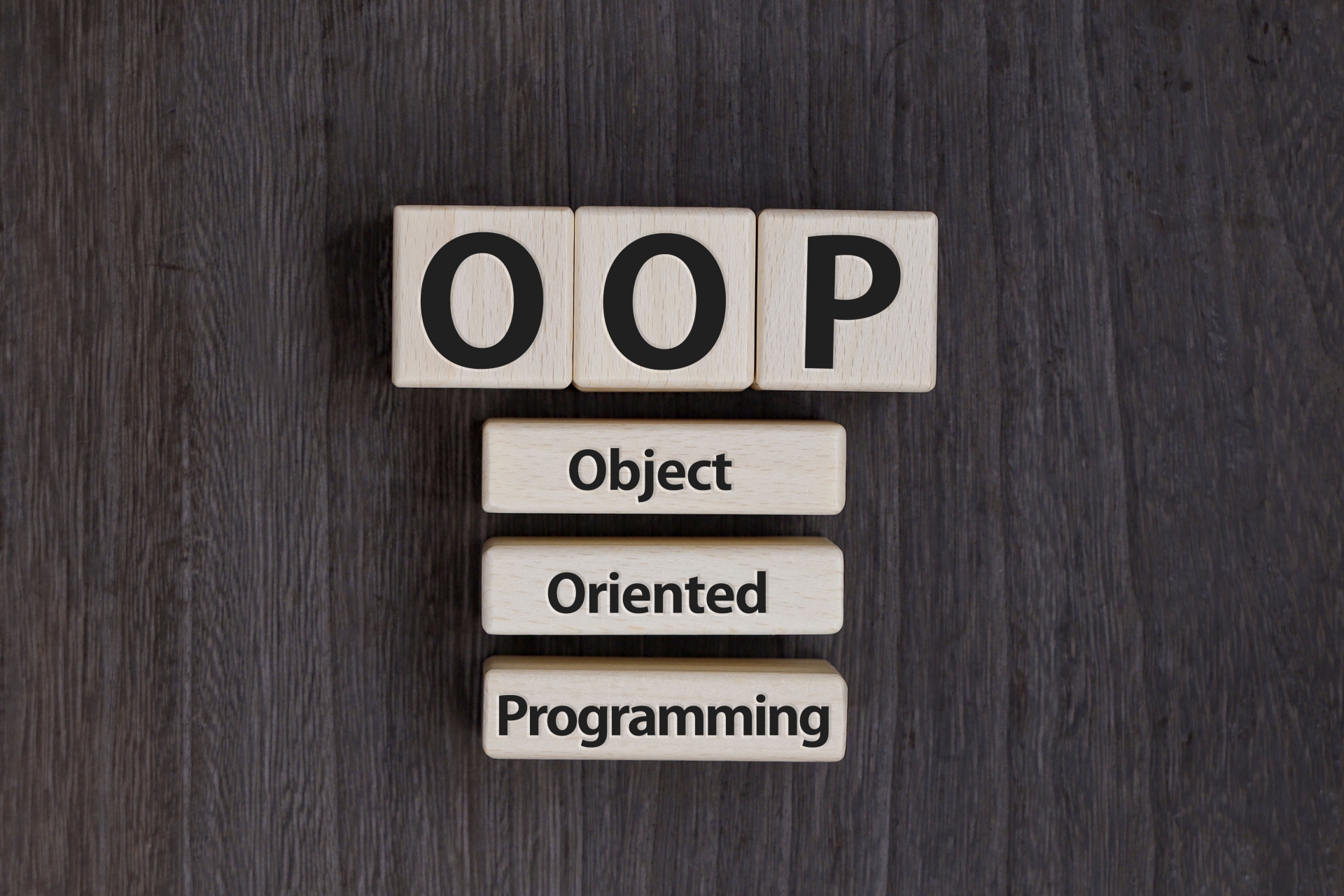
プログラムをより分かりやすく、そして柔軟に設計するための考え方として、オブジェクト指向が注目されています。まるで現実世界のように、プログラムの中に「モノ」(オブジェクト)を作り出し、それらが互いに関係し合いながら動作する仕組みです。今回は、オブジェクト指向の基礎から、実践的な活用方法までを詳しく解説します。
この記事の目次
オブジェクト指向とはどういう意味?
オブジェクト指向とはプログラミングの考え方のひとつで、「役割をもったモノ」ごとに分けて、「モノ」同士がどのように関係してくるのかを指定してシステムを作り上げていくことです。例えば、ゲームでキャラクターを作る時、歩いたり攻撃したりする「動作」ができます。「動作」が「役割を持ったモノ」で、動作のうち「歩く」「攻撃する」を「モノ」をすると、その攻撃をするときにどのように歩くのかなど、互いの関係性を指定してキャラクターを作っていくことを、オブジェクト指向プログラミングといいます。
オブジェクト指向の具体例
オブジェクト指向を理解するには、まず次の3つのワードを理解しておく必要があります。
●クラス・・・オブジェクトの設計図になるもので、どのような機能があるのか、行動できるのかなどを設定します。
●プロパティ・・・属性を意味し、オブジェクト(モノ)が持っている色や形などのデータを指します。
●メソッド・・・オブジェクト(モノ)が持つ、アクションを起こす処理のことを指します。
これらのワードは、オブジェクト指向を学ぶ際に多く出てくるので、覚えておくようにしましょう。
では、オブジェクト指向とはどのようなものなのか、具体的に見ていきましょう。
オブジェクト指向を説明する時によく例に挙げられるのが自動車です。
自動車の設計図であるクラスを元に、メーカーや色、大きさなどのプロパティ、走る、止まる、バックするなどのメソッドを組み込んでいきます。そうして作成したのがオブジェクトになります。
オブジェクト指向が生まれた背景
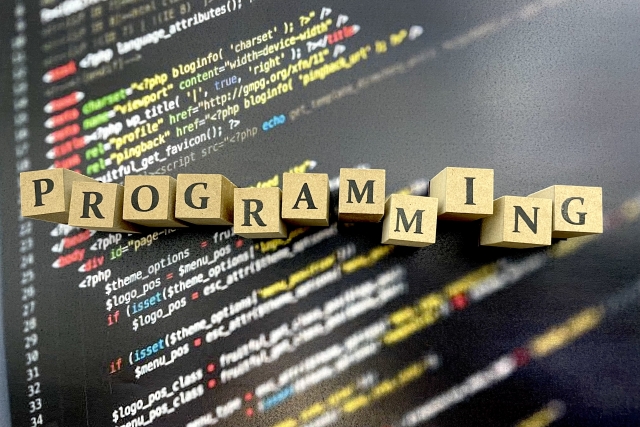
オブジェクト指向は、1970年に生まれたプログラミングの考え方です。現在、C++やC#、Pythonなど、多くのプログラミング言語がオブジェクト指向を取り入れているため、すでにこの言語を使っている人は、オブジェクト指向に触れていると言えます。
オブジェクト指向は、「よく分からない」、「古い考え」と言われることもあります。このように言われる理由は、オブジェクト指向が抽象的な概念が多いためです。しかし実は、効率よくプログラムを設計・開発できるなど、メリットもたくさんあります。
オブジェクト指向のほかにも、プログラミングの考え方(プログラミングパラダイム)があり、いくつかの種類があります。
①手続き型プログラミング
手続き型プログラミングは、コンピュータに「最初にこれをして、次にこれをして」と、順に指示を出すプログラミングの考え方です。例えば、ブロックで家を作ると考えた時、まずは土台を組み立てて、壁を組み立ててから、屋根を取り付けるというように、完成までの手順を一つひとつ細かく書いていきます。プログラミングでも、最初に何の処理をして、次にどのような処理をするかというように、手順を積み重ねてコンピュータに実行させます。
手続き型プログラミングの特徴として、プログラムの構造がシンプルでわかりやすいというメリットがあります。そのため、小さなプログラムを作る時には効率よく作ることができます。しかし、ブロックの家が大きく、窓をつける、部屋を仕切るなどの要素が増えてくると、それだけ手順が複雑になってきます。プログラムの場合も同じで、大規模になればなるほど、コードの管理が難しくなるというデメリットもあります。また、違う形のブロックの家を作りたいと思った時、手順が同じようにはならないので、作ったコードを別のプログラムで再利用できないことが多くあります。
代表的な手続き型プログラミングには、C言語やCOBOL、Fortran、Pascal、Perlなどの言語が使われています。
②構造化プログラミング
構造化プログラミングは、プログラムの手順を一つひとつ明確に記述していくプログラミングの考え方です。
構造化プログラミングでは、プログラムを「順次構造」と「選択構造」、「繰り返し構造」という3つの基本構造を組み合わせて作っていきます。これらを組み合わせることで、複雑な処理も表現できるようになります。車のナビゲーションを例にすると、出発地から目的地までのルートを、次の交差点を右に、何キロ直進など、細かく指示することで、目的地に案内してくれるというように、プログラムを順に実行していきます。
構造化プログラミングのメリットは、プログラムの構造がシンプルで、理解しやすく、他のプログラマーとも共有しやすいという点です。また、プログラムの間違いを見つけやすく、修正も簡単にできます。しかし、手続き型プログラミングと同様に、プログラムが大きくなると、コードが長くなり管理が難しくなるという点がデメリットとして挙げられます。
③関数型プログラミング
関数型プログラミングは、数学の関数の概念をプログラミングに取り入れた考え方で、「データに何らかの処理を加えていく」の連続で組み立てます。この関数をプログラムの基本単位として考え、関数の組み合わせによってプログラムを構築していきます。
例えば、料理を作る時で考えると、食材を組み合わせて、切る、混ぜる、煮る、焼くなど、一つひとつの作業を関数と考えます。「野菜を切る」という関数に「玉ねぎ」という入力を与えると、「切った玉ねぎ」という出力が得られます。「肉を焼く」、「調味料を混ぜる」などの関数を組み合わせて、ひとつの料理を作るレシピを作成します。
関数型プログラミングの特徴として、純粋関数という概念があります。純粋関数は、同じ入力に対して常に同じ値を返し、外部の状態に影響を与えたり、外部の状態から影響を受けたりしません。この性質は、プログラムの予測可能性を高め、バグを減らすことにつながります。
関数型プログラミングのメリットは、コードが簡潔になり再利用性が高いこと、並列処理に向いているため大規模なデータ処理に適していることが挙げられます。デメリットは、学習コストが高い、既存のプログラミング言語との互換性が低いといった点が挙げられます。
④オブジェクト指向プログラミング
オブジェクト指向プログラミングは、冒頭に記述している通り、「役割をもったモノ」ごとに分けて、「モノ」同士がどのように関係してくるのかを指定してシステムを作り上げる事の手順ではなく、モノを作り上げる操作という考え方です。
オブジェクト指向プログラミングは難しそうというイメージがあり、つまずいてしまうこともあるでしょう。しかし、きちんと理解できれば、開発の時間短縮にも役立ちます。
オブジェクト指向プログラミングのメリットは、効率よくプログラムを設計・開発できること、問題の特定がしやすいこと、仕様が変わっても簡単に対応できることなどが挙げられます。一方デメリットは、データと処理がひとまとめになっているので、どのコードが実行されているのか分かりにくく、設計に時間がかかる事などが挙げられます。
オブジェクト指向で重要な三大要素とは?

オブジェクト指向の三大要素とは、①継承、②カプセル化、③ポリフォーリズム(多態性)があります。それぞれどのようなものなのか、その具体例やコーディング例を見ていきましょう。
①継承
継承は、既存の親クラスの機能をそのままに、新しい子クラスを作成します。親から子が遺伝子を受け継ぐように、親クラスの設計図を元に、子クラスの設計図を拡張していくイメージを持つと分かりやすいでしょう。継承は、プログラム設計の効率化を目的としています。子クラスは、親クラスのプロパティやメソッドを自動的に取得し、コードの重複を減らし、再利用しやすくなります。また、機能の変更が必要な場合は、親クラスのコードを修正するだけで、子クラスにも変更が反映されるというように、保守性が高まります。
継承を使用することで、共通する処理が親クラスに集約され、子クラスでは、個別のメソッドを追加することができます。継承は、共通性を持つオブジェクト群を効率的に管理し、プログラムの構造を簡潔かつ明確にするための重要な概念です。
【継承の具体例】
継承は、どのような指示を出すのか、例をあげてみましょう。
2匹の犬が吠える指示を出したいとします。犬を表す親クラスでは、走る、食べるなどの共通の動きを指示していきます。これは、2匹の犬両方に共通する動きなので、1つのコードでそれぞれに共有できます。そのクラスを元に犬の個性となる具体的な吠え方を指示する子クラスを作成していきます。例えば、1匹の犬が「ワンワン」と吠えるとして、もう1匹の犬は「キャンキャン」と吠えるというように、異なる吠え方をそれぞれに指示することができます。
【継承の正しいコーディング例】
Javaでオブジェクト指向を用いた継承のコーディング例は下記のとおりです。
継承のキーワードは「extends」、「Animal」クラスが親クラス、「Dog」クラスが子クラスです。「Dog」クラスは「Animal」クラスの「move()」メソッドを継承し、さらに独自のメソッド「bark()」を持っています。
class Animal {
public void move() {
System.out.println("動きます");
}
}
class Dog extends Animal {
public void bark() {
System.out.println("ワンワン");
}
}
class Puppy extends Animal {
public void bark() {
System.out.println("キャンキャン");
}
}
②カプセル化
カプセル化とは、データ(プロパティ)やそれに関連する処理(メソッド)をひとつの単位としてまとめ、外部から直接アクセスできないようにする仕組みです。これは、データの安全性の確保やプログラムの設計や保守を簡単にする重要な概念です。
まるでカプセルの中にデータを閉じ込めて、外からはその中身を直接触ることができないように、オブジェクトの内部データ(フィールド)を外部から直接アクセスできないようにします。
例えば、「自動車」というオブジェクトで考えてみましょう。自動車には、エンジンやタイヤなどの内部部品と、発進・停止などの外部から見える動作があります。カプセル化では、エンジンの状態やタイヤの空気圧といったフィールドを外部から直接触れないようにし、代わりに「発進」や「停止」といったメソッドを呼び出すことで間接的に操作します。
そうすることで、外部からの不正なデータ変更を防げるだけでなく、他のプログラムでも安心して利用できるようになります。
【カプセル化の具体例】
例えば、「車」を表すクラスを考えてみましょう。車の速度や燃料残量をプロパティとして定義しますが、これらを直接操作できないように「private」修飾子を付けて保護します。そして、燃料を補給するメソッドや車を走らせるメソッドを用意し、そのメソッドを通した時だけプロパティを変更できるようにします。
燃料を補給するメソッドでは、補給量が負の値でないかをチェックすることで、不正な操作を防ぎます。また、車を走らせる際には燃料残量を確認し、残量が不足していれば動かないように制御します。これにより、外部のコードから直接データを変更されることで車の状態が矛盾することを防ぎ、安全で正確な動作が保証されます。
【カプセル化の正しいコーディング例】
Javaでオブジェクト指向を用いたカプセル化のコーディング例は下記のとおりです。
「Car」をクラスとし、「color(色)」、「speed(速度)」は、車の内部状態を表すフィールドです。「private」修飾子をつけることで、外部から直接アクセスできないようにしています。
public class Car {
private String color;
private int speed;
// コンストラクタ
public Car(String color) {
this.color = color;
this.speed = 0;
}
// getterメソッド
public String getColor() {
return color;
}
// setterメソッド
public void setColor(String color) {
this.color = color;
}
// 行動を表すメソッド
public void accelerate() {
speed += 10;
System.out.println("加速しました。現在の速度は" + speed + "km/hです。");
}
}
③ポリモーフィズム(多態性)
多態性とは、同じ名前のメソッドに対して、異なるオブジェクトがそれぞれ異なる方法で応答するという性質のことです。同じ言葉でも、話す相手や状況によって返ってくる答えが違ってくるように、プログラミングでも、同じメソッド呼び出しが、実行されるオブジェクトによって違った結果になります。
例えば、「話す」というメソッドがあったとします。このメソッドを人間に呼びかけると「こんにちは」と返ってくるかもしれませんが、犬に呼びかけると「ワンワン」と吠え、猫であれば「ニャー」と返ってきます。このように、同じメソッドでも、呼び出されるオブジェクトによって実行される内容が異なるのが多態性です。
ポリモーフィズムは、同じソフトウェアで異なるオブジェクトを扱えるので、プログラムの柔軟性が高まり、新しいクラスを追加する時にも、既存のコードを大きく変更する必要がないため、システムの拡張がしやすくなるなどのメリットがあります。
また、ポリモーフィズムは、大きく分けて、オーバーライド(動的多態性)と、オーバーロード(静的多態性)の2種類があります。
【オーバーライド】
親クラスで定義したメソッドを継承した子クラスで、名前を変えずに別の処理として書き換えることを言います。
例えば、「動物」という親クラスに「鳴く」というメソッドが定義されている場合、犬や猫は、それぞれ違った鳴き声のため、「犬」クラスや「猫」クラスでは、「鳴く」メソッドをオーバーライドし、それぞれの動物に合った鳴き声を出すように実行できます。
このように、親クラスで共通の機能を定義しておけば、子クラスでその機能を継承し、必要な部分だけオーバーライドすることで、コードの重複を減らして再利用しやすくなります。ただし、親クラスを変更した時に、子クラスに影響が出る可能性もあるので、クラスの関係を把握し、意図しない動作にならないように注意しなければいけません。
【オーバーロード】
同じ名前のメソッドを、渡す情報(引数)の種類や数によって、それぞれに違う処理をするようにできる機能のことです。
例えば、「動物」というクラスで「食べる」というメソッドを定義した場合、犬なら食べる引数に「骨」、猫なら「魚」、鳥なら「虫」というように、動物の種類によって異なった処理をさせることができます。これにより、同じ名前のメソッドでさまざまな状況に対応できるためコードの重複を減らし、少ないコードで書くことができます。また、メソッドの名前が同じなので、コードが読みやすくなるというメリットもあります。
【コンポーネント化】
コンポーネント化とは、ひとつの機能を複数の部品(コンポーネント)に分割し、それぞれの部品がポリモーフィズムの特性を持つように設計することといいます。つまり、コンポーネント化することで、コードの再利用ができるようになるということです。これにより、システム全体が柔軟で拡張性の高いものになります。
例えば「表示する」という機能がある場合、この機能を表示するデータの種類(テキスト、画像など)や表示する場所(画面、印刷など)ごとに異なるコンポーネントとして分割し、それぞれのコンポーネントが「表示する」という同じインターフェースを持ちながら、異なる処理を実行できるようにします。こうすることで、新しい表示方法を追加したい場合に、既存のシステムに大きな変更をすることなく、新しいコンポーネントを追加するだけで対応できるようになります。
オブジェクト指向のメリット

オブジェクト指向プログラミングでは、現実にあるものをプログラムの中で表現するという考え方を持っています。この考え方によって、プログラム開発の効率が上がります。そのうえ多くのメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのかを紹介します。
コードの使いまわしができる
オブジェクト指向プログラミングの最大のメリットともいえるのが、コードの使いまわしです。一度組み立てたオブジェクトは、別の場所で何度も再利用できるということです。
例えば、車のエンジンやタイヤ、ドアなどの部品はそれぞれに役割を持っています。これらは、別の車にも共通して使うことができます。エンジンというオブジェクト、タイヤというオブジェクト、ドアというオブジェクト、それぞれを組み合わせることで、また別の車の開発が可能です。
それぞれのオブジェクトの不具合がなければ、使い回しをしたときにも不具合が起こらない可能性が高いので、開発効率がアップし、スムーズな作業ができるようになります。
不具合の原因を特定しやすい
オブジェクト指向プログラミングでは、不具合の原因を特定することも、大きなメリットに繋がります。
オブジェクトはそれぞれの役割があると記述しましたが、このオブジェクトがあることにより、不具合が出た際、どのオブジェクトが原因なのかを特定しやすくなります。
例えば、車が動かなくなってしまった際、エンジンかタイヤが不具合を起こしていると予想できます。そして、タイヤが正常に動いていることが分かれば、エンジンが原因であると特定できます。このように、不具合箇所の発見がしやすくなることがメリットのひとつということになります。
仕様変更に対応しやすい
オブジェクトはカプセル化されており、オブジェクトに修正を加える場合は、そのオブジェクトに関連する部分だけに影響されるので、ほかのオブジェクトに影響しにくくなります。そのため、仕様変更しやすいといえます。例えば、車のドアの色を変更したい時、車全体ではなく、ドアのオブジェクトだけに色を指示するコードを修正すれば、ドアだけがその修正の影響を受けて、車体などの色には影響しないということです。
仕様変更に対応しやすいということは、物事の状況に柔軟に対応できるということで、時代や使う人が変われば、当然仕様変更も必要になります。オブジェクト指向プログラミングは、このような変化にも柔軟に対応できる考え方で、拡張性が高いプログラミングが実現できます。
プロジェクト全体を把握しやすい
オブジェクト指向プログラミングは、プログラミングの構造が視覚的にとらえやすいという特徴があります。それぞれのオブジェクトがどのような役割を持っているのか、オブジェクト同士がどのように連携しているのかもわかりやすくなっています。そのため、特に大規模なシステム開発になるとコードが複雑になってきますが、オブジェクトに分割されていることでそれぞれの役割が明確になり、全体を把握しやすくなります。また、多くの開発者が関わる場合でも、共有しやすいというメリットがあります。これにより、チーム開発でもスムーズに、誰でも理解できるようなシステムが組めるようになります。
オブジェクト指向のデメリット・課題

たくさんのメリットがあるオブジェクト指向プログラミングですが、メリットばかりではなく、デメリットも当然あります。どのようなデメリットがあるのかをきちんと理解することも大切です。
複数のオブジェクトを操作できない
オブジェクト指向では、それぞれのオブジェクトが役割を持っているおかげで、整理しやすくなるというメリットがありますが、その一方で、複数のオブジェクトを一斉に動かすのは少し手間がかかるデメリットもあります。
例えば、たくさんの車を表すオブジェクトに「スピードを上げる」という命令を出したい場合、オブジェクト指向では、それぞれの車にひとつずつ命令を出さなければいけません。車が多いほど、その分命令を送るコードも長くなり、問題が起こりやすくなります。さらに、車の種類によってスピードが異なる場合は、それぞれの車に合わせた命令を出さなければいけないため、複雑になってきます。
しかし、オブジェクト指向では、さまざまな状況に対応するためにデザインパターンというものがあります。このパターンを活用することで、複数のオブジェクトを効率的に操作できることもあります。
オブジェクトのメッセージを渡せない
オブジェクト指向では、オブジェクト同士メッセージをやり取りすることで、互いに協力して役割をする特徴があります。しかし、このメッセージのやり取りがうまくいかないことがあります。
これは、オブジェクト同士の関係が複雑になることがあるためで、1つのオブジェクトが他のオブジェクトに頼りすぎていると、少しの変更でも全体に影響が出てしまいます。また、どのオブジェクトがどのオブジェクトにどのようなメッセージを送るか分かりにくくなってしまうと、どこでエラーが起こっているのかが見つけにくくなるデメリットがあります。
このような問題を防ぐためには、オブジェクト同士の関係をシンプルにして、メッセージのやり取りを明確にする必要があります。そのために設計からしっかりと計画を立てなくてはいけないので、注意が必要です。
レイヤを分ける必要がある
オブジェクト指向では、プログラム全体を整理するために、役割ごとにレイヤに分ける必要があります。レイヤに分ける必要性としては、複雑なプログラムを管理し、それぞれのオブジェクトがそれぞれの役割に集中できるようにするためにです。レイヤに分けることで、保守や拡張が楽になります。
ある機能を変更したい場合、その機能を担当しているレイヤだけに修正を入れたとしても、ほかのオブジェクトに影響が出にくくなります。
ただし、レイヤを分けるためには、設計に手間がかかるというデメリットがあります。どのオブジェクトをどのレイヤに置くのかなどを考えなければいけないので、その点で複雑で理解しにくいと言われるひとつの原因ともいえます。しかし、安定したプログラムを作るには、レイヤは欠かせないものと覚えておきましょう。
プログラミングを学ぶならプログラミング教育 HALLO
プログラミングをするには、さまざまな手法があります。オブジェクト指向プログラミングもそのひとつで、それぞれの手法にメリット・デメリットがあるように、オブジェクト指向プログラミングにもメリットとデメリットがあります。
本格的に学びたいと思った時、プログラミング教室に通って身につける方法が確実です。プログラミング教室は多々ありますが、教室を選ぶひとつのポイントが、プロの講師であることです。プロの講師に教わることで、本やネット、動画などでは理解できなかったことや、疑問点なども、その場ですぐに質問でき、さらにプロだからこそ、専門的な疑問に対しても、解決できるサポート力があります。
プログラミング教育 HALLOの講師は、現役のプログラマーも中にはいます。現場で活躍している専門家だからこそ、サポート力が高く、日々進化していくIT業界の情報にも長けているため、安心してレッスンを受けることができます。
プログラミング教育 HALLOでは、随時無料体験レッスンを行っていますので、教室に通うことを検討している方は、ぜひ無料体験に参加して、講師の指導やレッスン内容、教室の雰囲気などを実感してください。
まとめ
オブジェクト指向とは、プログラミングの手法の一つで、プログラムをわかりやすくするために生まれた考え方です。その使い方は難しい、理解できないと言われがちですが、使い始めると、とても便利な方法だということが分かります。多くのメリットがある一方、複雑化しやすいというデメリットもありますが、保守性が高く、安定したプログラムを作る為には、オブジェクト指向は強力な武器となります。