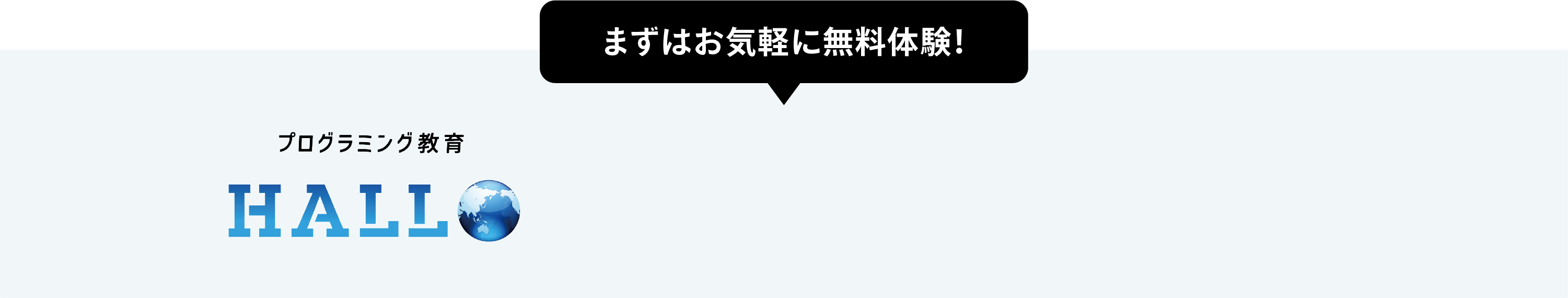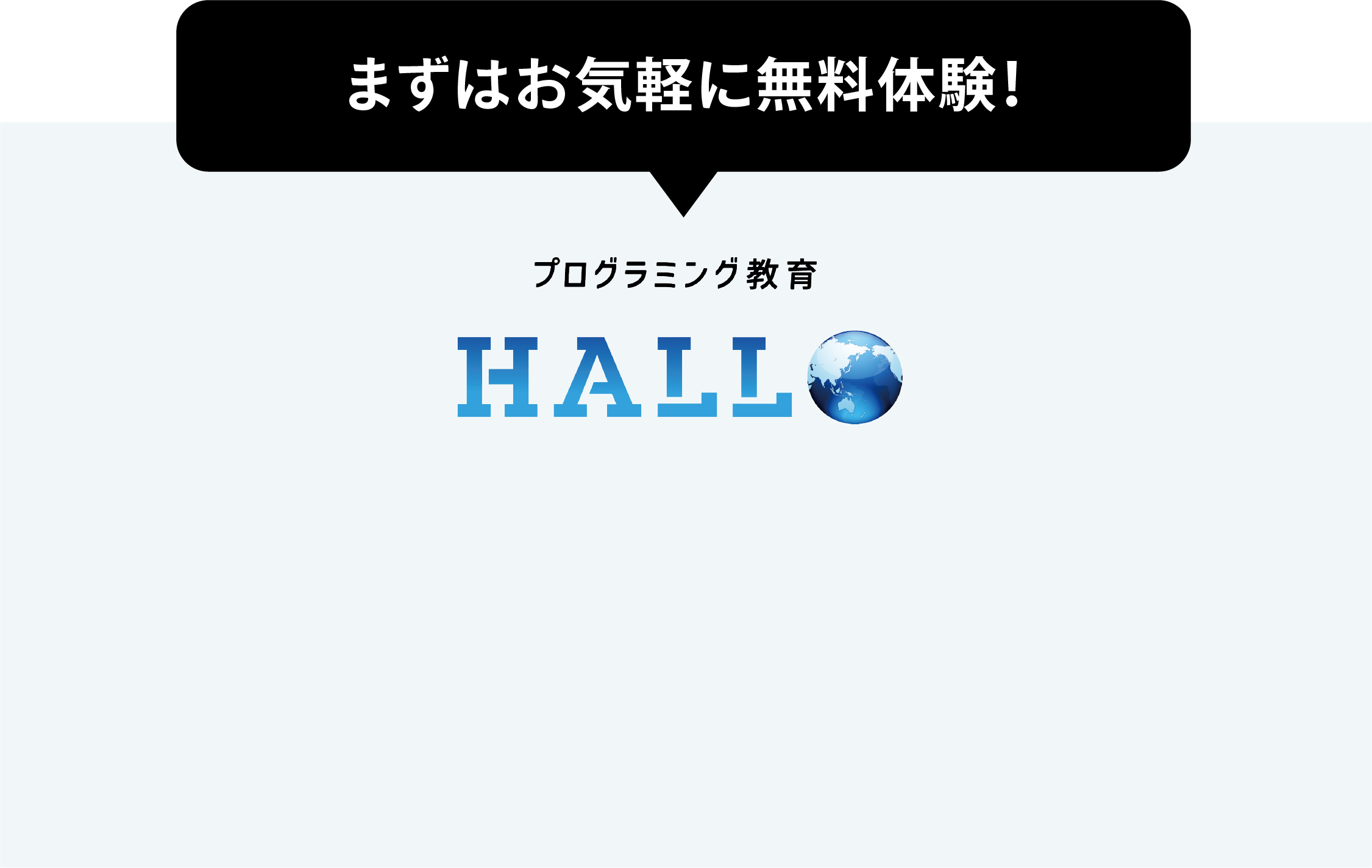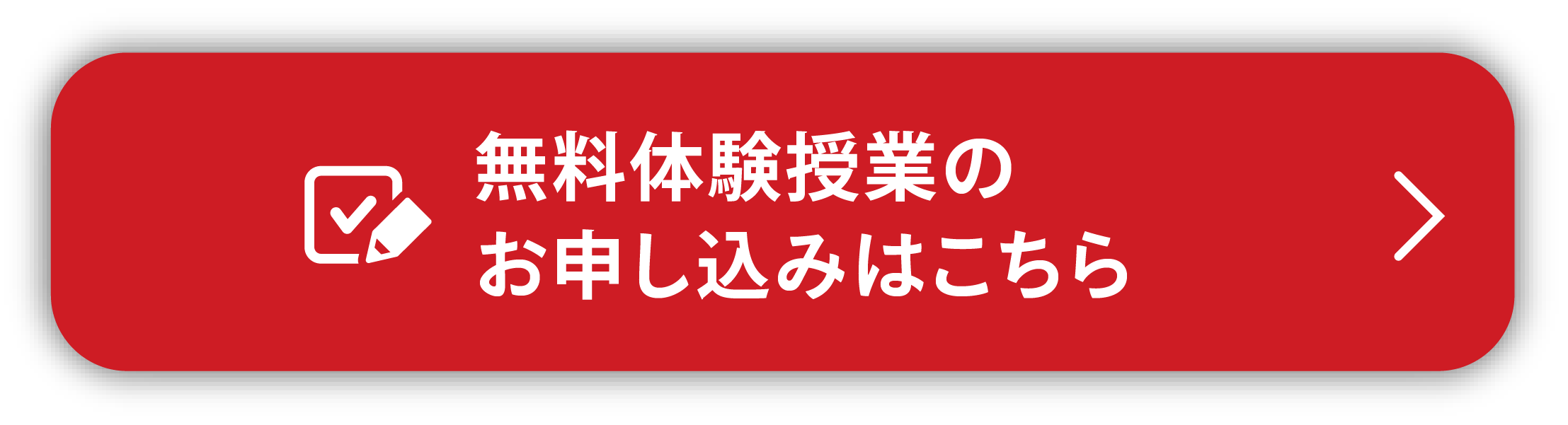中学校でプログラミング教育が必修化された背景と授業内容の変更点を解説
更新日:2025.4.28
公開日:2022.10.19

2021年から中学校で本格的にプログラミング授業がスタートしましたが、実際にどのような内容が学べるのか、具体的にイメージできていない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、中学校のプログラミング授業で身につけられるスキルや、それによって育まれる力について詳しく解説していきます。
この記事の目次
1.2021年度から強化された中学校でのプログラミング教育

まずは、中学校でのプログラミング教育についてどのようなものなのかを詳しく見ていきましょう。
1-1.プログラミング教育自体は2012年から開始
中学校でのプログラミング教育は、2012年からすでに技術・家庭科の授業で必修化されていました。中学校では、小学校で学んだプログラミングの基礎を活かして、身の周りのものをもっと便利にするにはどうすればいいか、プログラミングを使って解決していくという課題に取り組んでいきます。
1-2.2021年、中学校のプログラミング教育を全面実施
中学校でプログラミング教育が全面実施されたのが2021年。「必修化」と「全面実施」の何が違うの?と思われるかもしれません。「必修化」は、必ず勉強しなければいけない科目という意味です。一方「全面実施」とは、2021年度に中学1年~3年すべての生徒が卒業するまでに中学校でのプログラミング教育を完了しているという意味になります。
つまり、中学校でのプログラミング教育の始まりは2021年度ではなく、全面実施される前から、すでにプログラミング教育が実施されていました。
1-3.中学校プログラミング教育必修化の背景
将来子どもたちが大人になった時、ロボットが社会で活躍したり、AIでもっと仕事や家事が楽になったり、そんな未来が想像できます。そんな未来の社会を「Society5.0」といいます。「Society5.0」は、プログラミングの力がなくては成り立っていきません。プログラミングを学ぶことは、技術を身につけるだけでなく、生活が便利になる新しいアプリを作ったり、世の中にある問題や課題を解決するシステムを開発したりすることにつながっていきます。今の子どもたちがプログラミングを学ぶ背景には、未来の社会を創るための人材育成をするためという考えがあります。
1-4.新学習指導要領による変更点
2020年までのプログラミング教育と比べて、現在の新学習指導要領では、主に、双方向のコミュニケーションや問題解決能力、情報モラルを学んでいきます。具体的には、双方向のコミュニケ―ションというのは、友達とチャットで話すように、コンピュータとも言葉でやり取りをするAI(人工知能)に質問して答えを探す勉強をします。問題解決能力では、身の周りのことで、「もっとこうすれば便利になるのに」といった考えをプログラミングを使って解決する方法を練習しています。そして、情報モラルでは、インターネットを使うときに、どのようなことに気をつければいいのか、安全に使えるようにルールを学んでいきます。
これらを学んでいくことは、子どもたちの今現在だけでなく、将来大人になって社会に出た時にも、役立つ力をつけていくことにつながっていきます。
2-2.小学校、中学校、高校のプログラミング教育の違い

プログラミングの勉強は、段階的に難しくなっていきます。小学校では、ゲームを作ったり、ロボットを動かしたりする中で、「プログラミング的思考」を育てることを目的としています。中学校では小学校で学んだ基礎を元に、センサーを使ったロボットの操作や簡単なアプリなど、実際にプログラムを作っていきます。そして高校では、さらに専門的になり、Webサイトや実用的なアプリを作るなど、実際に利用できるプログラミングに挑戦していきます。
2.中学校におけるプログラミング教育の実態
中学校のプログラミング学習は、どのような内容で実践されているのでしょうか。
2-1.学習内容
中学校のプログラミング学習は「技術」の科目の中で「情報の技術」に含まれています。「(1)生活や社会を支える情報の技術」、「(2)ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」、「(3)計測・制御のプログラミングによる問題の解決」、「(4)社会の発展と情報の技術」の4つの観点から学習が進められます。
2-2.実践事例
中学校で実際に実践されている4つの観点に関する授業例を見てみましょう。
【2-2-1.「(1)生活や社会を支える情報の技術」の実践事例1】
普段からよく利用するコンビニを例に挙げ、情報ネットワークを活用したレジのPOSシステムの技術を疑似体験する授業が行われました。実践授業では、無人店舗を想定し、制約条件とお客様のニーズを明確にすることから始めます。POSシステムに似た教材を使って、買い物体験やデータ分析体験をしていき、そこで得られた情報を元に、おすすめ商品のリコメンドをする簡単なプログラムを作成していきます。データ分析では、年代や性別のクロス集計を行い、ユーザーに適した商品を表示させる工夫も行われました。生徒がシステム開発者になった場合、レジを無人化するにはどのようにすればよいかと、技術の見方や考え方を体験して学んでいきます。
【2-2-2.「(2)ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」の実践事例2】

「AI(人工知能)画像認識技術で社会の問題を解決しよう」というテーマで行われた授業で、無人レジシステムを作るという課題です。Scratchというプログラミングソフトを使って、AIが商品のバーコードを自動で読み取ってくれる。そこに生活や社会の問題を見つけていきます。例えば、レジでの待ち時間を少なくしたり、会計のミスを減らしたり、プログラミングをどのように組むことで、問題解決ができるかを実践していきます。顧客側とシステム開発側の両方からAI活用場面を考えることができます。
【2-2-3.「(3)計測・制御のプログラミングによる問題の解決」の実践事例3】
「2025年の人口の推移から21歳の自分たちが直面する社会」をテーマに取り組んだ事例があります。その中では、医療機器の開発・創造や普及した理由とその過程を調べて、問題を見つけます。そして、患者が求めるニーズを、これまでに学んだプログラミングの技術や知識を活かして、どのように問題解決をすればいいかを考えていきます。自分が患者になったとして、患者にとってどのようなことが必要か、どのようなものを求めているかを、医療機器メーカーや販売会社、医療機器の研究をする大学教員と共同して取り組みました。
【2-2-4.「(4)社会の発展と情報の技術」の実践事例4】
(1)~(3)で学んだプログラミングの技術で、社会ではどのように役に立つのか、生活にどう活かすことができるのかを学びます。そのうえで、よりよい生活や社会を実現するために、情報の技術のあり方について話し合い、自分の考えを発表していきます。例として、スマート農業などの新しい情報の技術を取り上げ、社会や環境経済などから見た、改良や応用などをグループで考え、それを元にまとめて発表をしていきます。
2-3.指導教員
学習指導要領が新しくなりましたが、プログラミング教育を行う教員については従来のままです。ただ、指導力の向上のために新しくなった学習指導要領の説明会が開催されたり、独立行政法人教職員支援機構が行う夏休み研修に参加したりすることが可能です。また、YouTubeに解説動画の投稿をしているため、わからない部分は何度でも見返せます。さらに、メーリングリストを用意しており、そのなかで良い実践事例について紹介されているので参考にすることも可能です。
3.中学校におけるプログラミング教育の課題
中学校でプログラミング学習を行う場合、課題もないわけではありません。こちらでは、どのような課題があるのか、以下4点でまとめました。
・小学校~高校まで一貫した教育の実施
・教師の指導力
・設備投資の必要性
・セキュリティの脆弱性
3-1.小学校~高校まで一貫した教育の実施
小学校から高校までプログラミング学習が必修となりましたが、それぞれの段階での連携がとれていない状態です。具体的には、小学校で学ぶ内容については各校に任せられているため、バラついています。学習内容はプログラミングに関する文字入力や論理的思考など、直接的な技術に関わるものではありません。ただ、学習内容の進め方が異なる以上、複数の小学校から各校の卒業生が1つの中学校に進学して学ぶ場合、習得内容に差が出てしまいます。そのような状態にならないためには、中学校での学習方法に工夫が必要です。
3-2.教師の指導力

中学校でのプログラミング学習を担当する多くの教師は、専門的にプログラミングを学んだ経験がないため、指導にあたることに不安を感じている場合も少なくありません。文部科学省は教師向けの研修を実施していますが、全体的なスキルアップには時間がかかると考えられています。プログラミングはその内容自体が難易度が高く、教員にとっても指導が難しい場合が多いため、負担が大きくなる可能性もあります。
そのため、教師の負担を軽減し、より分かりやすく効果的な授業を提供するために、新たな教材の作成や指導例の公開、さらには実践的なサポート体制の構築が求められています。これらの工夫により、教師が自信を持ってプログラミングを教えることができ、生徒にとってもより学びやすい環境が整うことでしょう。
3-3.設備投資の必要性
プログラミングにおいてはパソコンなどのIT機器を使用した授業が多くなります。しかし、投資予算の少ない学校では、生徒全員がしっかりと学べるような設備を十分に用意できないケースも少なくありません。そのような場合、学校によって教育環境に差が生まれる可能性があります。パソコンやタブレットなどは1台1台がそもそも高額ですし、生徒の人数分以外にも使用しているパソコンに何かあったときのために予備を用意しておく必要もあるでしょう。現状として、パソコンなどの設備の用意は各校が行わなければならないため、設備投資の問題は優先的に解決する必要があります。
3-4.セキュリティの脆弱性
生徒はIT機器や情報などの取り扱いに慣れていない場合が多いため、保存データの保護は大きな課題です。セキュリティのルールは学校によって異なりますし、セキュリティにこだわりすぎるとプログラミング学習において不便が生じる可能性があります。たとえば、USBメモリの禁止、インターネット上からソフトウェアをインストールするのは禁止などです。
学校によっては、USBでデータを保存したり、Wi-Fiを使った通信をしたりするには、学校長や教育委員会などに許可を求めなければいけないこともあります。それは、生徒たちの個人情報などの情報が誤って外部に漏れてしまわないようにするためです。そうすると、許可が通るまで授業が進められないなどの影響が出てしまうことも考えられます。しかし、情報漏洩防止などセキュリティ面で考えると、ゆるくすることも難しく、教師と生徒それぞれがきちんと理解して、データの取り扱いについてのルールを設ける必要があります。
4.プログラミング必修化による受験への影響
プログラミングの必修化は受験にも影響してしまいます。たとえば、プログラミングは「技術」の授業として行われているので成績が内申点に影響するため、受験という意味では技術の成績も重要です。また、2025年には大学の入学共通テストに「情報」の追加が決定しました。中学生の大学受験は少し先になりますが、入試科目として意識したうえで勉強しなければなりません。高校を受験する際に推薦入試となる場合は、プログラミングの作品やコンテストなどの結果が評価される可能性もあります。早い段階でプログラミングに慣れ親しんでおくことは、非常にメリットが大きいといえるでしょう。
5.中学生がプログラミングを積極的に学ぶ価値とは
学校の授業だけではなく、子どもへのプログラミング教育が注目されています。プログラミングはIT化が進む時代のなかでニーズがある技術であり、社会人として働くようになってからも役立つ論理的思考力や創造性を養うことも可能です。また、プログラミングの技術を身につけること、プログラミングを通してITリテラシーを高めることは将来の選択肢を大きく広げるきっかけになります。たとえば、生徒それぞれが作った作品にCCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)のシールを貼り、ほかの人が参考にできるようにした学校もありました。CCライセンスとは、再利用してもよいという著作者の許可のことです。プログラミングを極めれば、将来的に起業、特許の取得などにつながる可能性もあるでしょう。
6.中学生におすすめのプログラミング言語と学習方法
こちらでは、中学校の授業以外でプログラミング学習を進める場合におすすめのプログラミング言語や学習方法を紹介します。
6-1.おすすめの言語

簡単なものからはじめたい場合は、小学校から利用できるScratchなどの無料ツールがおすすめです。ビジュアル言語と呼ばれているタイプで、視覚的な操作ができることから、非常にわかりやすいのが特徴となっています。ブロックに文字が書かれており、それをドラッグ&ドロップするだけなので簡単ですが、複雑なアニメーションやゲームの作成ができる優れものです。自分が作成したゲームを公開して世界中の人に遊んでもらうことができます。また、公開されているゲームで遊び、プログラムを参考にすることも可能です。
本格的に学びたい場合は、大人も使用しているPythonやJavaScriptなどを学ぶのもよいでしょう。ただ、これらのコードは英語が使用されているため、多少の英語力が必要です。Pythonは特に注目されているプログラミング言語で、充実したライブラリがあります。AIの研究にも使用されているため、こちらを中学生の段階から学び始めるのもよいでしょう。英語に触れる機会を増やすことにも役立ちます。
たとえば、プログラミング教室の「プログラミング教育 HALLO」では論理的思考力や問題解決力、pythonのテキストコーディング、将来的に大学入試を受けるための対策、正確で速いタッチタイピングを身につけることができます。タイピング技術は学校で教えるのが難しいとされており、教室で身につけられるのはメリットといえるでしょう。しかも、オリジナル教材のPlaygramを使用してゲーム感覚で楽しみながら前述したスキルを養えるのが魅力です。通常は最寄りのスクールに通って学びますが、オンライン校もあるので状況によって選択できるのがよいところです。
中学生も積極的にプログラミングを学んでみよう
中学校でのプログラミング教育は、IT化がますます進む将来に向けて技術と経験を積むことができます。プログラミングができる人材は需要が高く、積極的に学んでおくと子どもの選択肢が広がります。「プログラミング教育 HALLO」では個別学習塾で実績がある「やる気スイッチグループ」のメソッドを取り入れた個別最適レッスンやオリジナル教材Playgramで楽しみながらレベルアップできます。無料体験も可能なので、気軽にお問い合わせください。
6-3.中学校のプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO
小学生からプログラミング教育が必修化されたなら、中学生から始めると遅くない?と思われるかもしれません。しかし、中学から始めても遅くはありません。むしろ、中学生なら理解力が早く、どんどん新しい知識を吸収できます。プログラミング教育 HALLOは、ゲーム作りやアプリ開発など、身近にある問題を解決するためのプログラミングの基礎からしっかりと学び、身につけていくことができます。少人数制のレッスンで、一人ひとりのペースに合わせて指導を刷るので、初心者でも安心してレッスンを受けていただけます。無料体験レッスンも随時行っていますので、いつでも見学・体験に参加してください。
執筆者:プログラミング教育HALLOコラム編集部