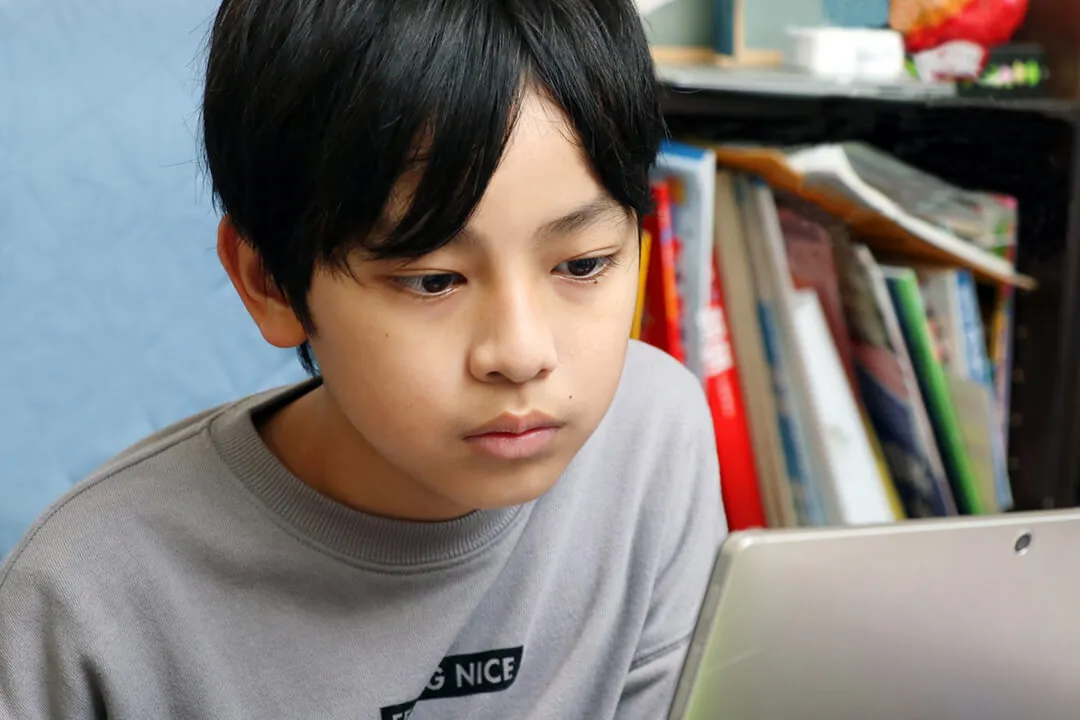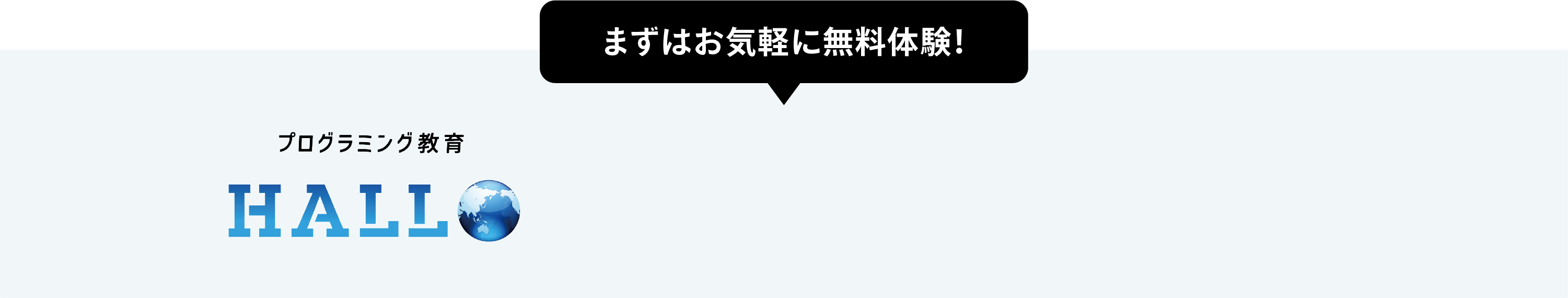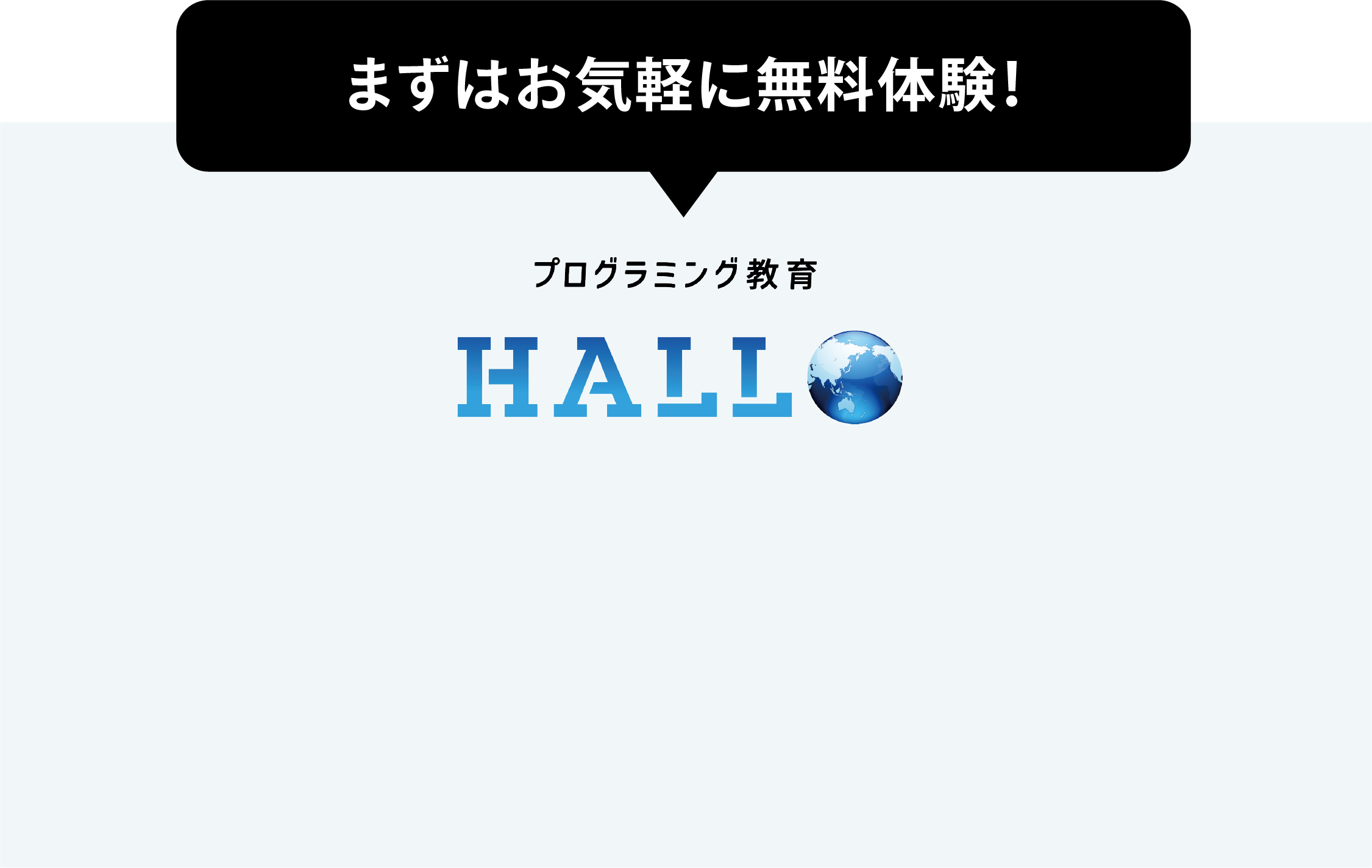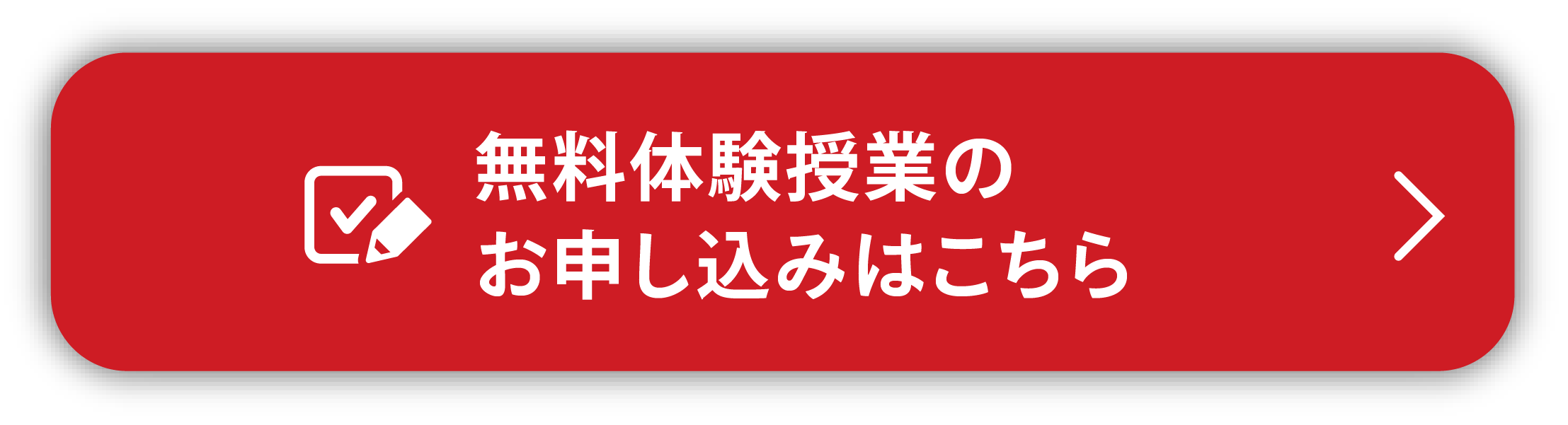子どものプログラミング教育とは?7つのメリットと家庭での注意点を解説
更新日:2025.8.31
公開日:2023.4.7

小学校では2020年からプログラミング教育が必修化されました。子どもたちにとってプログラミング学習は身近になってきましたが、まだ幼いのに必要なのか懐疑的な保護者の方もいるでしょう。新しい分野だからこそ、現状に問題点がないのか心配になるかもしれません。そこで本記事では、まずプログラミング教育のメリットや懸念点を紹介し、それらを踏まえて学校以外で学べる方法について解説します。
この記事の目次
1.プログラミング教育はなぜ導入された?

最初に、プログラミング教育が導入された目的を把握しておきましょう。文部科学省は「小学校プログラミング教育の手引」を公開しており、そこではプログラミング教育のねらいが次の3つに分類されています。「プログラミング的思考を育むこと」「コンピューター等の活用で社会貢献しようとする態度の育成」「各教科等の学びについて確実性を上げること」という趣旨です。ここで示されている「プログラミング的思考」とは、目標達成に向けて論理的に考えながら実行していく力を指します。その過程で必要な事柄をピックアップし、効果的に組み合わせる順番についても検討するのです。
この力はプログラミングに特化したものではありません。どのような職業でも求められる力のため、将来に備えて子どもの頃から伸ばすことが重視されるようになりました。
2.プログラミング教育のメリット

プログラミング教育を受けることには多くのメリットがあります。以下に挙げる7点は、そのなかでも特に魅力的なものです。それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
2-1.ITへの苦手意識を払拭できる
ITという言葉はインターネットやコンピューター、アプリなど、日常にあるさまざまな技術を指します。大人のなかには、仕組みが分からなかったり、使い慣れていなかったりすることが理由でこれらに苦手意識を持つ人も少なくありません。プログラミング教育を通じて子どもがITに自然と触れるようになると、IT技術への抵抗感が生まれにくくなります。身の回りにあるものの仕組みやアプリが動く仕組みを知ることで、興味や関心も育ちやすくなるでしょう。苦手意識を持つ前に、楽しみながら親しめることが、子どもがITを得意分野として育てていく第一歩になります。
2-2.プログラミング的思考が身につく
プログラミング教育では、「プログラミング的思考」を育てることが大きな目的の一つです。これは、コンピューターに正しく動いてもらうために、物ごとを順序立てて考える力のことで、次の5つの要素で成り立っています。一つは問題を細かく分けて考える「分解する力」、次にバラバラの要素をつなげる「組み合わせる力」、そして似ているものをまとめる「抽象化する力」、結果を予想する「シミュレーションする力」、学んだことを別の場面に応用する「一般化する力」です。プログラミングでキャラクターを思い通りに動かそうとするときには、正しい順番で命令を出さなければいけません。プログラミング学習では試行錯誤を繰り返して、少ない命令で効率よく動かす方法を見つけていきます。こうした経験を通して、この5つの要素の力が身につき、日常の問題解決にも役立つようになります。
2-3.問題解決能力が身につく
プログラミングをしても、初めから想定どおりに動くことは多くありません。たいていは何らかの失敗をしており、実行しても途中で停止してしまいます。そこで必要になるのが失敗した原因を探ることです。原因を突き止めたら、どのようにすれば改善できるのか検討します。そのうえでプログラムを修正する一連の作業が、デバッグと呼ばれる処置です。意図した動作を実現できるまで、常にこのスタンスで進めることがプログラミングの基本です。
改善案を導き出したからといって、すぐに成功するとは限りません。それでもプログラムがうまく動作しなければ、再び失敗の原因を検証することになるのです。こうしてデバッグを継続して、トライアンドエラーを繰り返しているうちに、問題解決能力が自然と身についていきます。
2-4.想像力・創造力・表現力が身につく
プログラミングは、何を作るかを考えるところから始まります。完成を目指して試行錯誤を重ねる過程では、想像力や創造力が自然と育ちます。子どもたちは、空想の街やゲームの世界など、自分の頭の中にあるイメージを形にしようと挑戦します。その中で大切になるのが、表現力です。どのようにすれば自分の考えや感じたことを、画面の中でうまく伝えられるのかを考えていきます。たとえば登場するキャラクターの動きや色づかい、音のタイミングなど、細かい部分にも工夫が求められます。自分なりの表現を模索しながら作品を仕上げることで、表現する力が少しずつ磨かれていきます。想像力や創造力、そして表現力を同時に育めるのが、プログラミング教育の魅力のひとつです。
2-5.判断力が身につく
プログラミングを学ぶと、どの方法がうまくいくのかを自分で考えて選ぶ力が育ちます。たとえば、やりたいことを実現するための方法がいくつもある場合、その中から一番よい方法を選ばなくてはなりません。また、うまく動かないときは、どこに原因があるのかを見つけて直す必要もあります。こうした経験をくり返すことで、物ごとをよく見て考え、自分で判断する力が少しずつ身についていきます。自分で考えて決める習慣が、将来さまざまな場面で役に立ちます。
2-6.他教科の理解が進む
小学校では、算数や国語といった既存の教科でも、授業にプログラミングが取り入れられています。たとえば、正多角形をプログラミングで描くという項目が、算数の学習指導要領に盛り込まれているのです。実行させたい命令を正確に伝えなければ、コンピューターは想定どおりに動いてくれません。そのため、正多角形を構成する要素を理解し、各要素の特徴もしっかり把握する必要があります。これらが不十分なままだと、プログラミング以前の問題として、どのような命令が必要なのかイメージすることすら困難です。このように、プログラミングで正しく描くための命令を試行錯誤するにあたり、正多角形の性質が理解できるようになっていきます。
なお、こうして図形に関する知識が増えると、正多角形以外も描けるようになります。まだ学習していない他の図形も、プログラミングなら手書きより簡単に作成が可能です。
2-7.将来の仕事の幅が広がる
ICT化は世界的に進んでおり、プログラミングの知識が活かされるのは、もはやエンジニアの領域だけではありません。すでにさまざまな分野で必要となっており、2030年にはICT人材が40万~80万人ほど足りなくなるという見通しです。つまり、プログラミングが可能な人材のニーズは、将来的に高まっていくと判断できます。また、基本的にプログラミング言語のベースは英語です。よって、英語を習得していれば、プログラミング言語も理解しやすくなります。
両方をマスターした人は、プログラミング環境が整っているところなら、国内外を問わず自由に働けるでしょう。また、たとえ実際にプログラミングをする機会がなくても、プログラミング的思考やITスキルは仕事に欠かせません。したがって、どのような職種に就いても、プログラミング教育の成果を活かせる可能性が高いです。
3.プログラミング教育の懸念点
プログラミング教育には前述のようなメリットがあり、将来的に役立つ考え方を身につけられます。一方、以下に挙げるような懸念点もあるので、それらを事前に知っておくことも大事です。
3-1.手書きする機会が減る
体の末端も神経で脳につながっているため、手や指を動かすと脳が刺激を受けて活性化するといわれています。それによって記憶が定着しやすくなるという恩恵もあるのです。従来の授業では、教師による板書の内容をノートに書き写すスタイルが当たり前でした。この他にも、コンパスや分度器を使って図形を描く等、頻繁に手書きをしていたのが実情です。プログラミング教育の導入によってパソコンやタブレットの使用が増えると、その分だけ手書きの機会が失われてしまいます。それにより、子どもによっては学習効率がダウンする可能性もあるでしょう。
しかし、対策の手段はいくらでもあるので、過剰に心配する必要はありません。たとえば、家の手伝いや家庭学習において、なるべく手先を使わせるように工夫することも有効です。
3-2.他教科の勉強時間が減る
子どもたちが使える時間は限られているため、プログラミングを学んでいると、他教科の勉強量が減るのではないかと懸念されています。この件に関しては誤解をしている人が多いので注意しましょう。小学校のプログラミング教育は、専用の科目として追加されたわけではありません。あくまでも、他教科の授業の一環として取り入れられました。つまり、他教科で教わる内容自体は減っていないということです。
ただし、これまでと指導方法が変わることは確かであり、それを踏まえて教える側は対応が必要です。取り入れ方に規定は設けられていないため、教師や小学校の方針によっては、授業のスピードに影響が出る可能性はあります。スピードが速くなった場合は、授業についていけるように予習や復習でフォローすることが望ましいです。
3-3.集中力が欠如する
子どもにとってパソコンやタブレット、スマートフォンといった端末は、必ずしも勉強のためだけのアイテムという認識ではありません。普段これらの機器を遊びに使っているなら、プログラミング教育の授業の間もそうしたいと思うことは十分にありえます。まだプログラミング教育以外で利用したことがない場合でも、ゲームのような娯楽を楽しめると知れば、学習中にそのような使い方をするかもしれません。いずれにせよ、授業への集中力を欠いてしまうケースがあります。
この懸念点については、教師や保護者が子どもたち一人ひとりに目を配り、声かけを増やすことで対策が可能です。また、子どもが夢中になる題材を使って教えることも効果を期待できます。
3-4.インターネット上でのトラブルが増える
パソコンやタブレットを使用できるようになると、インターネットへの接続も簡単にできるようになります。その機会が増えることで、インターネット特有のさまざまな危険に遭遇する可能性もあるのです。たとえば、怪しいサイトを開くといった定番のトラブルだけでなく、近年増加しているSNS上のいじめに巻き込まれるような懸念もあります。大人でもインターネットの使用中に困った状況に陥ることは珍しくありません。一般的に、子どもは大人よりITリテラシーが不足しているので、さらにリスクが大きくなります。
ICTの教育が進んでいる学校では、貸与する端末にアクセス制限をかける等、すでに対策済みであるケースも多いです。だからといって安心するのではなく、家庭学習では保護者が十分に警戒しなければなりません。
4.プログラミング教育環境の課題
すでに小学校からのプログラミング教育は必修化されましたが、やや先走りといえる状況になっています。なぜなら、多くの現場ではまだ教育環境が万全ではないからです。どのような課題があるのか具体的に見ていきましょう。
4-1.ICT環境が整っていない
ICT環境を整えるには膨大な費用がかかります。現在は生徒全員に1台ずつ端末が行き渡るように整備を進めている段階です。人数分を用意するだけでなく、無線LANの設備や各種ソフトの導入も必要になります。そのため、コストや手間の関係で整備が遅れてしまい、まだICT環境が不十分な学校も少なくありません。また、子どもが端末を使うようになると、インターネット上のトラブルや端末の紛失をはじめとして、さまざまなリスクが想定されます。これらの対策が必須となっており、セキュリティ面をしっかり管理しなければなりません。そのしわ寄せが教師にきており、業務の負担がさらに増えることになりました。
4-2.教師の知識不足
プログラミング教育を担当する教師が、元からプログラミングの知識を持っている場合もあります。しかし、そのケースは多くないため、教師のスキル不足が課題として注目されている状況です。小学校でも教師の指導力不足はいまだ大きな課題となっており、文部科学省の令和5年度「教育の情報化調査」では、ICT活用指導力に関する研修を受講した教員が全国平均で73%にとどまり、都道府県ごとの差も59〜95%と幅があることが示されました。部科学省は指導事例や教材提供に加え、ワークショップなどの実践型研修の実施など、教師の指導力向上に努めています。
5.安全に効率よくプログラミング教育を行うには?
プログラミング教育を順調に進めるには、まず保護者がその必要性をしっかり理解しておくことが大切です。そして、子ども自身が「やってみたい」と思える気持ちも大きなポイントになります。しかし、学校の授業だけではすべてを学ぶのはなかなか難しいのが現実です。子どもがもっと深く学び、力をつけていくためには、家庭でもサポートしていくことが重要です。
5-1.知育玩具やゲームを利用する
知育玩具にはプログラミング的思考を促すような仕組みがあり、組立てる遊びなどによって習熟が早まります。小学生になる前に、自分で考える力を育んでおけば、小学校入学後のプログラミング教育を抵抗なく受けられるでしょう。インターネットを使用できるぐらい成長したら、ビジュアル言語による学習を始めてみましょう。ビジュアル言語とは、命令のコードを書くのではなく、線やブロックを使って視覚的に指示を出すものです。無料で使えるアプリやWebサイトがインターネット上にたくさんあります。
小学校のプログラミング教育で設定されている目的は、あくまでも考え方を学ぶことです。上記のような手段で、実際にプログラミングを体験する機会があると、より興味を持って取り組めるようになります。
5-2.家庭でネットリテラシーの教育を行う
家庭でプログラミングを学ぶときは、インターネットの使い方についても伝えていくことが大切です。特に気をつけたいのが、個人情報の取り扱いです。名前や住所、通っている学校、写真などは、インターネット上で気軽に公開しないように繰り返し伝えましょう。SNSやゲームのチャットなど子どもだけでオンラインでやりとりをする機会も増えているため、どこまで話してよいか、どこからが危ないのかなど、子ども自身が判断できるようにルールを決めておくと安心です。また、なぜ個人情報を守らなければならないのかをわかりやすく説明すると、子どもも納得しやすくなります。インターネットには危険があること、情報を一度出すと取り消せないことを理解することが、安心して学び続けるための第一歩になります。
5-3.可能な限り学習環境を整える
プログラミングの学習を続けやすくするには、できるだけ集中しやすい環境を整えてあげることが大切です。静かで落ち着ける場所に机や椅子を用意し、手元が明るくなるように照明を工夫すると、学びやすくなります。学習に使う道具としては、インターネットにつながるパソコンやタブレットが必要です。多くの教材はオンラインで使うため、通信が安定していると安心です。また、タイピングがしやすいキーボードやマウスもあると操作に慣れやすくなります。子どもが困ったときに声をかけやすいよう、近くで見守ることもポイントです。こうした環境がそろっていると、子どもは安心してプログラミングに取り組めるようになり、自分のペースで学びを深めていけます。
5-4.プログラミング教室に通う
書籍や無料のオンライン学習サイトなど、プログラミング学習ツールは多くありますが、それらを子どもに与えても、家庭ではうまく学べないケースもあるでしょう。保護者にプログラミングの経験や知識がないと、質問されても正確に教えてあげられません。解決できない点が多くなるほど、子どものモチベーションは低下しやすくなります。また、自主的に勉強することが苦手なら、やはりプログラミング学習も進めにくいのが実情です。そんな時に検討していただきたいのがプログラミング教室です。プログラミングの知識を持つスタッフが寄り添って、理解できるまで丁寧に指導することで、子どもの理解力が高まるだけでなく、セキュリティ面に配慮したネット環境が整っているので、個人情報の取り扱いやアクセス制限などにも十分な対策が施されているので安心です。また、友だちと楽しみながら上達できるため、モチベーションの維持も難しくありません。
6.「プログラミング教育 HALLO」で楽しくプログラミングを学ぼう!
どのような職種でもプログラミング的思考は有効なので、プログラミングは将来必ず役に立つ技能といえます。学校教育を通じて、子どもがある程度の興味を持ったなら、プログラミング教室でも習うのがおすすめです。「プログラミング教育 HALLO」の豊富なカリキュラムは、子どもでも挫折せず楽しんで学べるように工夫されています。年長~中学生までが対象で、個別最適化したレッスンを受けられるので、無料体験授業を気軽に申し込んでみてください。
7.まとめ:メリットを理解してプログラミング教育を取り入れよう!
プログラミング教育は変化の激しい社会で子どもたちが主体的に考え、学ぶ力を育てるために導入されました。論理的思考力や創造力の発達など多くのメリットがある一方で、IT環境やネットリスクなどの課題もあります。安全で効果的に学ぶには、保護者のサポートと適切な学習環境が欠かせません。プログラミング教育のメリットを活かしながら、子どもが安心して楽しく学べるよう、保護者も一緒に見守っていきましょう。