小学生の習い事費用、月々いくら?男女・学年別の相場と抑えるコツを解説
更新日:2025.10.7
公開日:2025.8.26
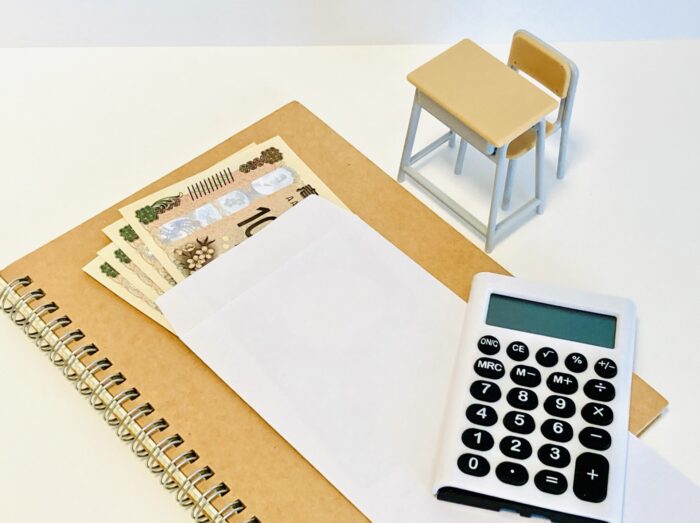
習い事には、水泳や英会話などの定番に加えて、最近ではプログラミングも人気が高まっています。子どもに好きなことを学ばせたい、将来に役立つ経験をさせたいと考える保護者の方も多いでしょう。しかし、その一方で、毎月の費用が家計の大きな負担になることもあります。この記事では、子どもの習い事にかかる費用の相場や、費用を抑えるためのポイント、家計への負担を軽減する方法についてご紹介します。これから子どもに習い事を始めさせたいとお考えの保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.習い事をしている小学生の割合は?

厚生労働省が令和2年に発表した「第9回21世紀出生児縦断調査(令和元年)」によると、小学生で習い事をしている子どもの割合は年々増加しています。平成13年生まれの子どもでは、第7回調査で75.9%だったのが、第9回調査では85.4%となり、約10ポイント上昇しました。さらに、平成22年生まれの子どもでも、第7回調査で76.8%から第9回調査で87.7%へと、およそ11ポイント増加しています。どの世代でも調査を重ねるごとに割合が高まっており、近年では8割以上の小学生が何らかの習い事をしているのが一般的になりつつあります。この背景には、保護者が子どもの学力や体力を伸ばしたいと考えるようになったことや、将来必要となるスキルを早い段階で身につけさせたいという意識が広がっていることが挙げられます。
■習い事をしている小学1年生~小学3年生の割合比較
| 平成13年出生児 | 平成22年出生児 | |
| 第7回調査 | 75.9% | 76.8% |
| 第8回調査 | 81.5% | 84.7% |
| 第9回調査 | 85.4% | 87.7% |
出典:厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況」より作成
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/18/index.html
2.小学生に人気の習い事ランキング

■性別にみた習い事等の種類(複数回答)【平成22年出生児】
| 男児 | 女児 | |||
| 1位 | 水泳 | 40.0% | 音楽(ピアノなど) | 39.6% |
| 2位 | サッカー | 21.1% | 水泳 | 34.2% |
| 3位 | 学習塾 | 20.4% | 通信教育 | 22.0% |
| 4位 | 通信教育 | 19.0% | 習字(硬筆を含む) | 21.9% |
| 5位 | 英会話(他の外国語を含む) | 16.4% | 英会話(他の外国語を含む) | 21.0% |
出典:厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況」より作成
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/18/index.html
厚生労働省の調査によると、小学生に人気の習い事には、男女で異なる傾向が見られます。男の子では「水泳」が40.0%と最も多く、次いで「サッカー」が21.1%、「学習塾」が20.4%となっており、スポーツ系と学習系がバランスよく上位に挙げられています。一方、女の子では「音楽(ピアノなど)」が39.6%で1位、「水泳」が34.2%、「通信教育」が22.0%と続き、芸術や基礎学習への関心の高さがうかがえます。男女ともに水泳が上位に入っていることから、多くの家庭で健康づくりや体力向上を重視して水泳を選んでいると考えられます。
関連リンク:https://www.hallo.jp/column/post-802/
2-1.小学生男子に人気の習い事
小学生の男の子に人気の習い事で最も多いのは水泳で、40%が習っています。水泳は全身を使う運動なので体力がつきやすく、水に慣れることで安心して泳げるようになる点も人気の理由です。次いで2位はサッカーで21.1%です。仲間とボールを追いかけるなかで協調性やチームワークが身につくことが大きな魅力です。3位は学習塾で、20.4%の子どもが通っています。学習塾では学力の基礎を身につけ、受験対策を目的に通う子が多い傾向があります。このほか、通信教育や英会話も人気があります。運動系から学習系まで、さまざまな分野の習い事が男の子たちの可能性を広げています。
2-2.小学生女子に人気の習い事
小学生の女の子に人気の習い事で最も多いのは音楽で、特にピアノなどが39.6%を占めています。楽器の演奏を通じて表現力や集中力が養われることが魅力です。次いで人気なのは水泳で、34.2%です。水泳は体力づくりに役立つだけでなく、自信を持って泳げるようになるため、幅広く選ばれています。3位は通信教育で22.0%です。自宅で自分のペースで学べる利便性が支持されています。4位は習字で21.9%となっており、美しい字を書く力や落ち着いて取り組む姿勢が身につきます。5位は英会話で21.0%です。英会話は国際的な視野を広げる学びとして人気が高まっています。このように、女の子の習い事は芸術、学習、スポーツと多彩な分野に広がっています。
3.小学生の習い事にかかる費用はどのくらい?

小学生の習い事にかかる費用は、性別や学年、通う学校の種類によって大きく変わります。ここではその相場を具体的に見ていきます。
3-1.男女別の月額相場
■小学生男女別の学校外活動費(円)
| 公立学校 | 私立学校 | |||
| 年間 | 月額(約) | 年間 | 月額(約) | |
| 男児 | 224,218 | 18,700 | 690,110 | 57,500 |
| 女児 | 207,587 | 17,300 | 744,278 | 64,500 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」より作成
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf
この調査によると、小学生の学校外活動費には男女でわずかな差が見られます。公立学校の場合、男児の月額活動費は約18,700円、女児は約17,300円で、男児のほうがやや多い傾向です。一方、私立学校では女児が月額約64,500円、男児は約57,500円となっており、女児のほうが高くなっています。公立・私立のいずれの場合も、男女によって活動内容や選ぶ習い事が異なることから、月々に必要な費用にも違いが生じています。特に私立では男女間の費用差が大きくなっています。これは、家庭の教育方針や子どもの興味・関心が、月額費用に影響を与えているためだと考えられます。
3-2.学年別の月額相場
■学校活動費の支出状況(学年別)(万円)
| 公立学校 | 私立学校 | |||||
| 補助学習費 | その他の学校活動費 | 合計 | 補助学習費 | その他の学校活動費 | 合計 | |
| 1年 | 7.7 | 12.2 | 19.9 | 28.2 | 38.4 | 66.6 |
| 2年 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 24.7 | 38.4 | 63.1 |
| 3年 | 8.0 | 12.3 | 20.3 | 28.5 | 35.4 | 69.8 |
| 4年 | 8.0 | 12.9 | 20.9 | 35.6 | 34.2 | 69.8 |
| 5年 | 11.8 | 12.5 | 24.3 | 50.0 | 31.2 | 81.2 |
| 6年 | 14.1 | 12.4 | 26.5 | 58.9 | 29.2 | 88.1 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」より作成
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf
この調査結果から、学年が上がるにつれて学校活動費の負担が増加することが分かります。月額で見ると、公立小学校では1年生で約16,000円、6年生では約22,000円となり、特に高学年になると補助学習費が大きく増えます。私立小学校の場合は、1年生で約55,000円、6年生では約73,000円と、どの学年でも公立よりかなり高額です。学年が進むにつれて学習内容や活動が多様化し、塾やクラブ活動などへの支出が増えることが、費用増加の主な要因と考えられます。特に私立では、学年が上がるほど月々の教育費の負担がさらに大きくなる傾向が見られます。
3-3.公立・私立別の月額相場
■公立・私立小学校における学校外活動費に占める「補助学習費」「その他の学校外活動費」の内訳(万円)
| 学校種別 | 補助学習費 | 体験活動・ 地域活動 |
芸術文化活動 | スポーツ・ レクリエーション活動 |
国際交流体験活動 | 教養・その他 | 合計 |
| 公立小学校 | 9.3 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 3.1 | 21.6 |
| 私立小学校 | 37.5 | 2.7 | 2.5 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 72 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」より作成
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf
公立小学校と私立小学校では、学校外活動費に大きな差があります。公立小学校の学校外活動費は1か月あたり約18,000円ですが、私立小学校は約60,000円と、私立の方が大幅に高くなっています。特に「補助学習費」では、公立が月額約7,750円、私立が約31,250円と、4倍以上の差があります。「運動系の活動」や「国際交流体験活動」なども、私立の方が公立より高額です。私立小学校では、多彩で質の高い活動や学習が提供されているため、保護者は毎月より多くの経済的負担を負う傾向があります。
関連リンク:https://www.hallo.jp/column/post-923/
4.小学生の習い事費用を抑えるためのポイント

子どものやる気を応援したいと思う一方で、家計への負担が気になるのも現実です。しかし、習い事の費用は、ちょっとした工夫で抑えることができます。例えば、自治体の助成金制度や入会時のキャンペーン、各種割引を活用する方法があります。また、通う頻度を見直したり、高価な道具を中古で揃えたりするのも効果的です。これからご紹介するポイントを参考に、無理なく長く続けられる習い事プランを考えてみましょう。
4-1.自治体の助成金制度を活用する
お住まいの自治体によっては、子どもの習い事費用の一部を助成してくれる制度があります。「子育て支援クーポン」や「放課後活動への補助」、「塾代助成」などの名称で、子育て世帯の経済的負担を軽くするための取り組みがおこなわれている自治体があります。
まずは自治体のウェブサイトで「子育て支援 助成金 習い事」などのキーワードで検索してみましょう。見つからない場合は、役所の子育て支援課などに直接問い合わせてみるのも方法です。
4-2.キャンペーンや割引を利用する
多くの習い事教室では、入会者を増やすためにお得な割引制度を用意しています。特に、春や秋の入会シーズンには「入会金無料」や「初月半額」といった期間限定のキャンペーンが実施されていることも多いので、始める時期を調整するのもいでしょう。
また、継続的に利用できる割引として注目したいのが兄弟割や姉妹割です。兄弟や姉妹で同じ教室に通うと、2人目以降の月謝が割引になる制度で、複数の子どもがいる家庭にとっては大きなメリットになります。入会を決める前に、公式サイトをチェックしたり直接問い合わせたりして、利用できる割引がないか忘れずに確認しましょう。
4-3.習い事に通う頻度を調整する
習い事を長く続けていくためには、費用だけでなく、お子さまやご家庭にとって無理のない通学ペースを見つけることも大切です。多忙な日常の中で、習い事を詰め込みすぎると、子どもにとって負担になってしまうことも。
週に1回のような適度な頻度であれば、学校や他の活動とのバランスも取りやすく、習い事を楽しみながら続けることができます。また、お子さまの興味や習熟度に応じて、取り組み方を柔軟に調整すれば、学びの質もさらに高まります。
続けやすい頻度と余裕のあるスケジュールが、結果的に「学ぶ楽しさ」につながる大きなポイントです。
4-4.事前にかかる費用の総額を計算する
習い事に必要なお金は月謝だけではありません。入会時には入会金や年会費がかかり、教材費やユニフォーム代などが必要になることもあります。さらに発表会や試合がある場合参加費や衣装代、遠征にともなう交通費や宿泊費が加わります。こうした出費を事前に把握していないと予想外の負担に慌てることになりかねません。体験レッスンの際などに年間で必要な費用を確認し、計画的に準備しておくことが大切です。
4-5.楽器やスポーツ用品は中古品も検討する
音楽や野球などの習い事では、高価な楽器や用具の準備が負担になることも。また、子どもの体はすぐに大きくなるため、ユニフォームや靴がすぐにサイズアウトしてしまいがちです。そこでおすすめなのが中古品の活用です。フリマアプリやリサイクルショップを利用したり、先輩からお下がりを譲ってもらったりすれば、初期費用を大きく抑えられます。
まずは中古で気軽に始めてみて、子どもが続けていきたいという気持ちが固まったら、そのときに本人に合った新品の購入を検討してみてはいかがでしょうか。
5.子どもの教育資金を計画的に貯める方法

子どもの将来のために、教育資金を計画的に準備したいと考える保護者は多いと思います。教育資金を準備する方法には、いくつかの選択肢があります。ここでは代表的な方法を紹介しますので、それぞれの特徴やメリットを理解し、ご家庭のライフプランやお金に対する考え方に合った最適な方法を選ぶことが大切です。
5-1.児童手当を使わずに貯める
国から支給される児童手当は、子どもの教育資金を準備するうえでとても頼りになる存在です。0歳から中学校を卒業するまでの間、児童手当をすべて貯めると、合計で約200万円という大きな金額になります。生活費とは別の銀行口座で管理すれば、気づかないうちにお金が貯まっていきます。この方法は、特別な手続きやリスクもなく、誰でもすぐに始められる手軽で確実な方法の一つです。まずは、自動的に貯金する仕組みを作ることから始めてみてはいかがでしょうか。
5-1.財形貯蓄制度を利用する
お勤め先に財形貯蓄制度がある場合は、ぜひ利用を検討してみてください。この制度は、毎月の給与からあらかじめ決めた金額が自動的に天引きされて積み立てられる仕組みです。そのため、自分で銀行にお金を移す手間がかからず、意志の強さに関係なく確実に貯金できる点が大きなメリットです。ご自身の勤務先にこの制度があるかどうか、また教育資金など目的を問わず使える一般財形貯蓄が用意されているかを確認してみましょう。
5-3.新NISAで貯蓄する
教育資金を効率よく増やしたいと考えている場合は、新NISAを活用する方法もあります。特に「つみたて投資枠」を使えば、毎月少しずつ投資信託などに積み立てていくことが可能です。ただし、元本が保証されているわけではないため、運用がうまくいかず資産が減るリスクもあります。そのため、長い目で見てリスクを理解しながら、コツコツと資産を増やしたい家庭に向いている選択肢といえるでしょう。
5-4.学資保険を活用する
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための金融商品です。その最大のメリットは「保障機能」にあります。契約者である親に万一の事態が起き、保険料の支払いが困難になった場合でも、その後の支払いは全額免除されます。そして、子どもの進学時期に合わせて、祝い金や満期保険金は契約通りに満額受け取ることができるのです。着実に貯蓄しながら不測の事態にも備えられるこの仕組みが、多くのご家庭にとって大きな安心感につながっています。
6.これからの社会で必須なプログラミング学習も習い事の選択肢に

小学生のうちからプログラミング教室に通うことには、大きなメリットがあります。専門の教室なら、学校の授業よりも深く体系的に学べるうえ、最新の技術や教材に触れながら、同じ興味を持つ仲間と切磋琢磨できるからです。
なぜなら、AIなどのデジタル技術が社会に浸透した今、プログラミングを通じて養われる「論理的思考力」や「問題解決能力」は、将来どんな道に進んでも役立つ必須スキルとなっているからです。楽しみながら学ぶ経験が、子どもたちの未来の選択肢を広げ、デジタル社会を生き抜くためのたしかな土台を築きます。
7.小学生のプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOは、年長から中学生までを対象とした本格的なプログラミング教室です。初心者でも安心できるように、イラストやビジュアルを取り入れた教材「Playgram」を採用しており、ゲームを楽しむような感覚で学べます。入門レベルのビジュアルプログラミングから始めて、ブロック型やPythonを使った本格的なコーディングまで、無理なくステップアップできるカリキュラムが整っているのも特長です。
授業は週1回の教室レッスンまたはオンラインに加え、自宅学習や月1回の発表会も実施されます。自分のペースで進められるため、初めて学ぶ子どもから経験者まで幅広く対応可能です。発表の場を通して表現力や自信が育ち、将来の進路や学びにもつながります。
さらに、一人ひとりに合わせた個別サポートも充実。理解度に応じた最適なレッスンや学習管理システムを活用できるので、安心して継続できます。簡単なゲームづくりからAIやセキュリティといった先端分野まで学べるため、好奇心を伸ばしながら論理的思考力や問題解決力、表現力もバランスよく養える教室です。
8.まとめ
小学生の習い事は、子どもの可能性を広げる大切なチャンスです。習い事には費用や時間の負担がかかりますが、通う目的や子どもの興味をしっかり考えれば、無理なく続けられる環境を作ることができます。最近では、プログラミングのように将来の学びにつながる習い事も増えており、選べる内容はどんどん多様になっています。子どもが“自分からやりたい”という気持ちを持ち、主体的に学び・成長できる場所を見つけることが、習い事を長く続けるための一番大切なポイントです。




