プログラミングが面白いと感じるのはどんな時?楽しく学ぶ方法も解説
更新日:2025.8.29
公開日:2025.7.19

プログラミングは、自由な発想をもとに、自分の考えやアイデアを形にできることが大きな魅力です。
試行錯誤を重ねながら思い通りに動かせるようになることで、達成感や楽しさを味わえるようになります。たとえ複雑な作品をつくらなくても、思ったとおり動いたり、順序立てた思考で問題を解決できたりする体験そのものが、子どもたちの大きな自信につながります。
また、楽しみながら学ぶことで理解が深まり、学習が継続しやすくなるのも特徴です。今回は、プログラミングが面白いと感じる瞬間や子どもに合った学習方法について解説していきます。年齢や興味に応じた言語の選び方や、おすすめの学習サービスについても紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
コーディング言語とは?

コーディング言語とは、コンピューターに指示を出すための言葉です。人間の考えをコンピューターが理解できる形に変える役割をもち、文字や記号を使って動作や処理の流れを示していきます。特定の命令を並べていくことで、ゲームやアプリ、ウェブサイトなどを動かす仕組みを作れるようになります。コンピューターは人間の言葉をそのまま理解できないため、こうした言語が必要とされているのです。
コーディング言語とプログラミング言語の違い
プログラミング言語とは、コンピューターにしてほしいことを伝えるための特別な言葉で、アプリやゲーム、ウェブサイトの開発などに広く使われています。一方、コーディング言語は、命令を書くときに使う言語という意味で用いられることが多く、時にはプログラミング言語の言い換えのように扱われる場合もあります。ただし、プログラミングは全体の仕組みを考えて作る作業まで含みますが、コーディングは実際に命令を打ち込む作業のことを指します。このように、意味は近いですが、少しだけ使い方に違いがあります。
コーディング言語の主な特徴
コーディング言語には様々な特徴があります。コンピューターへの命令を単語や記号で分かりやすく書けるように作られており、決められた順番やルールに従って命令を書くと、思った通りにコンピューターが動いてくれます。さらに、同じ作業を何度も繰り返したり、条件によって動きを変えたりといった便利な機能も用意されています。コーディング言語は種類が豊富で、目的や学ぶ人の年齢によって自分に合ったものを選べます。難しそうに感じるかもしれませんが、楽しく学べるような工夫がされている言語もたくさんあります。
子ども向けのコーディング言語は何歳から始めるべき?

子ども向けのコーディング学習は、早ければ小学校に入る前から始めることができます。近年ではパソコンやタブレットの操作に慣れている子どもが多く、遊びながら自然に学べる教材も増えています。特にビジュアル型と呼ばれる、文字ではなくブロックを組み合わせて動きを作るタイプの学習ツールは、未就学児でも無理なく取り組めるよう年齢に合わせて内容が工夫されており、楽しみながら考える力や表現力が育まれていきます。最初はゲーム感覚で始められるものから取り入れると、子どもも前向きに学びやすくなります。
なぜ、今子どもにプログラミングが必要なのか?
今の社会では、身のまわりにある多くのものがコンピューターで動いています。スマートフォンや家電、ゲームやアプリもすべてプログラムによって成り立っています。こうした仕組みを理解する力は、これからの時代に欠かせません。プログラミングを通して、子どもは自分のアイデアを形にする方法を学び、うまくいかないときにどう直すかを考える習慣も身につきます。このような経験は、将来どのような仕事に進んでも役立ちます。さらに、小学校でも授業に取り入れられているため、遊びながら自然に慣れていくことが大切です。
おすすめの子ども向けコーディング言語6選【~小学生まで】
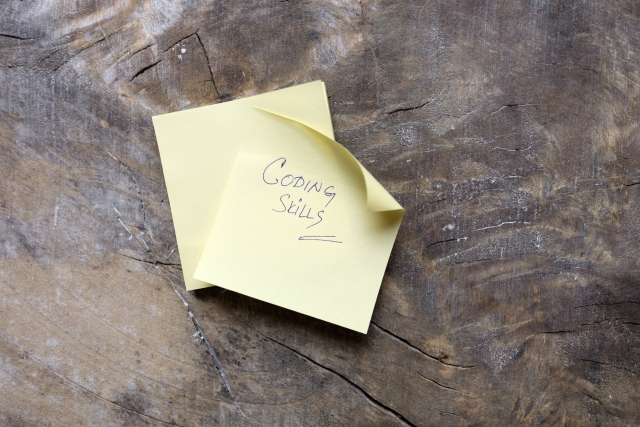
小学生までの子どもが楽しみながら学べるコーディング言語は多く存在します。ゲーム感覚で遊べるものから、キャラクターを動かしてプログラミングの考え方を身につけるものまで、その特徴はさまざまです。ここでは、特に人気が高く、初心者でも始めやすいコーディング言語を6つ厳選して紹介します。
①Scratch(スクラッチ)
Scratchは、ブロックを組み合わせるだけでプログラムを作れる、初心者向けのコーディング言語です。パズルのように命令をつなげて、キャラクターを動かしたり、音を鳴らしたりと、自由な作品を作ることができます。対象は主に8歳以上とされ、小学生のプログラミング教育でもよく使われています。無料で利用でき、インターネットがあればすぐに始められる手軽さも魅力です。遊びながら論理的思考を育てられることから、子どもの初めてのプログラミングに適しています。
公式サイト:https://scratch.mit.edu/
②Scratch Jr(スクラッチジュニア)
Scratch Jrは、未就学児や小学校低学年を対象にしています。文字を使わず、アイコンやブロックをタップするだけでキャラクターが動き、自然とプログラミングの基本に触れられます。アプリを使って操作する形式で、タブレットがあれば誰でも簡単に始められます。操作もシンプルなので、小さな子どもでも一人で扱えるのが特長です。無料でダウンロードでき、親子で一緒に楽しめる学習環境が整っています。
公式サイト:https://www.scratchjr.org/
③Viscuit(ビスケット)
Viscuitは、日本で開発されたビジュアル型のコーディングツールで、主に幼児から小学校低学年を対象にしています。絵を描いて、その絵がどのように動くかを「メガネ」という仕組みで設定するのが特徴です。文字や数式を使わずに、直感的に操作できるため、初めてのプログラミング体験にぴったりです。自分の描いたイラストが動き出す体験は、子どもの創造力を刺激します。Web版とアプリ版があり、基本的に無料で利用できます。家庭でも保育園や学校でも導入されている実績があります。
公式サイト:https://www.viscuit.com/
④Code.org(コードドットオーグ)
Code.orgは、世界中の子どもたちがプログラミングを学べるように設計されたオンライン学習プラットフォームです。対象年齢は幅広く、初心者から上級者まで対応しています。子ども向けにはキャラクターが登場するゲーム形式の教材が用意されており、楽しみながら学習できます。プログラミングの仕組みや考え方を段階的に学べるので、学校教育の補助教材としても活用されています。インターネット環境があれば無料で使えるのも大きなメリットです。
公式サイト:https://code.org/
⑤MakeCode(メイクコード)
MakeCodeは、マイクロソフトが開発したオンライン型のコーディング学習サービスです。ブロックをドラッグして操作するスタイルから始められ、慣れてくるとJavaScriptといった本格的な言語にも挑戦できるのが特徴です。対象は小学校中学年以上が目安とされ、ゲーム作成やロボットとの連携といった実践的な学びも用意されています。体験を通して自然に仕組みを理解できるため、楽しさと学びが両立しやすい環境です。ブラウザ上ですべて無料で利用できます。
公式サイト:https://makecode.microbit.org/
⑥CodeMonkey(コードモンキー)
CodeMonkeyは、物語を進めながら本格的なプログラミングの基礎を学べるオンライン教材です。ゲームの中でおさるのキャラクターを動かしながら、命令文を入力して問題を解いていく構成になっています。タイピングを使ってコードを書くスタイルなので、小学3~4年生以上の子どもに向いています。基本的な学習は一部無料で提供されており、有料プランではより多くの内容を学ぶことができます。論理的思考を育てる教材として、教育機関でも広く活用されています。
公式サイト:https://www.codemonkey.com/
子ども向けコーディング言語の選び方

コーディング言語には年齢やスキルに合わせたさまざまな種類があります。対象年齢や学ぶ目的によって適した言語は異なるので、学びやすさや興味があるかどうかなどを考えて、子どもに合ったコーディング言語を選びましょう。
対象年齢に適した言語を選ぶ
コーディング言語には、それぞれ適した年齢があります。未就学児や小学1~2年生の子どもには、絵やブロックを使って操作できる簡単なものが向いています。一方で、小学校中学年以降になると、文字を使った入力にも徐々に慣れていけるようになります。年齢に合っていない言語を使うと、内容が難しすぎて途中でつまずいてしまうこともあるため、無理のない範囲で始められるものを選ぶことが大切です。
ビジュアル型orテキスト型で決める
コーディング言語には、ブロックを組み立てるように操作するビジュアル型と、キーボードでコードを入力するテキスト型があります。ビジュアル型は直感的に理解しやすく、初心者や小さな子どもに向いています。テキスト型は、より本格的な内容に踏み込めるため、少し慣れてきた中級者以上におすすめされます。まずはビジュアル型から始め、成長に合わせてテキスト型に移行する流れも自然です。
学ぶ目的に合わせて決める
コーディングを学ぶ目的によって、選ぶ言語は変わってきます。遊びながら基礎を身につけたい場合は、ゲーム感覚で取り組めるものが適しています。一方で、論理的思考や将来的なスキル習得を重視するなら、ステップアップできる教材がそろった言語を選ぶと良いでしょう。どんな力を育てたいのかを明確にすると、子どもに合った言語を見つけやすくなります。
興味に合わせて続けられるものを選ぶ
コーディングを長く続けるには、子どもが興味を持てる内容かどうかが大きなポイントです。好きなキャラクターが出てきたり、自分で作った作品を公開できる仕組みがあったりすると、もっとやってみたいという気持ちが高まります。内容に関心を持てないと、やる気が続かなくなることもあるため、無理に取り組ませるのではなく、楽しみながら学べる工夫があるかどうかを基準に選ぶとよいでしょう。
サポート体制が整った言語を選ぶ
初めてコーディングを学ぶ子どもにとっては、サポート体制の有無も大きな安心材料です。わからないことが出てきたときに、ガイドやヘルプ機能が用意されていると、理解がスムーズに進みます。また、保護者や教育関係者向けの説明資料があることで、周囲の大人も学習を支援しやすくなります。
安心して取り組める環境があることは、学ぶ意欲を高めるきっかけにつながります。
子どもが続けやすいコーディング言語の学び方とは?
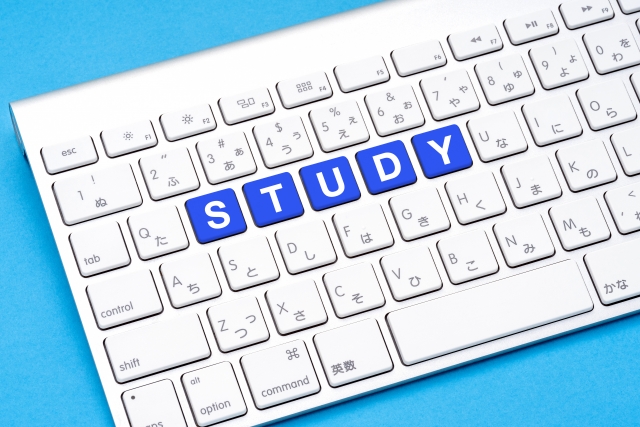
教室での指導やオンラインの教材、アプリや書籍など、コーディング言語を学ぶ方法はさまざまにあります。それぞれに特徴があるため、子どもの性格や学ぶ目的に合わせて使い分けることが、継続につながるポイントです。
プログラミング教室を利用する
教室に通う方法は、講師のサポートを受けながら学べるため、理解を深めやすいのが特徴です。個別に指導してもらえるスタイルや、同年代の仲間と学ぶスタイルがあり、集中して取り組みやすくなります。わからない部分をすぐに質問できる環境は、子どもにとって安心感があります。定期的な通学によって学習習慣が身につきやすく、自然と続ける力が育まれていきます。
学習サイトやアプリを活用する
自宅でプログラミングを学ぶなら、学習サイトやアプリが便利です。キャラクターが案内してくれたり、ゲーム感覚で進められたりと、子どもが飽きずに取り組める工夫がたくさんあります。好きな時間に少しずつ進められるので、忙しい日常の中でも無理なく続けられるのも利点です。また、自分に合ったレベルから始めて、少しずつステップアップしていけるので安心です。
書籍を使って学ぶ
書籍による学習は、基礎から順を追って学べるのが特徴です。図やイラストが多く使われている本なら、子どもでも読み進めやすいでしょう。親子で一緒に取り組める構成の本もあり、家庭での学びをサポートしやすくなっています。本を使って一つずつ丁寧に理解していくことで、しっかりとした知識が身につきやすくなります。自分の手で確認しながら進められる点も安心です。
子どものプログラミング教育なら、プログラミング教育 HALLO

子どもにプログラミング学習は難しくないのか、と不安になる保護者も多いでしょう。そんな保護者の想いに応えるのが、子どもたちのために特別に作られたプログラミング学習を実践しているプログラミング教育 HALLOです。子ども一人ひとりの「やってみたい!」という気持ちを大切に、無理なく、そして楽しく学べる環境を用意しています。
プログラミング教育 HALLOの大きな特長は、コーチが一人ひとりに寄り添ってくれる「個別指導スタイル」であること。まるで家庭教師のように、子どもの理解度や興味のアンテナがどこに向いているのかをしっかりと見守りながら、その子にぴったりのペースで学習を進めていきます。
プログラミング教育 HALLOでは、ただ知識を詰め込むのではなく、ゲームで遊ぶようなワクワク感や、何かを自分の手で創り上げる達成感を大切にしています。この「楽しさ」と「確かな学び」の絶妙なバランスこそ、プログラミング教育 HALLOが何よりもこだわっている点です。また、身につくのは、プログラミングの技術だけではありません。論理的思考力や課題解決型の思考力、ITリテラシー(情報技術)を身につけていくことも狙いにしています。
まとめ
コーディング言語はコンピューターに指示を伝える大切なツールで、子どもならScratchやViscuitなどビジュアル型のわかりやすく楽しい言語から始めるのが最適です。年齢や興味に合わせて言語を選び、無理なく続けられる環境を作ることが重要となります。プログラミング教育 HALLOでは、子ども一人ひとりに合わせた個別指導と、ゲーム感覚で楽しく学べる工夫で学習をサポートしています。こうした経験が、論理的な考え方や創造力を育て、将来に役立つ力となっていきます。




