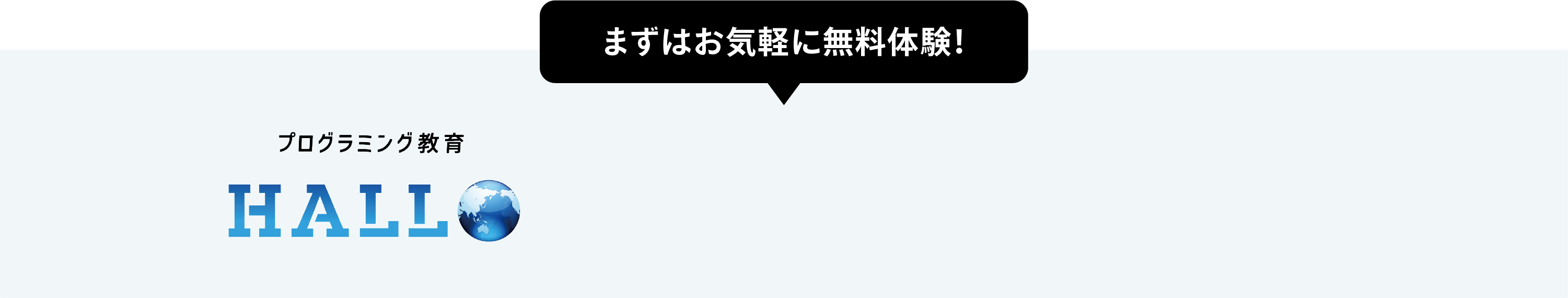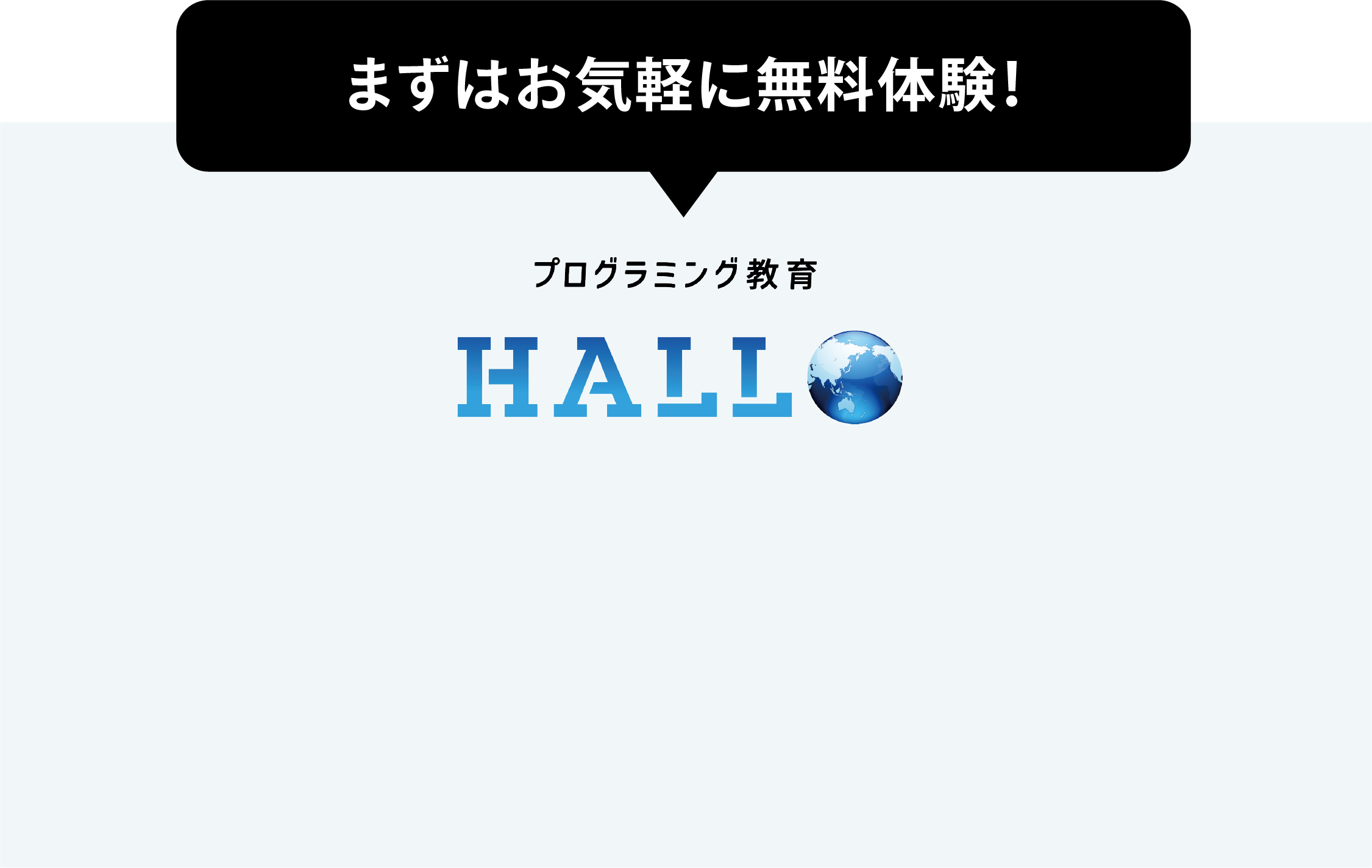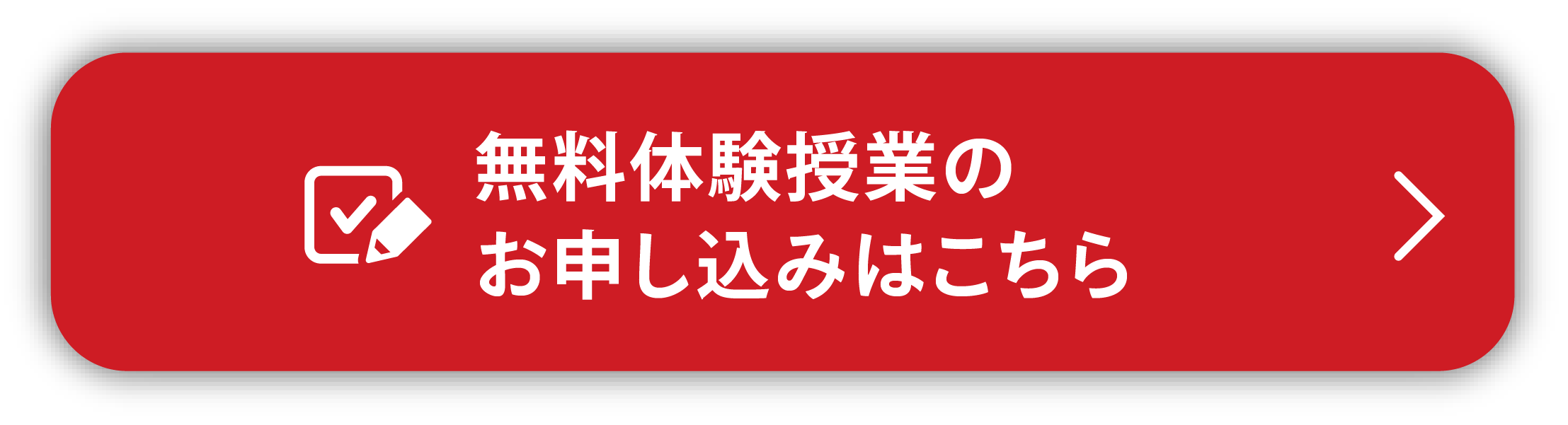エリクソンの発達段階理論とは?8つの段階とそれぞれの課題について解説
公開日:2025.4.21

エリクソンの発達段階理論は、人が生涯を通じて経験する8つの成長段階を説明するものです。
たとえば、赤ちゃんは親の愛情を通じて「世界は安心できる」と感じる一方、かまってもらえないと不安を抱きやすくなります。
小学生になると、成功体験を積むことが重要になってきますが、失敗をどう受け止めるかも大切です。この時期は大人が努力を認め、励ますことで自信が育まれます。
この理論を知ると、子どもの気持ちを理解しやすくなり、接し方を変える一助となるでしょう。理論通りには進まなくても、「今、この子はこういう時期なんだ」と意識するだけで子どもの成長を見守りやすくなります。
今回は、エリクソンの発達段階理論について詳しく解説していきます。
エリクソンの発達段階理論とは?

エリクソンの発達段階理論は、人の成長を8つの段階に分け、各段階で乗り越えるべき課題があるとする考え方です。
たとえば、赤ちゃんは親の愛情を通じて「基本的信頼」を育み、学童期には努力を重ねることで「自信」をつけます。
発達には個人差がありますが、もしもこの時期に失敗ばかりを指摘されてしまうと、自信を失いやすくなります。
「今、この子はこういう時期だから」と理解することで、適切なサポートがしやすくなります。
エリク・H・エリクソンの背景
エリク・H・エリクソンは1902年にドイツで生まれましたが、幼少期にはアイデンティティーの問題に悩んだそうです。なぜなら、父親が早くに家を去り、母親がユダヤ系の家庭に再婚したため、自身のルーツに戸惑ったのです。
この経験が、後の「アイデンティティー」の研究につながりました。
若い頃は芸術に関心があり、美術学校に通っていたそうですが、ウィーンでアンナ・フロイトと出会ったことをきっかけに心理学の道へ進みます。
その後アメリカに移住し、ハーバード大学などで教えながら、発達心理学の研究を深めました。特に「幼少期と社会」では、人の成長が社会とどのように関わるかを説いており、今も教育やカウンセリングに影響を与えています。
エリクソンの8つの発達段階
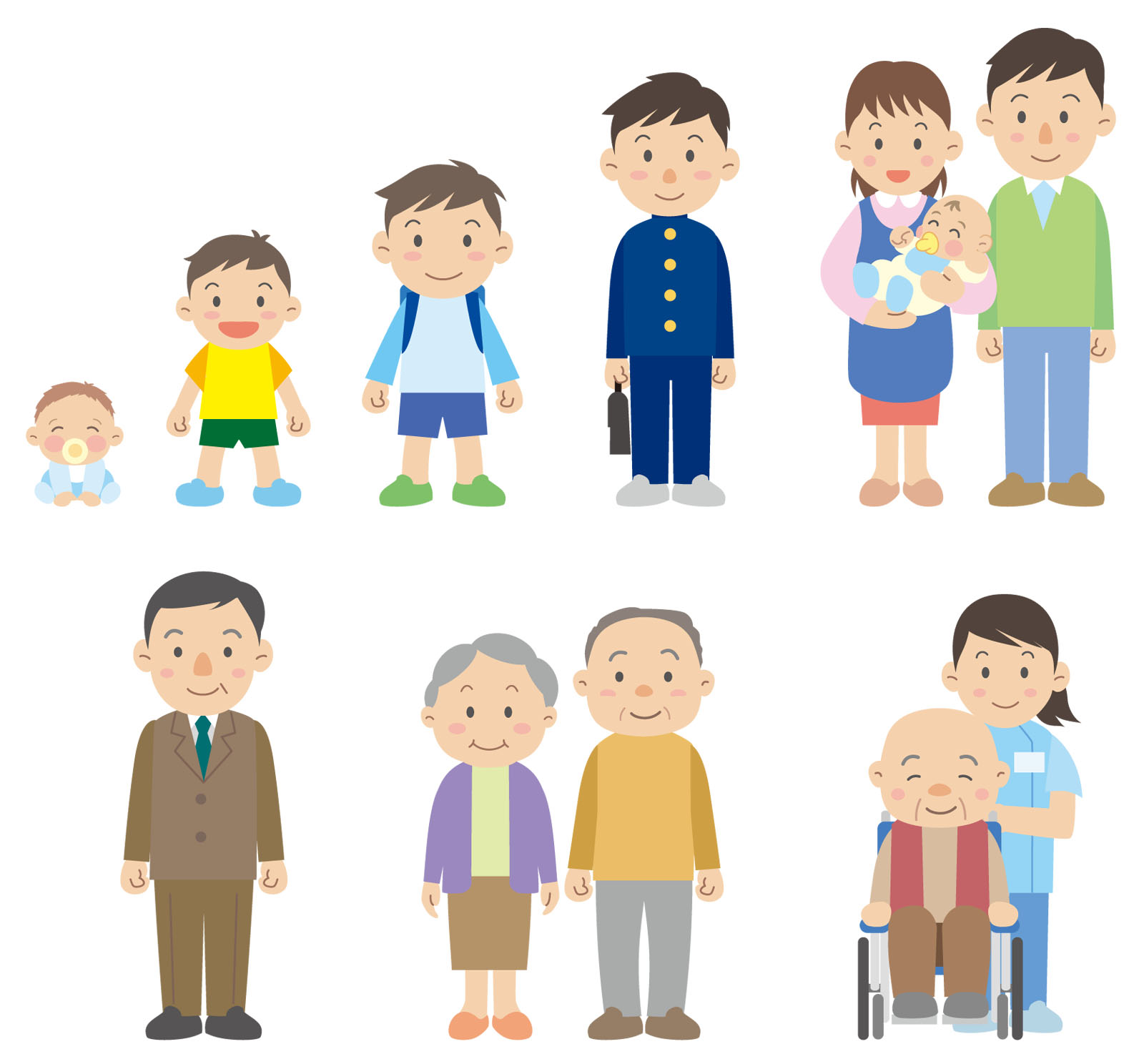
エリクソンの発達段階理論は、人間の一生を8つの段階に分け、それぞれの段階で特有の心理社会的課題や成長のテーマが存在するとしています。これにより、個々人がどのように成長し、人生の中でどのような問題に直面するかを理解する手助けとなります。以下に、エリクソンの提唱する8つの発達段階をまとめた表を示します。
■ 乳児期 (0-1歳半)
・発達課題vs.心理社会的危機:基本的信頼 vs. 不信
・成功の結果:希望
■ 幼児期前期 (1半-3歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:自律性 vs. 恥・疑惑
・成功の結果:意志
■ 幼児期後期 (3-6歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:自主性 vs. 罪悪感
・成功の結果:目的
■ 学童期 (6-13歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:勤勉性 vs. 劣等感
・成功の結果:有能感
■ 青年期 (13-22歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:アイデンティティーの確立 vs. 役割の混乱
・成功の結果:忠誠
■ 成人期(22-40歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:親密性 vs. 孤独
・成功の結果:愛
■ 壮年期 (40-65歳)
・発達課題vs.心理社会的危機:生産性 vs. 停滞
・成功の結果:世話
■ 老年期 (65歳以上)
・発達課題vs.心理社会的危機:自我の統合 vs. 絶望
・成功の結果:知恵
参考:https://www.stemon.net/blog/erikson/
①乳児期(出生から1歳半)
幼児期(出生から1歳半)は、赤ちゃんが「この世界は安心できる場所なのか?」を学ぶ大切な時期です。エリクソンの発達段階理論では、「基本的信頼 vs. 不信」と呼ばれ、この時期に信頼感が育つかどうかが、その後の人間関係にも影響を与えるとされています。
たとえば、赤ちゃんが泣いたとき、すぐに親が抱きしめてあやすと、「泣いたら誰かが来てくれる」「自分は大切にされている」と感じ、安心して世界を受け入れるようになります。わが子をあやしたときに、泣き止んで安心したような顔を見せるのを見た経験がある人は多いことでしょう。逆に、放置されてしまうと、「泣いても誰も助けてくれない」と思い、不安を抱えやすくなるといわれています。
もちろん、すべての瞬間に完璧な対応をするのは難しいですが、大切なのは「一貫性」です。いつもとはいかなくても、赤ちゃんが「基本的に自分は愛されている」と十分に感じられるように接しましょう。忙しい日々の中でも、安心感と信頼感が育まれるよう、少しずつ意識して接することで、信頼感のある関係が築かれていきます。
②幼児期前期
幼児期初期とは、1歳から3歳の間を指し、この段階では「自律性 vs. 恥・疑惑」が主要な課題です。この時期の子どもは、自分で物事をやりとげる能力を発達させます。
たとえば、自分で食事をしたり、トイレを使用したり、着替えをしたりする活動を通じて、自律性が育まれます。
具体的な行動例としては、子どもが自分でスプーンを使って食事をする場面をイメージしてみてください。自分でスプーンを使って食事をする=自分で物事を行う機会が提供され、成功体験を積むことで、子どもは自主性を育み、自信が持てるようになります。
一方で、過度に保護されたり、厳しく否定される経験が多い場合、子どもは自分の能力に対して疑いを抱いたり、恥を感じるようになったりします。
エリクソンは、この時期に自律性をうまく発達させることが、その後の進展において重要であると述べています。この段階での成功と失敗は、その後の自立性や自主性に大きな影響を与えるため、適切なサポートが必要です。
③幼児期後期(3~6歳)
幼児期後期(3歳〜6歳)は、子どもが「やってみたい!」という気持ちを強く持ち、積極的に行動する時期です。エリクソンの発達段階理論は、この時期の課題を「自主性 vs. 罪悪感」とし、自分で考えて行動する経験が大切だとしています。
たとえば、公園で子ども同士が遊んでいるとき、「砂で遊ぼう!」と提案する子もいれば、鬼ごっこのようにルールが決まっている遊びをしたがる子もいます。
その提案がうまく受け入れられれば「自分のアイデアが受け入れられた!」という自信につながりますが、ときには友だちを押しのけたり、思い通りにならず泣いてしまったりしてしまうこともあります。このとき、大人が「そんなことをしてはダメでしょう!」と頭ごなしに叱ってしまうと、「自分が何かするのはよくないことなのかな?」と罪悪感を持ちやすくなります。
この時期は、たとえ失敗したとしても「やってみてもいいんだ!」と感じられる環境が大切です。子どもの積極性を尊重しつつ、適切にフォローすることで、自己肯定感が育まれていきます。
④学童期(6~13歳)
学童期(6歳〜13歳)は、子どもの「もっとできるようになりたい!」と努力する気持ちを育む時期です。エリクソンの発達段階理論では、「勤勉性 vs. 劣等感」がこの時期の課題とされ、勉強や運動などの成功体験が自信につながると述べています。
たとえば、算数の問題が解けたときや、体育の授業で縄跳びがうまく跳べたときなどは、子どもは「やればできる!」と誇らしさを感じます。
一方で、「なぜこんなこともできないのか!」と責められたり、頑張っても認めてもらえなかったりすると、子どもは「どうせ自分なんて……」と自信を失い、挑戦する意欲をなくしてしまいます。
大切なのは、結果だけでなく、努力の過程を認めてあげることです。「頑張ったね!」「昨日よりも上手にできるようになったね!」と声をかけるだけで、子どもは「もっとやってみよう!」と思えるようになります。
子どもの挑戦する気持ちを大切にしながら、成長を見守っていきましょう。
⑤青年期(13~22歳)
青年期(13歳〜22歳)は、「自分は何者なのか?」と悩むことが増える時期です。エリクソンの発達段階理論では、「アイデンティティーの確立 vs. 役割の混乱」が課題とされ、進路や人間関係を通じて自分や自己を見つけようとします。
たとえば、高校生になると「将来何になりたい?」という話題が自然と出ます。「私は政治家になりたい」「学者になる」というようにはっきりと答えることができる人もいるでしょう。しかしながら、明確な答えを持ち合わせておらず、「自分は何がしたいのだろう?」「本当にこの道でいいのだろうか?」と惑う人も少なくありません。
さらに、この時期は友人関係や恋愛を通じて、自分の価値観が形成されていく時期でもあります。友だちとぶつかることもあれば、誰かの意見に流されてしまうこともあるでしょう。
しかし、それらの経験を通して自分という人間を確立することができます。
このとき、大人はどのような対応をすべきでしょうか。ベストなのは、無理に答えを求めるのではなく、若者がさまざまなことを試しながら「自分らしさ」「やりたいこと」を見つけることができるよう、見守ることです。
⑥成人期(22~40歳)
成人期(22歳〜40歳)は、人との深い関係を築くことが大きなテーマになります。エリクソンの発達段階理論は、この時期の課題を「親密性 vs. 孤独」とし、恋愛や結婚、友情、職場の人間関係などを通じて、信頼できる相手とつながることが大切だとしています。
たとえば、仕事が忙しくて疲れているとき、何でも気兼ねなく話せる友だちと食事をすると「私は一人じゃない」と安心することができます。SNSでのイイネやメッセージのやり取りなどでも誰かとつながっているという安心感が得られます。
一方で、「今日は誰とも話していない」「自分のことを理解してくれる人がいない」と感じると、孤独感が深まり、社会とのつながりを見失うこともあります。
親密な関係は必ずしも結婚や恋愛だけに限るものではありません。大切なのは「この人なら自分を受け入れてくれる」「この人はわかってくれる」と思える存在がいることです。
信頼できる友だちや仲間との深いつながりや親密な関係は、充実した人生を送る一助となるでしょう。
⑦壮年期(40~65歳)
壮年期(40歳〜65歳)は、「自分は社会の中でどのような役割を果たしているのだろうか?」と考えることが増える時期です。
エリクソンの発達段階理論は、この時期の課題を「生産性 vs. 停滞」とし、仕事や家庭、地域活動を通じて社会に貢献することが重要だとしています。
たとえば、職場で後輩を指導し、「先輩ありがとうございます。勉強になりました!」と言われたとき、自分の経験が役に立ったと実感できて誇らしい気持ちになることでしょう。
また、子どもが成長し、親の生きざまや自分の教えを生かしている姿を見ると、「親としての役目を果たせているようだ」と感じることもあるでしょう。
一方で、仕事や家庭での役割を見失うと、「自分はもう必要とされていないのかもしれない」と不安にかられるケースも少なくないでしょう。
大切なことは、幾つになっても「自分にはできることがある」「私は必要とされている」と思える環境をつくり、その中に身を置くことです。
それは何も仕事に限った話ではありません。趣味や地域活動などを通じてでも、コミュニティーや他者と関わることで、社会とのつながりを実感することができます。
⑧老年期(65歳以上)
老年期(65歳以上)は、「これまでの人生はどうだったのか?」と振り返ることが増える時期です。
エリクソンの発達段階理論は、この時期の課題を「自我の統合 vs. 絶望」とし、過去の経験を肯定的に受け止められるかが心の充実感に影響するとされています。
たとえば、長年働いてきた人が「自分は頑張った」と思えれば、穏やかな老後を過ごせます。しかし、「もっと違う選択をすればよかった」「もっと別の人生が歩めたはずだ」と後悔が募ると、孤独や喪失感に苛まれることもあります。人生の満足感は、過去をどう受け止めるかによって変わると言っても過言ではありません。
一方で、過去を振り返るだけが老年期ではありません。新しい趣味を始めたり、孫と遊ぶ時間を楽しんだりすることで、人生の新たな意味を見出すことができますので、何事も食わず嫌いをせずに挑戦することが大事です。
エリクソンの発達段階理論を知っておくメリットは?
エリクソンの発達段階理論を知ると、子どもの成長をより深く理解できるようになります。
たとえば、思春期の反抗期も「アイデンティティーを模索する大切な過程だ」と考えることができれば、必要以上にイライラせずに済むかもしれません。
教育や子育てだけでなく、人間関係全般に役立つ考え方なので、ぜひ参考にしてみてください。
子どもにもたらすメリット

【子どもの自己理解を助ける】
エリクソンの発達段階理論を知ると、子どもがどういう風に成長し、どのような壁にぶつかるのか、何を考えているのかを理解しやすくなります。
たとえば、学童期の「勤勉性 vs. 劣等感」の時期では、「頑張ればできる!」「できるようになった!」という成功体験がとても重要になっていきます。
そして、親や先生がこの理論を理解していると、子どもがどんな悩みを抱えているのかに気づきやすくなるのはもちろんのこと、適切に対処しやすくなります。
たとえば、計算が苦手で、「算数は向いてないから、嫌いだ、やりたくない」と落ち込んでいる子がいるとしましょう。このとき、計算練習を積み重ねて正解できるようになったり、制限時間内に解ける問題数が増えたりすると、達成感を味わうことができます。この達成感の積み重ねが自己肯定感を育む手助けとなります。
また、何かにつけて反論や反抗し、言うことを聞かない子の場合にもこの理論は有効です。
なぜならば、「今はアイデンティティーの確立時期で、大人の階段を登っているのだな」と冷静に受け止めることができるからです。
こうした視点を持つことで、大人も子どもも互いにストレスを減らし、より良い関係を築いていくことができるでしょう。
【子どもの自信につながる】
エリクソンの発達段階理論を知ると、子どもの「やったぞ、できるようになった!」という自信がどのように育つのかがわかります。
この理論を親や先生が知っていると、子どもの努力に寄り添いやすくなります。
正解でも、間違っていても、「頑張ったね!」「少しずつ上達しているよ!」と声をかけるだけで、子どもは「褒めてもらえた! もっとやってみよう」と思えるものです。
逆に、周囲の大人から「どうしてこのようなこともできないのか!」と否定されると、劣等感を抱いてしまうこともあります。
大人が適切なサポートをすることで、子どもの成長は大きく変わってきます。温かく見守る心の余裕を持ちましょう。
【良好な人間関係を築きやすくなる】
エリクソンの発達段階理論は、子どもの人間関係の築き方にも深く関わってきます。
たとえば、乳児期の「基本的信頼 vs. 不信」の段階では、親が赤ちゃんの泣き声にすぐに応え、抱きしめたり、声をかけたりすることで、「この人は自分を大切にしてくれる」という安心感が芽生えるとともに、泣くことが一つの手段であることを学びます。
逆に、泣いていても放置されることが多いと、人に対する不信感を抱きやすくなり、自分の要求が通らないことへのフラストレーションが溜まってしまいます。
学童期の「勤勉性vs.劣等感」では、子どもは友だちと協力しながら努力するということの大切さを学びます。
大人が適切にサポートすれば、子どもは自分に自信を持ち、人との信頼関係を築く力を養っていきます。些細な声かけや共感を怠らず、子どもの成長を見守りましょう。
【心理的に安定しやすくなる】
エリクソンの発達段階理論によると、子どもは各成長段階でさまざまな心理的課題に直面します。
たとえば、乳児期や幼児期では、親が子どもの気持ちに寄り添い、「大丈夫だよ」「一人じゃないからね」と声をかけることで、安心感が育まれます。
逆に、泣いていても無視されたり、愛情表現が不足していたりすると、人を信じるのが難しく感じるようになってしまうケースも中にはあります。
また、学童期の「勤勉性 vs. 劣等感」では、努力を認められる経験が重要になってきます。
学校の合唱コンクールで、音程がうまく取れずに落ち込んでいるときなどに、先生から「練習の成果が出ているから自信持って声を出そう」と声をかけてもらえると自信を喪失せずに済みます。
子どもは周囲の関わりの中で自信や信頼を少しずつ積み重ねていきます。安心して成長できるよう、親身に寄り添うことを心がけましょう。
【保護者にもたらすメリット】

【 子どもの理解が深まる】
エリクソンの発達段階理論を知ると、子どもが今どのような心理的課題に直面しているのかがわかり、親としてどのように支えればよいかが考えやすくなります。
たとえば、青年期の「アイデンティティーの確立 vs. 役割の混乱」の時期には、思春期特有の悩み(進路や将来、交友関係など)にぶつかります。そんなときでも、周囲の大人が辛抱強く見守り、背中を押すようなアドバイスを行うことで、迷いが消え、自信を持って「わが道」を行きやすくなります。
また、学童期の「勤勉性vs.劣等感」の段階では、前述した通り、努力を認められる経験が大切です。褒めたり、認めたりする言葉をかけることで、モチベーションが上がるのはもちろんのこと、苦手意識も薄れやすくなります。
子どもは、大人の関わり方次第で大きく変わります。ちょっとした声かけや励ましが、自信や挑戦する意欲につながることを念頭に置いて接しましょう。
【親子の信頼関係が強化される】
エリクソンの発達段階理論を知ると、親子の信頼関係の築き方がよく分かります。たとえば、幼児期の「基本的信頼 vs. 不信」の時期、子どもは親が自分を受け入れてくれることで、自分以外への他者に対する信頼感を育んでいきます。
また、学童期の「勤勉性 vs. 劣等感」の期間ならば、できないことや人より劣っていることをあげつらうのではなく、できないという事実を受け入れつつ、どう伸ばしていくか、どう乗り越えていくかを子どもと一緒に考えるようにすることが重要です。
親のちょっとした声かけや関わりが、子どもの心を支える大きな力になります。日々の何気ないことでも信頼関係は深まりますので、些細なことでも褒めたり、認めたり、アドバイスをしたりするようにしましょう。
【発達状況に応じた対応ができる】
エリクソンの発達段階理論を知ると、子どもの成長をより深く理解できるようになるため、段階に応じた対応がしやすくなります。
たとえば、幼児期前期の「自律性 vs. 恥・疑惑」の段階では、子どもは「自分でやりたい!」という自主性や自立心が強くなります。家事のお手伝いや、自分で服を脱ぎ着する、歯磨きをするなどの行為がこれにあたります。
この時期は、親が手助けしたいという気持ちや、大人がした方が早いという気持ちを押し留めて、子どもが自分なりにやり遂げる様子を見守りましょう。
このように、各段階に応じて関わる大人がすべきこと、した方がよいことをあらかじめ知っておくと、落ち着いて適切に対処することができるため、ぜひエリクソンの発達段階理論を子育ての生かしてください。
子どものプログラミング教育なら、プログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOは、子どもが楽しく学べる工夫が満載のプログラミング教室です。
実際に体験する子どもたちの中には、最初は「難しそう」と不安げな様子でしたが、ゲーム作りをしていくうちに、「もっとやりたい!」と意欲を燃やしたり、創意工夫に勤しんだりする生徒もいます。
授業は少人数制をとっており、コーチが丁寧にサポートする為、プログラミングが初心者の子どもでも安心して授業を受ける事ができます。
また、保護者へのフィードバックも行っているため、子どもの成長を実感していただきやすいのも当教室の魅力です。
プログラミングを通じて、子どもの論理的思考や創造力を育てたいという保護者におすすめです。
まとめ
子どもの成長を見守る中で、「どうしてこのような行動をするのだろうか?」と悩むことは少なくありません。
そのようなときにエリクソンの発達段階理論を知っていると、子どもがどのような心理的課題と向き合っているのかが分かり、適切なサポートがしやすくなります。
悩んでいることや苦手に思っていること、失敗したことなどを怒ったり、放置したりするのではなく、その事実を受け入れ、かつ乗り越える手助けをすることが子どもの自主性や自立心、挑戦する意欲を育むうえで大切です。
子育てに悩んだり、迷ったりしている方は、今回ご紹介したエリクソンの発達段階理論をぜひ生かしてみてください。